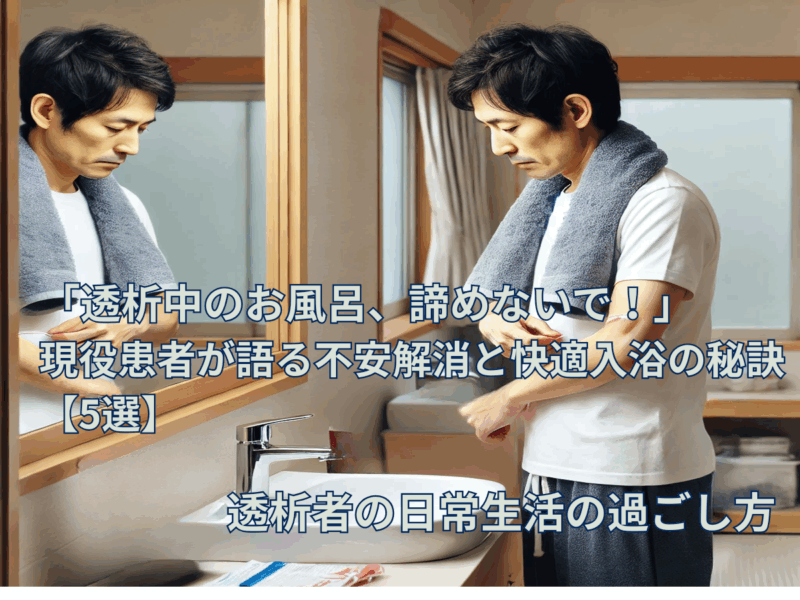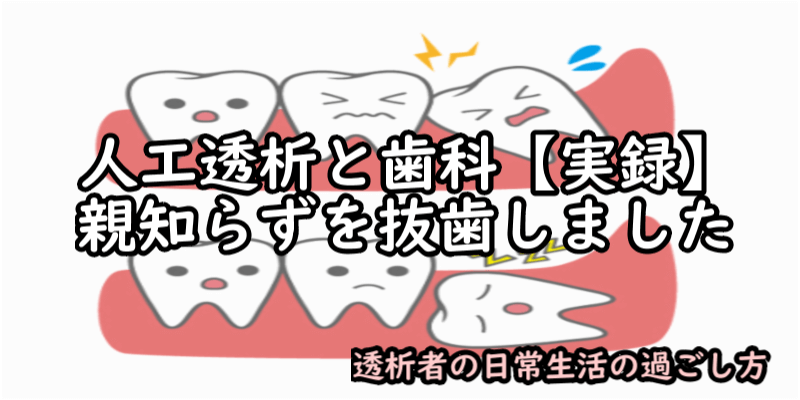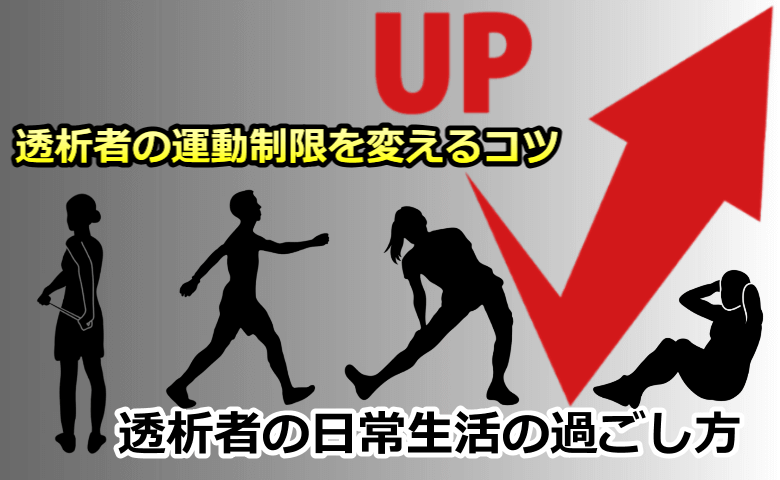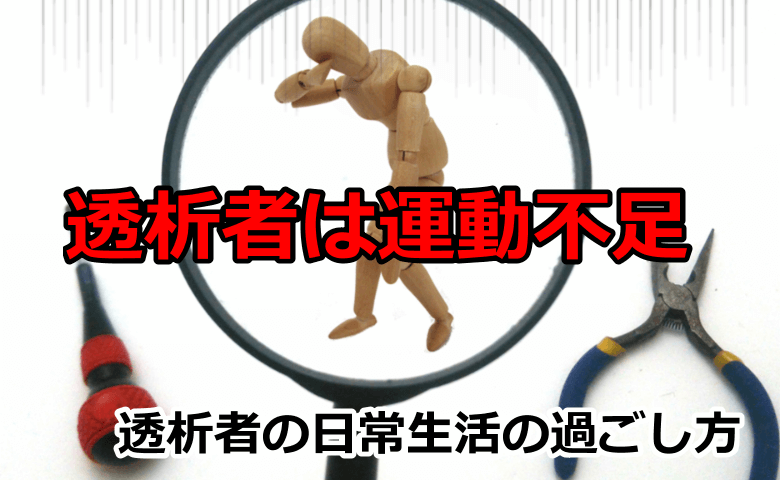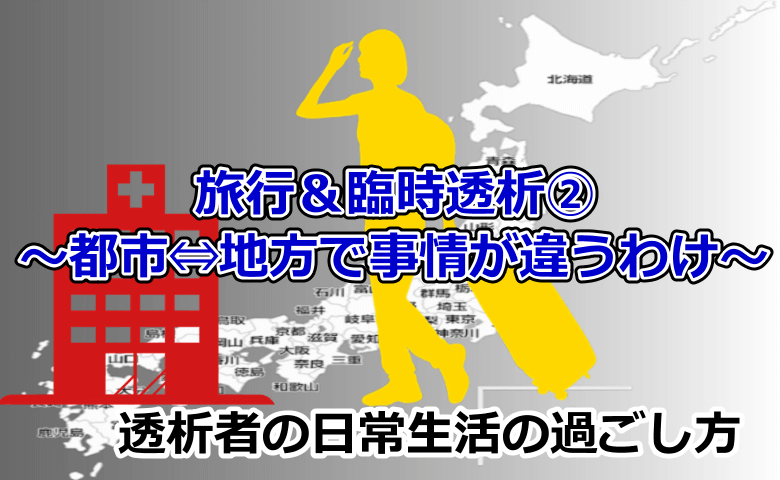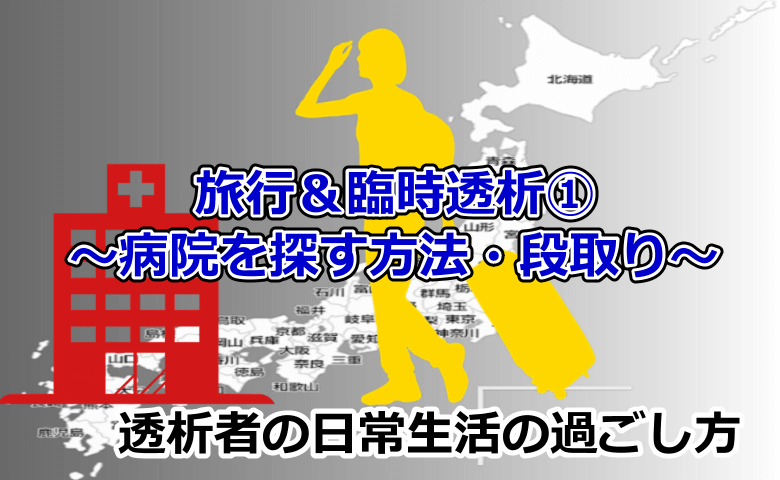透析患者の日常生活の過ごし方– category –
-

「透析中のお風呂、諦めないで!」現役患者が語る不安解消と快適入浴の秘訣5選
透析治療中のみなさん、毎日お疲れさまです。透析歴20年超、40代後半の会社員です。私も透析を始めたばかりの頃は、「お風呂、どうすればいいんだろう?」「シャントは濡らしていいの?」なんて、たくさんの不安を抱えていました。特に、透析導入初期はわ... -

【透析患者のワクチン接種】不安ですか?感染症対策と安心のコツ
「透析患者のワクチン接種ってどうなんだろう?」と日々感じている方も多いのではないでしょうか。「副反応が怖い」「透析への影響は?」そんな疑問や心配、すごくよく分かります。私も最初はそうでしたから。 同じ透析仲間として、ワクチン接種に関するリ... -

透析アプリを探してみました。現実は・・・
旅行透析(臨時透析)、昨今の災害状況をみて、スマートフォンやタブレットの存在意義は大きいと思います。 かつてはガラケーと呼ばれる携帯電話が隆盛を誇っていましたが、それに比べたら情報量は半端ないです。 ふと「透析者向けのアプリってある... -

【透析患者の歯のケア・口腔ケア】きちんと行っていますか?
今回取り上げたのは、透析と歯のケア、口腔ケアです。 一見、何の因果関係が無いように見えます。 はい、そういうふうに見えますね。 というのも、、書籍や病院のWebページなどをみても、透析患者の歯のケア、口腔ケアについて言及したものは少ないです。... -

人工透析中、歯科で抜歯しました。注意点もいろいろ!【実録】
透析しはじめてから4、5年しての話しになります。 奥歯に違和感が出てきて、日が経つごと痛みが増してきました。 かかりつけの透析医には伝えていました。「何となく痛いのだ」と。 一番の最悪シナリオは、透析中に痛みだし、4~5時間そのような状... -

非透析日の運動療法【OFF HD エクササイズ】を紹介!
透析日の運動、透析中に行う運動のことを【ON HD エクササイズ】と呼びます。 それに対して非透析日、つまり透析でない日に行う運動のことを【OFF HD エクササイズ】と呼んでいます。 これは透析でない日に行う運動なので、ふだんの生活の場面にお... -

透析患者|運動制限を変えるコツは【無理しない・楽しむ】の2点!
今回は血液透析患者の運動制限について取りあげていきます。 以降、血液透析患者を「透析患者」、スポーツや競技、運動などをまとめて「運動」と略称します。 前回の「透析患者は運動不足!骨格筋量の減少が顕著・末梢動脈疾患も。」の続編的な位置... -

透析者は運動不足!骨格筋量の減少が顕著・末梢動脈疾患にも。
透析導入時や透析の回診の際に医師からこんなふうに聞かれますよね? 「体調・血圧は大丈夫ですか?」 「薬の飲み忘れていない?ちょっとリンの値が高いね・・・どんな食べ方をしました?」 そして・・・ 「筋肉量を落とさないで(維持する... -

【旅行透析】東京は観光・病院に交通も便利!でも地方だったら
惜しまれながら「寝台列車がなくなってしまった」と嘆いているうちに、また復活の逃しが出てきましたね。 「あの寝台列車に一度は乗りたかったな〜」とそうつぶやき、思い浮かべているうちに、車中連泊ありの豪華列車に関する旅行やツアー、高速バスなどが... -

【旅行・出張先で臨時透析】病院を探す方法・段取り教えます!
ここでは、旅行・出張先などで行う臨時透析についてとりあげています。 透析患者でも、特に透析導入者で「血液透析となると、旅行・出張って難しいですよね?」という声を多く聞くことがあります(血液透析のことをを以下、透析とします)。 確かに旅行・...
12