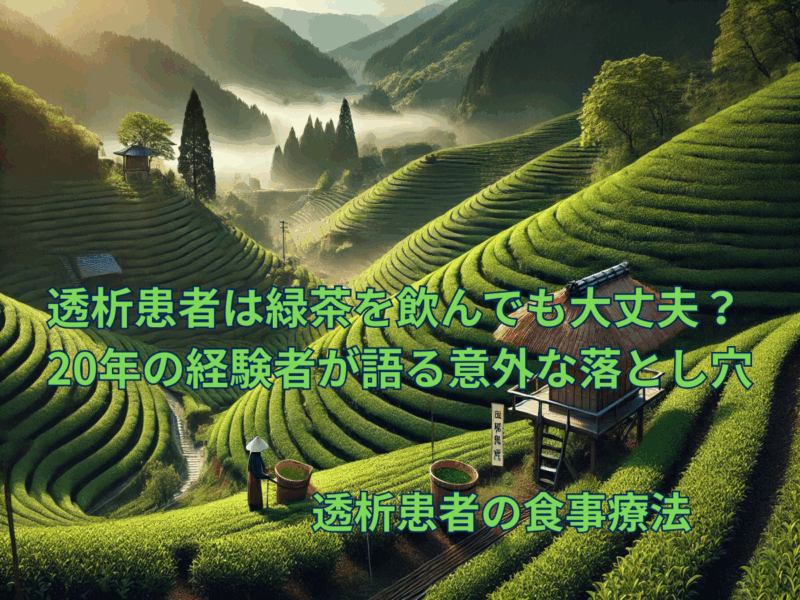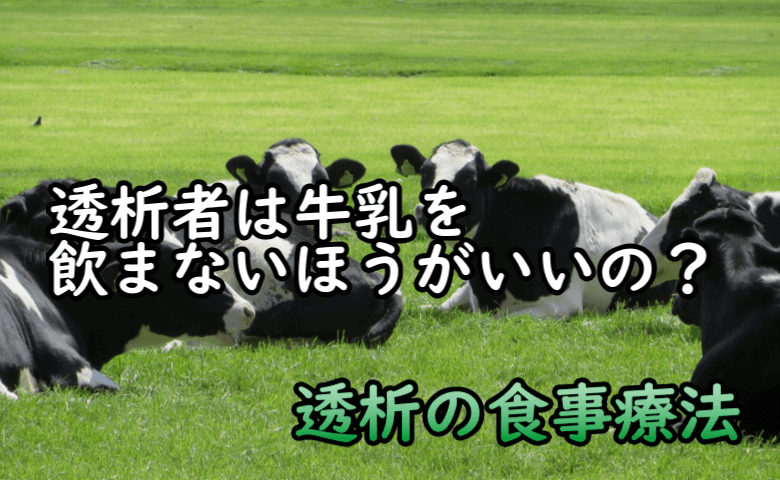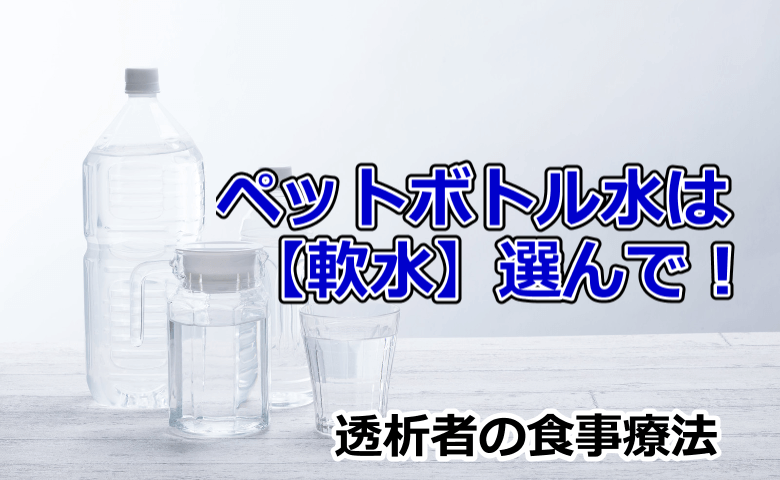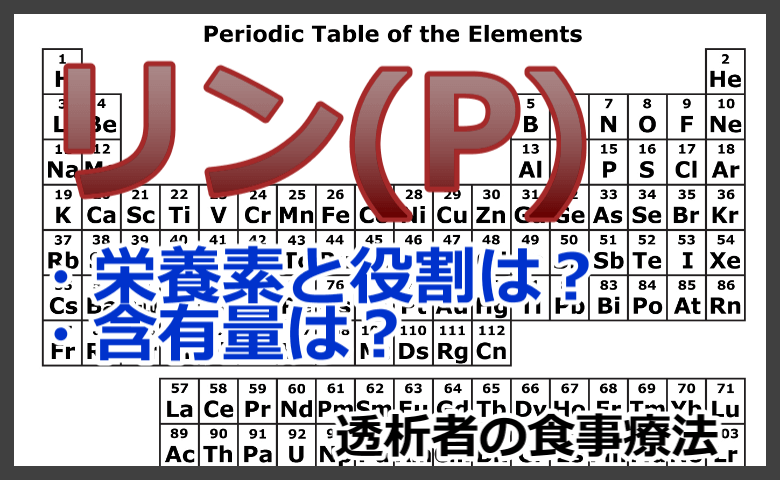透析患者の食事療法– category –
-

「透析患者はりんごを諦めるな!」カリウム制限でも賢く楽しむ秘訣話
透析治療を受けている皆さん、特に食事制限、中でも果物のことで悩んでいませんか? 「透析患者はりんごを食べちゃダメなの?」そんな疑問や不安を抱えている方、結構多いんじゃないでしょうか。私も導入当初はそうでした。 毎年、親類からりんごが届けら... -

【透析患者とみかん】カリウム怖い!?賢い食べ方と安心のヒントを伝授
あの甘酸っぱい香り、家族と食べる温かい時間…みかんって、なんだか特別な果物ですよね。私も大好きなんです。でも、透析をしていると「カリウムが高いからダメ!」なんて言われて、寂しい思いをしている方も多いんじゃないでしょうか。食べたい気持ちと、... -

作り置き透析レシピ活用術|無理なく続く食事管理のコツを紹介!
透析治療中の皆さん、毎日の食事作り、本当に大変じゃないですか?特に透析導入初期の頃は、カリウムだ、リンだ、塩分だ、水分だって…制限が多くて、何を作ったらいいのか途方に暮れてしまいますよね。私も透析歴が20年を超えましたが、今でも食事管理は正... -

透析患者は緑茶を飲んでも大丈夫?20年の経験者が語る意外な落とし穴
透析患者にとって、水分管理や食事制限は切っても切れない悩みですよね。特に、大好きな緑茶を「飲んでもいいの?」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか? 緑茶にはカテキンなど健康に良い成分も含まれていますが、透析患者の場合は注意が必要... -

腎臓病で寿司控えてた。透析患者はカリウム・リンにも注意して!
あなたは回転寿司・高級寿司店に月何回、足を運びますか? 私は月1回くらい行きます。 私の家族も寿司が好きなので、回転寿司店に負けないくらい美味しいスーパーのお寿司を買ってきては、食べることもありますね。 それだけ、寿司は日本人の身近かにある... -

【透析者は牛乳飲まないほうがいい?】リン値、骨粗鬆症も心配!
私は透析をしはじめてからは、牛乳という牛乳はほとんど飲んでいません。 中学生、高校生の育ちざかりな頃ならば、特にアレルギーもなかったのでふつうに飲んでいました。 ハウス食品のブランドであるフルーチェ。簡単にデザートにして食べることも... -

透析者の食事/ペットボトルは【軟水】を選んで!硬水は危険です
今回は透析者の食事療法のうち、水分摂取の制限に関連するものとして「透析者のペットボトル水の選び方や飲み方」について取り上げています。 水分といっても水はもとより、お茶、コーヒー、紅茶、味噌汁・・・いろいろとあるのですが、ペットボト... -

コンビニ弁当・外食はリンが宝庫?便利だけど【毎日は危険】
「リン(P)の働き知ってる?透析者の過剰摂取は【リスク大】」では、1日の摂取量や耐容上限量、リン(P)含有量が多い食品を挙げました。 今回は透析中、コンビニ食や外食でどんな付き合い方をすればよい?ということで、おなじくリン(P)をと... -

リン(P)の働き知ってますか?透析者の過剰摂取は【リスク大】
リンという元素は聞いたことはあるでしょうか。 「マッチの原料」とか「赤潮」の原因といったら、きっと思い浮かべられるのではないでしょうか? 小・中学生の理科の授業では、空気中では自然発光を示すことの実験を、社会の教科書でも公害... -

透析【リン値の高い状態】は副甲状腺機能亢進症や血管石灰化に!
透析においては、慢性腎臓病の治療上ではあまり意識していなかった食事療養のなかに、「リン(P)の摂取に注意すること」が挙げられます。 現代の食生活において、加工品や冷凍品はとても身近なものであり、実に便利なものです。 ただ製造の過...
12