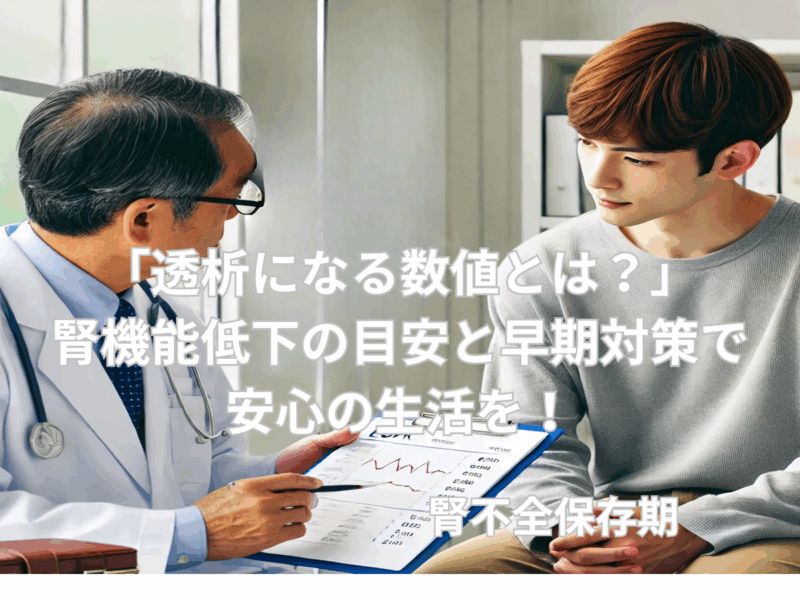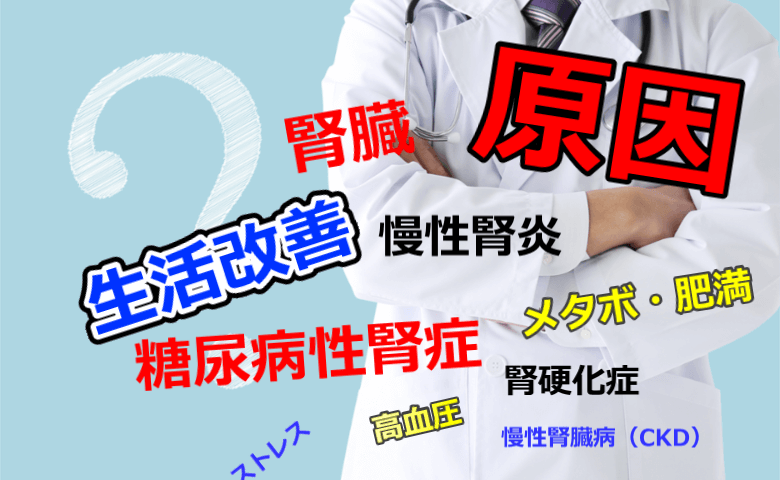腎不全保存期– category –
-

「透析になる数値とは?」腎機能低下の目安と早期対策で安心の生活を!
透析になる数値を知って不安を和らげよう 透析という言葉を聞いただけで、不安になる方も多いのではないでしょうか。私自身、透析生活が始まった当初は「これからどうなるんだろう」と夜も眠れないほど心配していました。 特に「どんな数値で透析が必要に... -

【透析へ至る原因疾患は何?】今すぐに生活改善を始めて!
「慢性腎臓病(CKD)は新たな国民病であって、人工透析予備軍だ」 と、「人工透析予備軍とは?気づかずに進行する慢性腎臓病に注意!」のなかで説明しました。 慢性腎臓病(CKD)ですが、実は単一の病名ではありません。 「腎臓が慢性... -

【人工透析予備軍とは?】気づかずに進行する慢性腎臓病に注意!
痛風予備軍、糖尿病予備軍、人工透析予備軍…。 何かと「〇〇予備軍」とついていますが、それらがどのような症状なのか聞いたことはありますか? 予備軍ということばの意味は、「いずれその状態になる可能性の高い人々」という意味で比喩的に使われ...
1