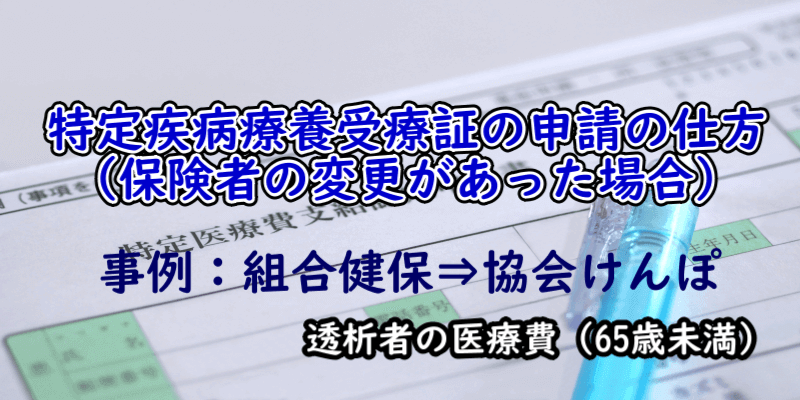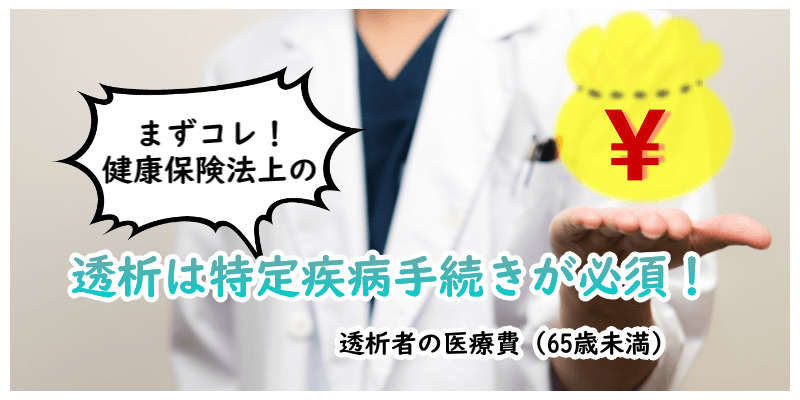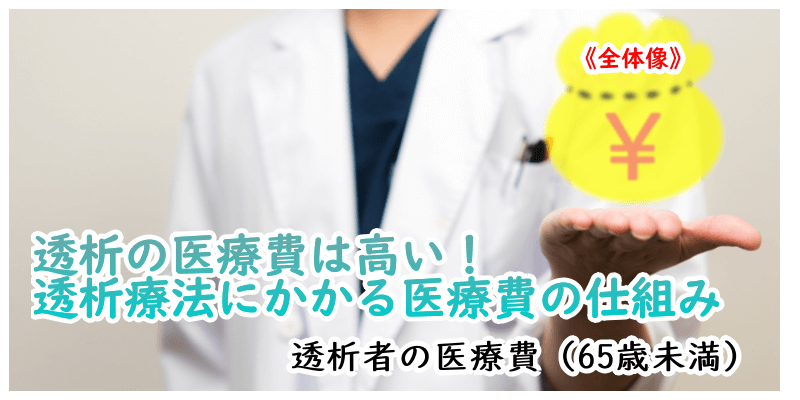透析患者の医療費(65歳未満)– category –
-

特定疾病療養受療証の申請の仕方(保険者の変更があった場合)
私は勤続10年超の会社に勤めていますが、「健康保険組合が解散するかもしれない」という報道が出て、その動向を見守っていましたが、結果的に解散することになりました。 透析導入して転職した頃は、静養と転職活動する時期があり、一時期国民健康... -

透析【特定疾病(特例)】手続きは必須!月額1万か2万円に。
健康保険法上にある高額療養費について、高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない疾病について「特定疾病」が3つ挙げられています。 その3つのなかに「人工透析を受けている慢性腎不全」があり、厚生労働大臣により認定されていま... -

透析の医療費は高い!しくみは知っておいたほうが良い理由。
透析療法にかかる医療費のしくみは、複雑でわかりにくいものです。 自分の医療費が「どのような制度を利用すれば負担が軽減されるのか」を知るだけでは、実は事足りません。 ご存知の通り、透析の医療費はとても高いものです。それだけ世間の目も厳...
1