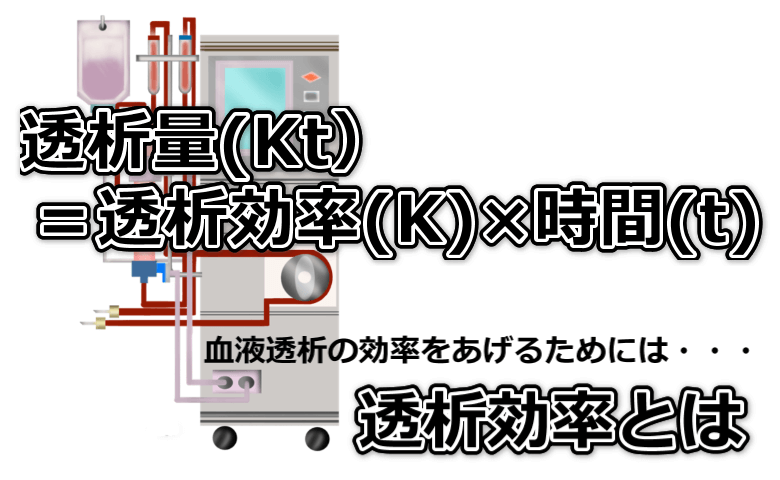透析効率とは– category –
-

「透析時間の延長はできますか?」そのひと声からはじまる。
「4時間透析」を行っている病院もありますが、4時間は最低限のもの、最低ラインであることは認識すべきです。4時間よりは30分でも1時間でも透析時間が長ければ、生命予後や合併症発症の遅延など後々影響してくることは言うまでもありません。 ... -

透析時間の決め方。えっ!4時間透析は【最低ライン】なの?
「4時間透析が当たり前!ですよね」 「いいえ、違いますよ。」 透析量については次の積算をあげていました。 「透析量(Kt)」=「透析効率(K)」×「時間(t)」 4時間透析よりも、もっと「透析時間を延ばす」「延長すること」が大事だと... -

血液透析の【効率】をあげるためにはどうすればいい!?
ここでお話しするのは「血液透析の効率をあげるためにはどうすればいいのか?」という内容になります。 ・「透析量(Kt)」=「透析効率(K)」×「時間(t)」という積で求められる ・透析者のシャントの状態、管理のしかたが悪ければ透析効率は落ちる!...
1