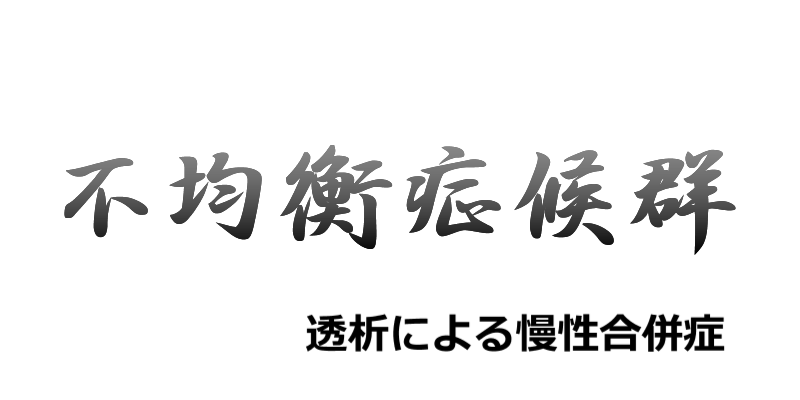透析による治療|慢性合併症– category –
-

透析導入者は【不均衡症候群】を乗り越えなければならない。
今回は特に透析導入時に多いとされる「不均衡症候群」について取り上げていきます。 私が透析しはじめたのは20代後半でしたが、不均衡症候群について看護師さんから説明を受けました。 末期の腎不全で尿毒症がひどくなり、もう目先、すぐに... -

透析による合併症。予防&対策は【食事療法】がもっとも有効!
ここでは透析による合併症について、取り上げています。 透析療法には「血液透析」と「腹膜透析」がありますが、どちらにしても特有の合併症はあります。 腹膜透析であれば、腹膜炎やカテーテル出口部・皮下トンネル感染症、被嚢性腹膜硬化症などが...
1