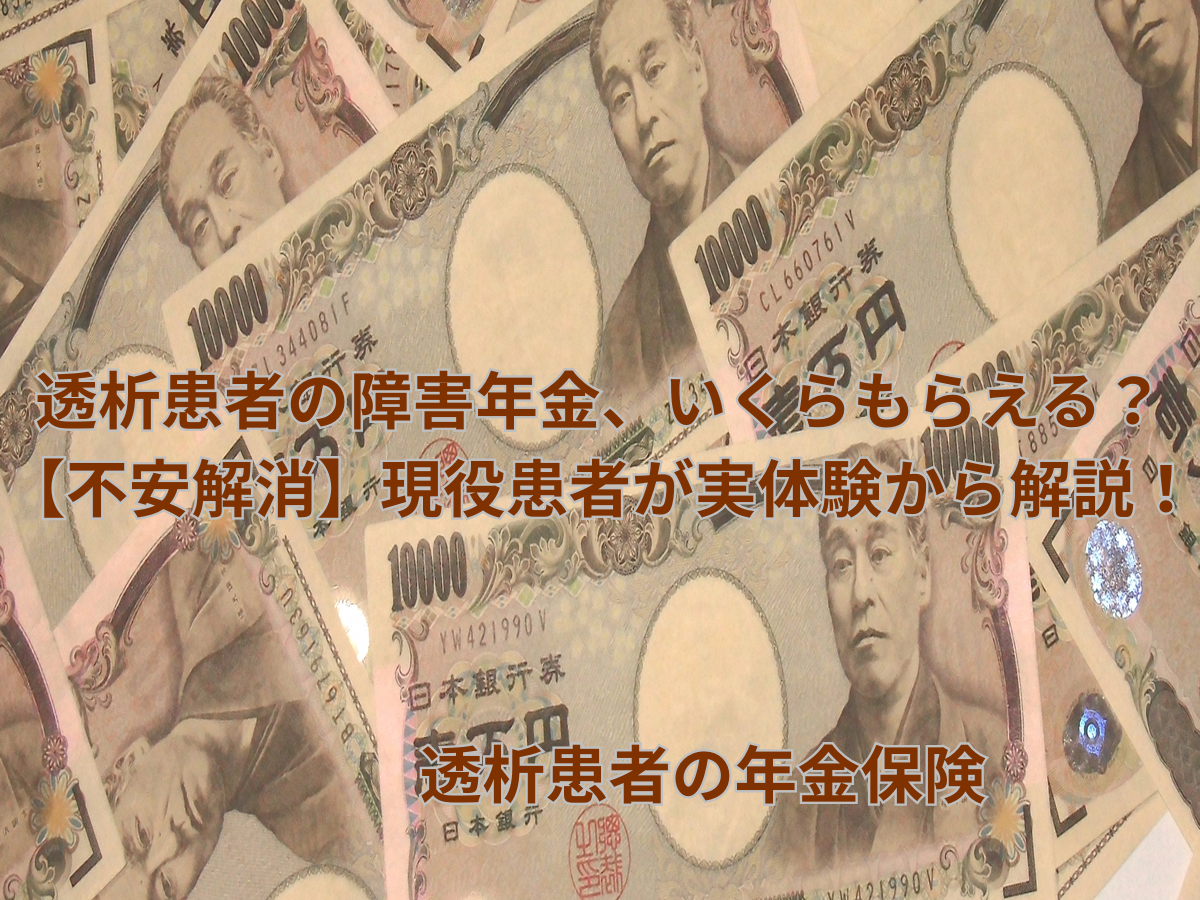
「透析と向き合うあなたへ。」お金の不安、少しでも軽くしませんか?
透析導入が決まった時、治療そのものはもちろん、「お金はどうなるんだろう?」
特に透析患者の障害年金はいくらもらえるのか、ものすごく不安だったのを覚えています。
あなたも今、同じような気持ちを抱えているかもしれませんね。この記事では、私自身の経験も踏まえながら、透析患者さんが受け取れる障害年金について、そして関連するお金の制度について、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。難しい専門用語はなるべく使わず、私が実際に感じたこと、困ったこと、そしてどう乗り越えてきたか、そんなリアルな声をお届けします。
この記事を読み終える頃には、漠然としたお金への不安が少しでも和らぎ、「よし、こうすればいいのか!」と前向きな気持ちになってもらえたら、これほど嬉しいことはありません。
透析患者がもらえる障害年金、ぶっちゃけいくら?
さて、一番気になるところですよね。障害年金、実際に「いくら」もらえるのか。これは、加入している年金制度(国民年金か厚生年金か)や、これまでの納付状況、そして家族構成によって変わってきます。だから、「ズバリ○○円です!」とは言えないのが正直なところなんです。
ただ、目安として知っておくことは大切ですよね。まず、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
- 障害基礎年金 これは、自営業の方やフリーランスの方、専業主婦(夫)の方などが主にもらう国民年金ベースのものです。透析患者さんの場合、多くは「障害等級2級」に認定されるため、その場合の年金額が基準になります。金額は毎年見直されますが、大まかには年間で約80万円弱くらいが目安でしょうか。もし、18歳未満のお子さんがいれば、加算もあります。
- 障害厚生年金 これは、会社員や公務員の方が加入する厚生年金ベースのものです。障害基礎年金に上乗せされる形で支給されます。計算方法がちょっと複雑で、これまでの給料(標準報酬月額)や加入期間によって大きく変動します。なので、人によって本当にまちまちなんです。障害基礎年金と合わせると、年間で100万円を超えるケースが多いですが、数百万円になる方もいれば、そこまで多くない方もいます。配偶者がいる場合の加算もありますね。
私が最初に自分の年金額(私は初診日が学生のときであり、社会人ではないので国民年金で計算されています)を知ったときは、「あ、これだけもらえるんだ…」と、正直ホッとしたのを覚えています。何せ治療費の心配が大きかったですから。
でも、同時に「これだけで生活していくのは厳しいな」とも感じました。だから、年金はあくまで「支え」の一つとして捉えて、どうやって仕事と両立していくか、他の制度も活用できないか、具体的に考えるきっかけになりましたね。ぶっちゃけ、お金の計算は得意じゃないんですが、これは避けて通れない道でした。
正確な金額を知りたい場合は、やはり年金事務所に相談するのが一番です。「ねんきん定期便」などでも、ある程度の試算はできるかもしれません。
参照:透析にかかる障害年金は収入補填が目的。受給には納付【3要件】が必須!
参照:透析にかかわる障害年金制度。申請し【請求】しなければもらえない!
障害年金の等級って?透析患者は原則「2級」ってホント?
障害年金の話でよく出てくるのが「障害等級」です。透析患者さんは「原則として2級」と認定されることが多い、と聞いたことがあるかもしれません。これは、ある意味本当です。でも、「原則」ってところがミソなんですよね。
なぜ透析患者は原則2級なのか
じゃあ、なんで透析をしていると多くの場合「2級」になるんでしょうか。これは、国の定めた「障害認定基準」というルールに基づいています。難しい言葉で言うと、「腎臓の機能障害」の程度で判断されるわけですが、もっと簡単に言うと、「日常生活や仕事にどれくらい支障が出ているか」がポイントになります。
人工透析療法(血液透析や腹膜透析)を受けている場合、それは腎臓がほとんど機能していない状態、つまり生命維持のために不可欠な治療を受けている状態とみなされます。
週に数回、数時間の治療に拘束され、食事制限や水分制限もあり、合併症のリスクも常に抱えている。疲れやすさや体調の波もある。こうした状況は、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と判断され、これが障害等級2級に相当するとされているんです。
私自身、透析導入当初は頭の中ではわかっていても「なんで自分がこんな目に…」という気持ちばかりが出るとともに、同時に「でも、これで少しは経済的な不安が減るのかも」という複雑な思いがありました。だって、体がしんどいのは事実ですし、以前のように現場でバリバリ働くのは難しい。その状況を国が「障害」として認めてくれるというのは、ある意味、”救い”でもありました。
ただ、「原則」とついているように、必ずしも全員が2級とは限りません。例えば、他の重い病気も合併していて、日常生活がさらに困難な場合は1級になる可能性もありますし、逆に、透析導入後も比較的状態が安定していて、就労状況なども考慮された結果、3級(障害厚生年金のみ)や不支給となるケースも、ゼロではないようです。まあ、でも透析を受けている方の多くは2級と考えていいと思います。
2級と認定されることの「重み」と「支え」
障害等級2級と認定されることは、経済的な「支え」になることは間違いありません。治療費や生活費の足しになり、精神的な安心感にもつながります。これは本当に大きいです。
でも、忘れてはいけないのは、それが「障害の状態にある」という公的な認定でもあるということです。つまり、それだけ身体に負担がかかっている、という証明でもあるわけです。年金がもらえるからラッキー、なんて単純な話では決してない。私も時々、この「2級」という認定の重みを感じることがあります。元気な日もあれば、どうしようもなく体がだるい日もある。その波と付き合いながら生きていくことの証でもあるんですよね。
だから、年金はありがたく受け取りつつも、それに頼りきるのではなく、自分の体調と相談しながら、できる範囲で社会と関わり続けたい、そう思っています。年金はあくまで生活を支える「土台」の一つ。その上に、自分らしい人生をどう築いていくか、それが大切なんだと、20年超透析と付き合ってきて感じています。
障害年金をもらうための「壁」申請手続きのリアル
さて、障害年金がもらえること、等級のことが分かっても、自動的に振り込まれるわけではありません。自分で「申請」というアクションを起こさないといけないんです。これがまた、なかなか骨の折れる作業でして…。私も経験しましたが、ちょっとした「壁」に感じる人もいるかもしれません。
まずは何から始める?最初のステップ
「よし、申請しよう!」と思ったら、まずどこに行けばいいのか。基本的には、お近くの年金事務所か、街の年金相談センターに相談に行くのがスタートラインです。予約が必要な場合が多いので、事前に電話で確認するのがおすすめです。
そこで、「透析になったので障害年金を申請したい」と伝えると、必要な書類一式をもらえたり、手続きの流れを教えてくれたりします。これが第一歩。
でもその前に説明しておきたいのは、「初診日」の証明がめちゃくちゃ大事なんです! 初診日っていうのは、障害の原因となった病気(透析の場合は、腎不全の原因となった病気、例えば糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎など)で、初めてお医者さんにかかった日のこと。この初診日に、どの年金制度に加入していたか(国民年金か厚生年金か)で、もらえる年金の種類が決まるんです。
そして、この初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が必要になることが多い。これが、昔のことだったり、病院がなくなっていたりすると、証明するのが大変になるケースもあるんです。私の知り合いはこれでかなり苦労していました…。なので、申請を考え始めたら、まず自分の初診日がいつで、証明できるかを確認しておくのが、実はすごく重要だったりします。
主な必要書類としては、
- 年金請求書
- 戸籍謄本や住民票
- 診断書(これが一番重要!)
- 受診状況等証明書(初診日を証明するもの)
- 病歴・就労状況等申立書(自分で作成するもの)
などがあります。他にもケースによって必要な書類が出てくることも。書類を集めるだけでも一苦労ですよね。特に「診断書」は、透析を受けている病院の主治医に作成をお願いすることになります。医師も忙しいので、早めにお願いして、余裕をもって準備することが大切です。私の時は、診断書の内容について、先生と何度かやり取りしました。自分の状態を正確に伝えて、適切な内容で書いてもらうことが重要ですからね。
「病歴・就労状況等申立書」ここが勝負どころ!
必要書類の中でも、特に自分で書き上げる「病歴・就労状況等申立書」、これが実はめちゃくちゃ重要なんです! なぜかっていうと、診断書だけでは伝わらない、あなたの日常生活のリアルな状況や、仕事でどれだけ困っているかを、審査する人に伝えるための唯一の手段だからです。
「いつからどんな症状があって、どんな治療を受けてきて、日常生活でどんなことに困っているか、仕事(家事なども含む)にどんな支障が出ているか」などを、自分の言葉で具体的に書く必要があります。
ここは、遠慮せずに、正直に、そして具体的に書くことがポイントです。「疲れやすい」だけじゃなくて、「朝起きるのが辛く、午前中は集中力が続かない」「透析の翌日は特にだるくて、簡単な家事もままならない」「通勤電車で立っているのがきつく、何度も途中下車してしまう」みたいな感じで、できるだけ具体的に書くんです。
私もこれを書くのは結構大変でした。自分の弱さを改めて見つめ直す作業でもありますしね…。でも、「ここでしっかり書かないと、自分の大変さが伝わらないかもしれない」と思って、当時の状況を思い出しながら、一生懸命書いた記憶があります。
例えば、会議中にどうしても眠気に襲われてしまうこととか、パソコン作業が長時間続けられないこととか、そういう「具体的なエピソード」を盛り込むと、審査する側もイメージしやすくなるんじゃないかと思います。ここは、ある意味、あなたの状況を伝える「プレゼン資料」みたいなもの。ちょっと大げさかもしれないけど(笑)、それくらいの気持ちで取り組む価値はあると思います。
審査期間はどれくらい?待つ間の心境
さて、全ての書類を揃えて年金事務所に提出したら、あとは審査結果を待つだけ…なんですが、この待つ期間がまた、長いんです!
一般的には、申請してから数ヶ月かかると言われています。私の時も、たしか3ヶ月くらいはかかったと思います。 もっとかかる場合もあるようです。この間、「ちゃんと審査されてるかな…」「書類に不備はなかったかな…」「もし不支給だったらどうしよう…」なんて、色々考えちゃって、結構ソワソワ、ドキドキする日々でした。
そして、ある日突然、年金事務所から封書が届くんですよ。これが「年金証書」なら、無事に受給決定! 本当にホッとした瞬間でした。
もし、「不支給決定通知書」や「却下通知書」が届いた場合は、残念ながら今回は認められなかったということになりますが、諦めるのはまだ早いです。決定に不服がある場合は、「審査請求」という不服申し立ての手続きをすることができます。専門家(社会保険労務士さんとか)に相談するのも一つの手ですね。
とにかく、申請手続きは時間も労力もかかりますが、もらえる権利があるものですから、諦めずにチャレンジしてほしいと思います。
参照:透析にかかわる障害年金制度。申請し【請求】しなければもらえない!
障害年金だけじゃない!透析患者が使える「お金の支え」
障害年金は大きな支えですが、透析患者さんが利用できるお金に関する制度は、それだけではありません。むしろ、これらを知っておかないと、大変なことになりかねません。特に医療費に関する制度は、絶対に押さえておきたいポイントです。
特定疾病療養受療証 これがないと始まらない!
まず、透析治療を受ける上で絶対に、絶対に必要になるのが「特定疾病療養受療証」です。これは、高額な医療費がかかる特定の病気(人工透析はその代表例です)の患者さんの自己負担額を軽減してくれる、超重要な制度です。
通常、医療費って3割負担とかですよね? でも、透析治療は毎月何十万円とかかる、めちゃくちゃ高額な治療です。もしこれを3割負担なんてしていたら、あっという間に破産してしまいます…。
そこで、この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、1ヶ月の自己負担額の上限が、原則として1万円(※所得によっては2万円になる場合もあります)になるんです! これがないと本当に生活が成り立ちません。
これは、加入している健康保険(国民健康保険、会社の健康保険組合、協会けんぽなど)に申請すれば発行してもらえます。透析導入が決まったら、病院のソーシャルワーカーさんなどが手続きをサポートしてくれることが多いと思いますが、自分でもしっかり確認しておきましょう。毎月の透析治療費が、この制度のおかげで、なんとか支払い可能な範囲に収まっているわけです。
障害者手帳 メリットはいろいろ
次に、「身体障害者手帳」です。人工透析を受けている場合、多くは「腎臓機能障害」として、身体障害者手帳の交付対象となります。等級は、状態によって異なりますが、多くは1級に該当することが多いようです。(障害年金の等級とはまた別物なので注意してくださいね)
この手帳を持っていると、いろんなメリットがあります。例えば、
- 所得税や住民税の障害者控除
- 自動車税などの減免
- 公共交通機関(JR、バス、タクシーなど)の運賃割引
- 高速道路料金の割引
- 公共施設(美術館、博物館、動物園など)の入場料割引または免除
- 携帯電話料金の割引
- NHK受信料の減免
などなど、本当に様々です。自治体によっては、さらに独自のサービス(例えば、福祉タクシー券の支給とか)がある場合も。これは、申請しないともらえない「権利」ですから、ぜひ取得しておくことをお勧めします。申請は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で行います。診断書などが必要になります。
私ももちろん持っていますが、特に税金の控除や交通費の割引は、地味に助かっています。塵も積もれば、ですからね。
参照:透析前後でも身体障害者手帳は申請できます。窓口で確認して!
自治体独自の助成制度も見逃せない
国の制度だけでなく、都道府県や市区町村が独自に行っている医療費助成制度がある場合もあります。例えば、「重度心身障害者医療費助成制度」などがその例です。これは、障害者手帳の等級など、一定の条件を満たすと、医療費の自己負担分をさらに助成してくれる、というものです。
ただし、これは自治体によって制度の有無や内容が大きく異なります。所得制限がある場合も多いです。「特定疾病療養受療証」で自己負担は1万円(または2万円)になっているので、この制度の対象になっても、実質的な負担軽減はそれほど大きくない、というケースもありますが、それでも対象になるなら申請しておくに越したことはありません。
どんな制度があるかは、お住まいの市区町村の役所のホームページを見たり、福祉課や障害福祉課といった窓口に直接問い合わせてみるのが一番確実です。私も引っ越した時に、役所で「透析患者向けの助成って何かありますか?」って聞いてみて、利用できる制度を教えてもらった経験があります。情報収集は大事ですよ!
参照:【透析の保険適用はどうなってる?】医療費不安を解消する公的支援【完全ガイド】
障害年金をもらいながら働くということ
さて、障害年金を受給できるとなった場合、次に気になるのが「働きながらでももらえるのか?」ということですよね。特に私のような現役世代(氷河期世代ですが…)にとっては、死活問題です。
結論から言うと、障害年金をもらいながら働くことは、原則として可能です。障害基礎年金については、基本的に所得制限はありません(20歳前に初診日がある場合を除く)。
障害厚生年金については、働き方や収入によっては、年金額の一部または全部が支給停止になる可能性はあります。ただ、透析を受けている(障害等級2級)場合は、よほど高額な収入がない限り、支給停止になることは稀なようです。
とはいえ、「働く」と言っても、透析導入前と同じようにバリバリ働くのは、正直、難しいと感じる人が多いのではないでしょうか。私自身もそうです。
透析治療には時間も体力も使います。週3回、病院に通って4〜5時間。その前後の準備や移動時間も含めると、半日仕事です。透析のない日も、疲れやすかったり、体調が不安定だったりすることは少なくありません。だから、フルタイムで、非透析日は残業もこなして…というのは、かなりハードルが高い。
私の場合は、転職時にきちんと会社に、チームの上司や同僚に理解を得たうえで、仕事をあがっていますし、少なくともコロナ禍のときは在宅勤務もしたことがありました。
それでも、やっぱりしんどい時はあります。会議中に集中力が途切れたり、大事な時に限って体調を崩し損ねそうになっていたり…。自己管理はもちろん大切ですが、”限界”もあります。透析器歴が20年超となり、同じく会社の社歴も同じくらい。職場の同僚や上司の理解と配慮は、本当にありがたいです。これがなかったら、今の仕事を続けるのは難しかったかもしれません。
障害年金があるからといって、完全に仕事から離れてしまうのではなく、自分の体調と相談しながら、できる範囲で社会とのつながりを持ち続けること。それが、経済的な面だけでなく、精神的なハリや、社会的な役割を保つ上でも大切なんじゃないかな、と私は考えています。もちろん、無理は禁物ですよ!
仕事と治療の両立は、本当に簡単なことではありません。時短勤務、パートタイム、在宅ワーク、障害者雇用枠での就職・転職など、さまざまな選択肢があります。ハローワークや転職エージェントなども活用しながら、自分に合った働き方を見つけていくことが重要です。「正直、楽じゃないですよ!」毎日が試行錯誤です。でも、工夫次第で道は開ける、そう信じてやってます。
まとめ 透析と向き合い、制度を賢く利用して生きていく
透析治療と向き合う中で、「お金」の不安は、どうしてもついて回ります。その不安を少しでも和らげるために、障害年金という制度があること、そしてその金額の目安や申請方法について、私なりの経験を交えながらお伝えしてきました。
障害年金は、透析患者にとって間違いなく大きな経済的な支えとなります。申請手続きは少し大変かもしれませんが、もらえる権利があるものですから、ぜひ諦めずに情報を集め、行動に移してみてください。
そして、障害年金だけでなく、「特定疾病療養受療証」や「身体障害者手帳」、自治体独自の助成制度など、利用できる制度は他にもあります。これらの制度を賢く活用することで、医療費の負担を減らし、生活の安定につなげることができます。
お金の心配が少しでも軽くなれば、治療に専念しやすくなりますし、前向きな気持ちで日々の生活を送ることにもつながるはずです。透析をしていても、仕事や趣味、旅行など、諦めずに自分らしい人生を送ることは可能です。
一番大切なのは、一人で抱え込まないこと。分からないこと、不安なことは、遠慮なく病院のソーシャルワーカーさんや、年金事務所、役所の窓口、あるいは私のような経験者に相談してみてください。情報を集め、制度を理解し、そして行動する。それが、透析と上手に付き合いながら、より良い生活を送るための鍵だと、私は信じています。