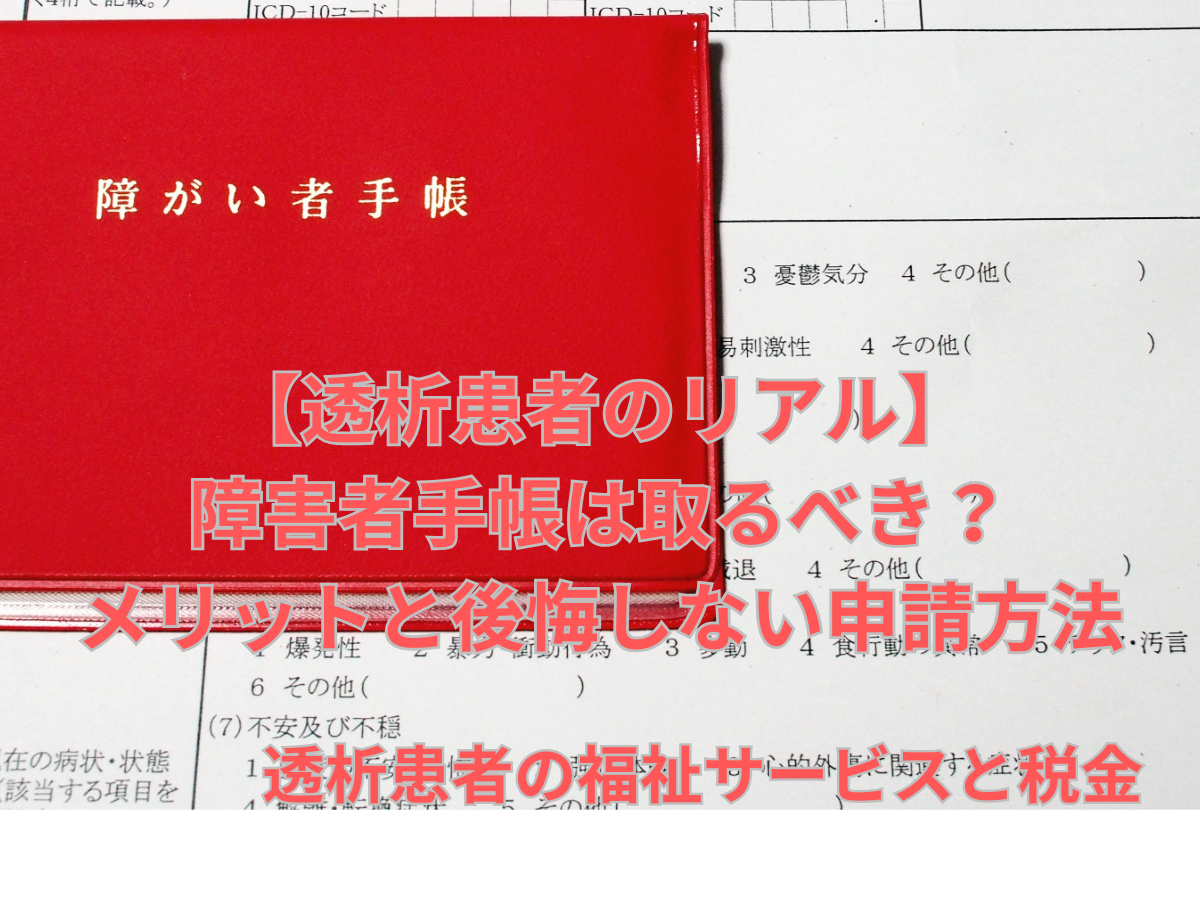
透析治療が始まると、生活が一変します。治療そのものへの不安はもちろん、「これからどうなるんだろう」「お金のことは?」「仕事は続けられる?」…次から次へと疑問が湧いてきて、夜も眠れないなんてことも。
私も透析導入当初は、まさにそんな感じでした。特に透析と障害者手帳の関係って、なんだかよく分からないし、ちょっと抵抗を感じる人もいるかもしれません。
私は透析歴20年超え、現役会社員をしています。今回は、そんな皆さんの不安や疑問に、長年の患者経験から正直にお答えしていきたいと思っています。「障害者手帳って、ぶっちゃけどうなの?」「申請は面倒?」「どんなメリットがあるの?」
この記事を読めば、透析患者にとっての障害者手帳のリアルな位置づけや、あなたが損しないための情報がきっと見つかるはずです。私自身の体験談も交えながら、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。一緒に、少しでも前向きな透析ライフを目指しましょう!
透析と障害者手帳の関係って? – まずは基本を押さえよう
透析を始めたばかりの方や、これから導入を考えている方にとって、「なんで透析で障害者手帳?」って思うかもしれませんね。私も最初はピンときませんでした。でも、これ、透析患者にとってはすごく大事なことなんです。
なぜ透析患者が障害者手帳の対象になるのか?
すごく簡単に言うと、透析治療が必要な状態、つまり「腎臓機能障害」が、身体障害者福祉法で定められた障害等級に該当する場合が多いからなんです。腎臓って、体の中の老廃物をろ過してくれる超重要な臓器ですよね。その機能が著しく低下して、自力では生命維持が難しくなり、人工的にその機能を補う透析が必要になる。これは、日常生活や社会生活に大きな制約を受ける状態だと国が認めている、ということなんです。
等級は、腎臓の機能の状態、具体的にはeGFR(推算糸球体濾過量)の値などをもとに判定されます。多くの場合、透析を導入すると、身体障害者手帳の1級や3級などに該当することが多いと言われています。もちろん、これは医師の診断に基づいて判断されるので、一概には言えませんけどね。私の場合は、導入後すぐに申請して1級に認定されました。当時は、等級がどうこうというより、それだけ自分の腎臓が頑張れなくなっちゃったんだな、と受け止めるしかなかったですけど。
障害者手帳を持つことのメリット、デメリット(正直な体験談)
じゃあ、実際に障害者手帳を持つと、どんな良いことがあるのか?結構たくさんあります。一番大きいのは、やっぱり経済的な支援かと思います。
- 医療費の助成 これは本当に助かります。透析治療って、めちゃくちゃお金がかかります。でも、手帳と特定の医療費助成制度(特定疾病療養受療証とか、お住まいの自治体の制度とか)を組み合わせることで、自己負担額がかなり抑えられます。これが無かったら、正直、治療を続けるのは相当厳しい…っていうのが本音です。
- 税金の控除・減免 所得税や住民税、自動車税なんかが安くなることがあります。これも地味に大きい。私も地方在住で、車通勤して会社や通院で使っています。年末調整や確定申告で手続きが必要だけど、忘れずにやりたいところですね。
- 公共料金などの割引 電車やバス、タクシーの運賃割引、携帯電話料金の割引、美術館や映画館の入場料割引など、いろいろあります。全部が使えるわけじゃないし、地域や事業者によって内容も違うんですが、知っておくとお得な場面は結構ありますよ。
- 就職・転職での配慮 障害者雇用枠での応募が可能になったり、会社によっては通院への配慮が得られやすくなったりします。これについては後で詳しく話しますね。
まあ、こんな感じでメリットはたくさんあるわけです。
じゃあ、デメリットは? って聞かれると、うーん…正直、制度上のデメリットっていうのは、私自身はあまり感じていません。ただ、人によっては「障害者」というレッテルを貼られるような気がして、心理的な抵抗を感じる、というのはあるかもしれません。
確かに私は運営者の紹介でも触れましたが介護していました。そのような立場になったとき、最初に手帳を受け取ったときは、なんだかんだといって複雑な気持ちでした。「ああ、自分は『障害者』になったんだな」と。
でも、透析を続けていく上で、この手帳があることで受けられるサポートは、やっぱり無視できないくらい大きい。だから、私は「これは治療を続けて、自分らしく生きていくための『お守り』みたいなものだ」って考えるようにしました。あとは、手帳を持ち歩くのがちょっと面倒とか、更新手続きがあるとか、そういう手間はありますが・・・。でも、メリットと比べたら、まあ、許容範囲かな、と私は思っています。
結局のところ、手帳を持つかどうかは個人の判断です。でも、もし迷っているなら、一度、どんなメリットがあるのか具体的に調べてみて、自分にとって必要かどうか考えてみる価値は十分にあると思いますよ。
障害者手帳、どうやって申請するの? – 私の経験談も交えて
さて、じゃあ実際に障害者手帳を申請しよう!と思ったら、どうすればいいのか。手続きって聞くと、なんだか面倒くさそうですよね。
はい、正直ちょっと面倒です(笑)。でも、まあ、一つ一つやっていけば大丈夫。私が申請した時のことを思い出しながら、流れを説明しますね。かれこれ20年以上前の話なんで、多少今と違う部分もあるかもしれませんが、基本的な流れは変わってないはずです。
申請に必要な書類と流れ – ちょっと面倒だけど、乗り越えよう!
まず、大まかな流れはこんな感じです。
- お住まいの市区町村の福祉担当窓口に相談 まずは役所に行って、「身体障害者手帳の申請をしたいんですけど」と相談するのがスタートです。ここで申請に必要な書類一式をもらえます。親切な担当者さんだと、いろいろ教えてくれますよ。
- 指定医に診断書・意見書を書いてもらう これが一番のキモですね。役所でもらった書類の中に、診断書・意見書の用紙があります。これを、身体障害者福祉法で定められた「指定医」に書いてもらう必要があります。多くの場合、透析治療を受けている病院の先生が指定医になっているはずなので、主治医に相談してみましょう。
- 必要書類を揃えて窓口に提出 診断書・意見書の他に、申請書、写真(規定のサイズがある)、マイナンバーが確認できる書類などが必要です。全部揃ったら、再び役所の窓口に提出します。
- 審査 提出された書類をもとに、審査が行われます。ここで、障害の等級などが決定されます。
- 手帳の交付 審査が無事に通れば、手帳が交付されます。交付までには、だいたい1ヶ月〜2ヶ月くらいかかることが多いみたいです。私の時は、思ったより早かった記憶があるけど、まあ、気長に待ちましょう。
ざっとこんな流れです。ね、ちょっと書類集めとか面倒くさそうでしょ? でも、医療費のこととか考えると、やっぱり頑張って手続きする価値はあると思います。
診断書を書いてもらう時の注意点 – 先生とのコミュニケーションが鍵
申請手続きの中で、やっぱり一番大事なのは、先生に書いてもらう「診断書・意見書」です。これがないと始まりませんからね。
普段からお世話になっている主治医にお願いするのが一般的だと思いますが、いくつか気をつけておきたいことがあります。
- 早めに相談する 先生も忙しいので、診断書を書いてもらうのには時間がかかることがあります。「すぐに書いてください!」って急かすんじゃなくて、余裕を持ってお願いするのが大事です。私は、「先生、障害者手帳の申請を考えているので、診断書をお願いできますか?」って、次の診察の時とかに、事前に話しておくようにしました。
- 何のための診断書か明確に伝える 「身体障害者手帳の申請用です」と、はっきり伝えましょう。診断書って、いろんな種類がありますからね。目的が違うと、書いてもらう内容も変わってしまいます。
- 費用がかかる場合がある 診断書の作成には、文書料として費用がかかるのが普通です。病院によって金額は違うので、事前に確認しておくと安心です。保険適用外なので、数千円くらいかかることが多いです。
- 自分の状態をちゃんと伝える 診断書には、現在の腎臓機能の状態や、透析治療の状況などを書いてもらう必要があります。普段の診察だけじゃ伝わりきれない、日常生活での困りごととかがあれば、この機会に先生に話してみるのもいいかもしれません。等級は客観的なデータで決まる部分が大きいです。
とにかく、先生とのコミュニケーションが大事です。遠慮せずに、でも丁寧に、お願いするようにしましょう。私の主治医は、すごく理解のある先生だったので、スムーズにお願いできましたが、もし話しにくいなと感じる場合は、病院のソーシャルワーカーさんとかに相談してみるのも手です。
審査期間はどれくらい? – 待つ間の心境とか
書類を全部提出したら、あとは審査の結果を待つだけです。先ほども話しがしましたが、だいたい1ヶ月から2ヶ月くらいが目安みたいですね(自治体によっても違うみたいですが・・・)。
この待ってる間、まあ落ち着かない感じです。「ちゃんと通るかな」「等級はどうなるかな」とか、いろいろ考えてしまいます。私の場合、透析導入直後で、体調もまだ不安定だったし、将来への不安も大きかった時期だったので、余計にソワソワしていたのを覚えています。「これで少しでも経済的な負担が軽くなれば…」って、藁にもすがる思い、みたいな感じでした。
「考えても仕方ないですからね。なるようにしかならない」と考えることできますか!?とかく透析治療にしっかり向き合って、体調を整えることに集中するのが一番です。忘れた頃に、役所から「手帳ができましたよ」って連絡が来る、くらいの気持ちでいるのがいいかもしれません。
そして、無事に手帳が交付されたときは、やっぱりホッとしましたよ。これで治療を続けていくための一つの基盤ができた、みたいな。複雑な気持ちがなかったわけじゃないけど、それ以上に安堵感の方が大きかったです。
障害者手帳で受けられる支援 – 知らなきゃ損するかも?
障害者手帳を手にしたら、具体的にどんなサポートが受けられるのか、もう少し詳しく見ていきましょう。これ、本当にいろいろあります。全部を把握するのは大変なくらい。でも、知っておかないと使えないですからね。代表的なものをいくつか紹介します。私が実際に利用して「これは助かる!」と思ったものを中心に。
医療費助成 – これが一番大きい!私の場合…
やっぱり、一番インパクトが大きいのは医療費の助成です。透析治療って、保険適用でも高額になりがち。一般的な血液透析だと、1回あたり数万円、月だと40万円以上かかるなんて言われています。もちろん、高額療養費制度があるので、全額自己負担になるわけじゃないですけど、それでも毎月の負担はかなりのもの。
ここで障害者手帳(腎臓機能障害で1級など)を持っていると、国の「特定疾病療養受療制度」や、お住まいの自治体独自の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度など、名称は様々です)の対象になることが多いんです。
「特定疾病療養受療証」があると、透析治療にかかる医療費の自己負担限度額が、収入に応じて月額1万円か2万円になります。これ、めちゃくちゃ大きいですよね。
さらに、自治体によっては、この自己負担分も助成してくれて、実質的な負担がゼロになったり、もっと少額になったりする場合もあります。私が住んでいる自治体は、幸いこの制度が手厚くて、透析に関する医療費の窓口負担はほとんどありません。これは本当に、本当にありがたいです。
ただし! この医療費助成を受けるには、障害者手帳を持っているだけじゃダメで、別途申請が必要な場合がほとんどです。手帳が交付されたら、すぐに役所の窓口で「透析に関する医療費助成について教えてください」と確認するのが鉄則です。必要な書類とか、手続きの方法とか、ちゃんと聞いておきましょう。自動的に適用されるわけじゃないので、ここは要注意ポイントですよ!
税金の控除・減免 – 意外と見落としがち?
次に税金関係。これも結構助かります。
- 所得税・住民税の障害者控除 納税者本人または扶養親族が障害者の場合、所得から一定額が控除されます。手帳の等級によって控除額が変わります(特別障害者の場合は控除額が大きい)。会社員の場合は年末調整で、自営業などの場合は確定申告で手続きします。忘れずに申告しましょう。
- 相続税の障害者控除 これは、もしもの時の話ですが、相続人が障害者の場合に相続税額から一定額が控除されます。
- 贈与税の非課税 特定の信託契約などを利用した場合、贈与税が非課税になる制度もあります。これはちょっと専門的な話になるので、税理士さんとかに相談するのがいいかも。
- 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免 一定の要件を満たす場合、これらの税金が減免されることがあります。通院などで車が必須な人にとっては、かなり大きいですよね。これも自治体によって要件が違うので、役所の税務課とかに確認が必要です。
税金の話って、なんだか難しくて面倒に感じちゃうんですけど、塵も積もれば山となる、ですからね。使える制度はしっかり活用したいところです。会社員だと、年末調整の時に会社に障害者手帳を持っていることを伝える必要があるので、ちょっと抵抗がある人もいるかもしれませんが…。これも後で触れますね。
公共料金の割引とか – 地味だけど助かる
これは、日々の生活の中で「あ、ちょっと得したかも」って思えるやつですね。
- 公共交通機関の運賃割引 JR、私鉄、バス、タクシーなどで割引が受けられることがあります。割引率や対象範囲(本人だけか、介護者もかなど)は事業者によって様々。長距離移動が多い人ほど恩恵が大きいですね。私は臨時透析などで新幹線をよく使うので、これは本当に助かってます。
- 携帯電話料金の割引 各携帯キャリアが、障害者手帳を持っている人向けの割引プランを用意していることが多いです。基本料金が安くなったりするので、これもチェックしてみる価値ありです。
- 公共施設の入場料割引 美術館、博物館、動物園、公園、映画館などで、本人や介護者が割引料金で利用できることがあります。これらの施設を確認してみましょう。
- NHK受信料の減免 世帯構成などの要件を満たせば、NHKの受信料が全額または半額免除になります。
- 水道料金・下水道料金の減免 自治体によっては、水道料金などが減免される場合があります。これも要確認ですね。
一つ一つは少額かもしれないけど、積み重なると結構な違いになります。手帳を提示する必要があるので、常に持ち歩くのが基本になりますね。
その他のサービス – 地域によって違うから要チェック!
上記以外にも、地域や自治体によって、独自のサービスが提供されていることがあります。
- 福祉タクシー券の交付 通院などに使えるタクシーの利用券がもらえる。
- 自動車運転免許取得費用の助成
- 住宅改造費の助成 手すりの設置など。
- 補装具・日常生活用具の給付・貸与
本当にいろいろあるので、まずは自分の住んでいる市区町村の「障害福祉課」みたいなところに問い合わせて、「透析で身体障害者手帳を持っているんですが、どんなサービスが利用できますか?」と聞いてみるのが一番確実です。もしかしたら、自分が知らなかった便利な制度が見つかるかもしれませんよ。
ぶっちゃけ、これらの制度って、申請しないと使えないものがほとんどなんです。「知らなかったから使えなかった」じゃ、もったいないですからね。情報収集、大事です!
障害者手帳と仕事 – 両立のためのヒント
透析治療を受けながら仕事を続けるって、簡単なことじゃないですよね。週3回の透析に通う時間を確保しなきゃいけないし、体調の波もある。私も会社員なので、この悩みはすごくよく分かります。障害者手帳を持っていることが、仕事の面でどう関わってくるのか、私なりの考えや経験をお話しします。
障害者雇用枠ってどうなの? – 私なりの考え
障害者手帳を持っていると、「障害者雇用枠」での就職や転職が可能になります。これは、企業が法律で定められた割合以上の障害者を雇用する制度ですね。
メリットとしては、
- 障害への配慮が得られやすい 通院時間の確保や、体調に合わせた業務内容の調整など、一般枠に比べて相談しやすい環境であることが多いです。
- 採用のハードルが下がる可能性がある 障害者採用を積極的に行っている企業も多いです。
デメリットというか、考えどころとしては、
- 求人の数が限られる 一般枠に比べると、職種やポジションの選択肢は少ないかもしれません。
- 給与水準が低い場合がある 必ずしもそうとは限りませんが、一般枠より給与が低めに設定されているケースもあるようです。
- キャリアパスが限定される可能性 担当できる業務範囲が限られたり、昇進の機会が少なかったりする可能性もゼロではありません。
私自身は、氷河期世代にあたりとにかく再就職するのが難しくなりました。時期的には2000年代に突入していて、世の中が良い時代を向かうと思いきや良くならず、(その後「失われた20年、30年」と思いもしませんでしたが…)同時期に透析導入となり、転職活動が長丁場となったのです。
逆を言うと、時代は流れ、透析導入される方もいるでしょう。「障害者雇用枠」で採用され、働き続けることもできます。(私は幸い、会社や上司、同僚の理解があって、通院時間の確保(中抜けや時短勤務など)や、体調が悪い時の休憩など、配慮して頂いて今日まで仕事を続けています。転職も経験しましたが・・・。いずれえにしても、本当に恵まれている環境だと思っています。)
「障害者雇用枠」を使うかどうかは、その人の状況や価値観によります。安定して長く働きたい、障害への配慮を確実に得たい、という場合は有力な選択肢になると思います。一方で、キャリアアップを目指したい、一般枠と同じ土俵で勝負したい、という場合は、一般枠で働きながら必要な配慮を求めていく、という道もあります。
もし、これから就職・転職を考えているなら、ハローワークの専門援助部門や、障害者専門の転職エージェントなどに相談してみるのがいいと思います。いろんな情報や選択肢を提供してくれますよ!
会社への伝え方 – カミングアウトのタイミングとか
今、一般枠で働いている人が透析導入になった場合、「会社に伝えるかどうか」「いつ伝えるか」これ、結構悩みますよね。障害者手帳の取得を伝えるかどうかも含めて・・・。
私の知り合い場合は、透析導入が決まった段階で、直属の上司には正直に話したと言います。週3回の通院が必要になること、体調によっては急に休む可能性もあることなど。幸い、上司がすごく理解のある人で、「大変だけど、無理せず続けていこう。サポートできることはするから」と言ってくれて、本当に救われたと言います。
障害者手帳を取得したことも、年末調整の手続きで必要だったので、総務(人事)にも伝えたと言います。また、部署(チーム)の同僚には、どこまで話すか迷ったそうですが、結局のところ、普段一緒に仕事をしているメンバーですから、透析をしていること、通院で中抜けすることなどを話したそうです。隠してコソコソするより、オープンにした方が結果的に働きやすいかな、と思ったそうです。私も同感ですね。長期渡っての治療ですよ!コソコソしている時間こそ、精神的によろしくないですね。(もちろん、これも人それぞれ、職場の雰囲気にもよると思うところは否定できませんが・・・)。
伝えるメリットとしては、
- 必要な配慮を得やすくなる(通院時間の確保、業務負荷の調整など)
- 隠しているストレスから解放される
- 周囲の理解を得られれば、精神的な支えになる
伝えることへの不安としては、
- 偏見を持たれないか
- 仕事内容や評価に影響しないか
- プライベートなことをどこまで話すべきか
があります。
私が思うに、伝えるかどうか、どこまで伝えるかは、最終的には自分で決めるしかないということです。ただ、透析治療を続けながら働くためには、何らかの配慮が必要になることが多いのも事実。全く伝えないでいると、かえって無理が生じて、仕事も治療も続けられなくなってしまう可能性もあります。
もし伝えるなら、タイミングとしては、透析導入が決まった時や、障害者手帳を取得した時が良いかもしれません。伝え方は、まずは信頼できる上司に相談するのが一般的。(ほぼ何でもそうではないでしょうか)。伝える内容としては、病状そのものより、「治療のために週〇回の通院が必要」「体調によってこういう配慮が必要になるかもしれない」といった、仕事への影響と必要な配慮を具体的に伝えるのが良いと思います。
それからその前に考えておきたいのは、「自分が会社に何を求めているか」ですね。ただ知っておいてほしいのか、具体的な配慮(時短勤務、残業免除、通院のための中抜け許可など)を求めているのか。それを明確にしてから相談する方が、話がスムーズに進むと思います。
無理なく働くための工夫 – 透析とのバランス
透析と仕事を両立させるためには、やっぱり自分なりの工夫が必要です。私が20年以上続けてこられた中で、大事だなと感じているのはこんなことです。
- 体調管理を最優先に これが大前提。無理は絶対に禁物です。透析日は特に疲れやすいので、仕事のペースを調整するとか、帰宅後はしっかり休むとか。食事制限や水分制限も、仕事のパフォーマンスに影響するので、ちゃんと守る。睡眠も大事ですね。
- 完璧を目指さない 仕事も家事も、全部完璧にやろうとすると、絶対どこかで無理が出ます。「まあ、今日はこのくらいでいいか」って、自分を許すことも大事。周りに頼れるところは頼る。(←ココは私なりに反省しています。仕事きちんと終わらせて通院に向かう!大事なことですが、肝心の治療時間が短くなったりということ、若い頃は結構ありましたね。)
- コミュニケーションを大切に 職場で理解を得るためには、やっぱり日頃からのコミュニケーションが大事だと思います。自分の状況を正直に話せる範囲で話しておくとか、感謝の気持ちを伝えるとか。
- 自分に合った働き方を見つける 残業の少ない部署に移る、時短勤務を利用する、場合によっては転職や働き方を変える(フリーランスになるとか)という選択肢も考える。透析クリニックの時間を、夜間透析やオーバーナイト透析に変えることで、日中の仕事への影響を減らすという方法もありますね。私は夜間透析を利用しています。(オーバーナイト透析ができる病院ができたという情報は患者さんの話しから聞いたこともあったのですが、条件的に無理でした。)
- 気分転換も忘れずに 透析をしていると、どうしても生活が治療中心になりがち。でも、仕事以外の楽しみとか、リラックスできる時間を持つことも、長く続けていくためにはすごく重要です。私の場合は、治療中は映画を観たりしていますし、週末に軽い運動をしたり、好きな音楽を聴いたりしていますよ。
障害者手帳を持っているからといって、特別なことをする必要はないですが、手帳があることで受けられる配慮(例えば、通院のための休暇制度とか)をうまく活用しながら、自分なりのペースで仕事と付き合っていく、ことは必要です。頑張りすぎない、でも諦めない、そのバランスが大事だと思いますね。
障害者手帳と障害年金 – 合わせて考えたいお金のこと
障害者手帳と並んで、透析患者にとって重要になってくるのが「障害年金」です。これもお金に関わる大事な制度なので、違いをちゃんと理解しておきたいですね。
障害者手帳と障害年金の違い – ごっちゃにしないで!
この二つ、名前が似てるから混同しやすいんですけど、全く別の制度です。
身体障害者手帳は、
- 根拠法: 身体障害者福祉法
- 目的: 様々な福祉サービス(医療費助成、税金の優遇、各種割引など)を受けるための証明書
- 申請先: 市区町村の福祉担当窓口
- 等級: 1級〜6級(腎臓機能障害の場合は主に1級、3級、4級)
一方、障害年金は、
- 根拠法: 国民年金法、厚生年金保険法
- 目的: 病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に、現役世代も含めて受け取れる「年金」
- 申請先: 年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口(初診日に加入していた年金制度による)
- 等級: 障害基礎年金(1級・2級)、障害厚生年金(1級・2級・3級、+障害手当金)
簡単に言うと、障害者手帳は「サービスを受けるための証明書」、障害年金は「生活を支えるためのお金」というイメージです。
透析を導入した場合、多くは障害者手帳の対象になると同時に、障害年金の受給要件(原則として障害等級2級以上に該当)も満たす可能性が高いです。
重要なのは、障害者手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致しないということ。審査する機関も基準も違うからです。手帳が1級だから年金も1級、とは限らないんですね。
そして、障害者手帳を持っていても、障害年金は自動的にもらえるわけではありません。これも別途、自分で申請手続きをする必要があります。
障害年金の申請 – これも結構大変だけど…
障害年金の申請も、障害者手帳と同じくらい、いや、人によってはそれ以上に大変かもしれません。揃える書類が多いし、ちょっと複雑です。
主な流れは、
- 年金事務所などで相談・書類入手 まずは、自分が障害年金の対象になるか、どの年金を申請するのか(基礎?厚生?)などを確認します。初診日(腎臓の病気で初めて病院にかかった日)がいつか、その時にどの年金制度に加入していたか、保険料の納付状況などが重要になります。
- 医師に診断書を作成してもらう 障害年金専用の診断書が必要です。障害者手帳の診断書とは別物なので注意!
- 「病歴・就労状況等申立書」を作成する これが結構大変。発症から現在までの経過、日常生活や仕事への支障などを、自分で詳しく書く必要があります。
- 必要書類を揃えて提出 診断書、申立書の他に、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)、戸籍謄本、住民票、通帳のコピーなど、たくさんの書類が必要です。
- 審査・決定 日本年金機構で審査が行われ、支給・不支給や等級が決定されます。結果が出るまで数ヶ月かかることが多いです。
聞いただけでも「うわっ…」て思いますね!? 特に「初診日の証明」とか「病歴・就労状況等申立書」の作成でつまずく人が多いみたいです。
私も申請したときは、(大学生のときだから)昔の病院に書類を取り寄せたり、自分の病歴を思い出して書いたり、結構苦労しました。正直、「もうやめようかな」って思った瞬間もありました(笑)。
障害年金は、もし受給できれば、生活の大きな支えになります。特に、透析の影響で思うように働けなくなってしまったということもありうる話しであり、本当に重要です。
もし、自分で手続きするのが難しいと感じたら、社会保険労務士(社労士)さんに相談するのも一つの手です。費用はかかりますが、専門家なのでスムーズに進めてくれることが多いです。無料相談をやっている社労士さんもいるので、一度話を聞いてみるのもいいかもしれません。
障害者手帳の申請と障害年金の申請、どっちも大変だけど、透析患者にとっては、自分の生活を守るための大事な手続きです。諦めずに、情報を集めて、必要なら周りの助けも借りながら、チャレンジしてみてほしいなと思います。
不安や疑問はここで解消! -よくある質問(私なりの回答)
ここまで、透析と障害者手帳について、いろいろお話ししてきました。でも、まだ「ここがよく分からない」「こういう時はどうなの?」って思うこともあるかもしれませんね。私が透析仲間と話していて、よく話題になることや、私自身が最初に疑問に思ったことについて、Q&A形式で答えてみたいと思います。あくまで私個人の経験や考えに基づいた回答ですけどね。
手帳を持つことに抵抗がある…
これは、すごくよく聞くあるある話です。「障害者」っていう言葉の響きとか、なんとなく社会から区別(差別)されるような感じとか、ネガティブなイメージを持っちゃう気持ち、よく分かります。
でも、私が20年以上透析と付き合ってきて思うのは、障害者手帳は、決して「レッテル」なんかじゃないってことです。これは、私たちが治療を続けて、少しでも自分らしい生活を送るために、社会が用意してくれた「サポートを受けるための権利証」みたいなものなのです。そう考えるようにしています。
医療費の助成や税金の控除、いろんな割引サービス。これらは、私たちが透析という大きなハンディ、負担を抱えながら生きていく上で、本当に大きな助けになります。手帳を持つことの心理的な抵抗と、それによって得られる具体的なメリットを天秤にかけてみてほしいんです。
それに、手帳を持っているからといって、常にそれを周りに知らせる必要はないんですよ。必要な場面(役所での手続きとか、割引サービスを使う時とか)で提示すれば良いだけです。普段の生活で、わざわざ「私、障害者手帳持ってます」って言う必要はないよ。
もし、どうしても抵抗があるなら、無理にとは言いません。でも、どんなサポートが受けられるのか、一度しっかり調べてみてから判断しても遅くないと思います。意外と、「あ、これなら申請してみようかな」って思えるかもしれません。
更新手続きは必要?
はい、多くの場合、身体障害者手帳には有効期限があって、更新手続きが必要です。腎臓機能障害の場合、一般的には数年ごとに再認定(更新)が必要になることが多いようです。
「えー、またあの面倒な手続きするの?」って思いますよね(笑)。でも、更新の時は、最初の申請ほど大変じゃないことが多いです。多くの場合、再度、指定医に診断書・意見書を書いてもらって、役所に提出するという流れになります。
更新時期が近づくと、自治体からお知らせが来ることが多いですが、念のため、自分の手帳の有効期限はちゃんと確認しておきましょう。期限が切れる前に手続きを始めるのが基本です。うっかり忘れていると、助成やサービスが一時的に受けられなくなっちゃう可能性もあるので注意が必要です。
ただ、透析を導入している場合、腎臓機能が回復することは基本的にないので、再認定で等級が変わったり、手帳が交付されなくなったりする心配は、あまりないと考えていいと思います。まあ、手続きは面倒ですけどね…。これも、治療を続けていくためのプロセスの一部、と思って乗り切りましょう。
もし等級が変わったら?
基本的には、透析導入によって認定された等級(多くは1級や3級)が、その後の更新で大きく変わることは考えにくいです。腎臓の機能が劇的に改善することは、残念ながら通常はありませんからね。
ただ、もし何らかの理由で(例えば、他の障害が加わったとか、診断基準が変わったとか、非常に稀なケースですが)、等級が変更になった場合は、受けられるサービスの内容が変わる可能性があります。
例えば、等級が上がれば(数字が小さくなれば)、より手厚い支援が受けられるようになるかもしれませんし、逆に下がれば(数字が大きくなれば)、一部のサービスが対象外になる可能性もあります。
もし等級変更の通知が来たら、まずは何が変わるのか、役所の窓口でしっかり確認することが大事です。医療費助成や税金の控除額、利用できる割引サービスなどに変更がないか、ちゃんと聞いておきましょう。
まあ、透析患者の場合は、等級が変わる心配より、更新手続きを忘れずにやる、ということの方が現実的な注意点かな、と思います。
最後に – 透析と共に、自分らしく生きるために
透析と障害者手帳について、私の経験や考えをいろいろとお話しさせていただきました。透析導入は、誰にとっても大きな出来事です。不安や戸惑いがあって当然だと思います。私もそうでしたから。
障害者手帳の申請も、正直、ちょっと面倒です。心理的なハードルを感じる人もいるでしょう。でも、この記事を読んで、障害者手帳が、決して特別なものではなく、透析治療を続けながら、少しでも負担を軽くし、自分らしい生活を送るための、一つの有効な「ツール」なんだって感じてもらえたら嬉しいです。
医療費の助成、税金の控除、様々な割引サービス。これらを活用することで、経済的な不安を少しでも和らげることができます。それは、治療に専念したり、仕事や趣味を続けたりするための、大きな力になるはずです。
透析をしていても、できることはたくさんあります。仕事だって、旅行だって、工夫次第で楽しめます。障害者手帳は、その「工夫」を後押ししてくれる制度の一つです。
もちろん、手帳を持つかどうかは、最終的にはご自身の判断です。でも、もし迷っているなら、まずは情報収集から始めてみてください。役所の窓口、病院のソーシャルワーカーさん、そして私のような経験者の話も、何かヒントになるかもしれません。
透析と共に生きていく道は、決して楽なことばかりではありません。でも、使える制度はしっかり使って、周りのサポートも借りながら、少しでも前向きに、そして自分らしく、日々を過ごしていきましょう。私も、まだまだ会社員として働きながら、透析ライフを続けていきます。一緒に頑張りましょう!