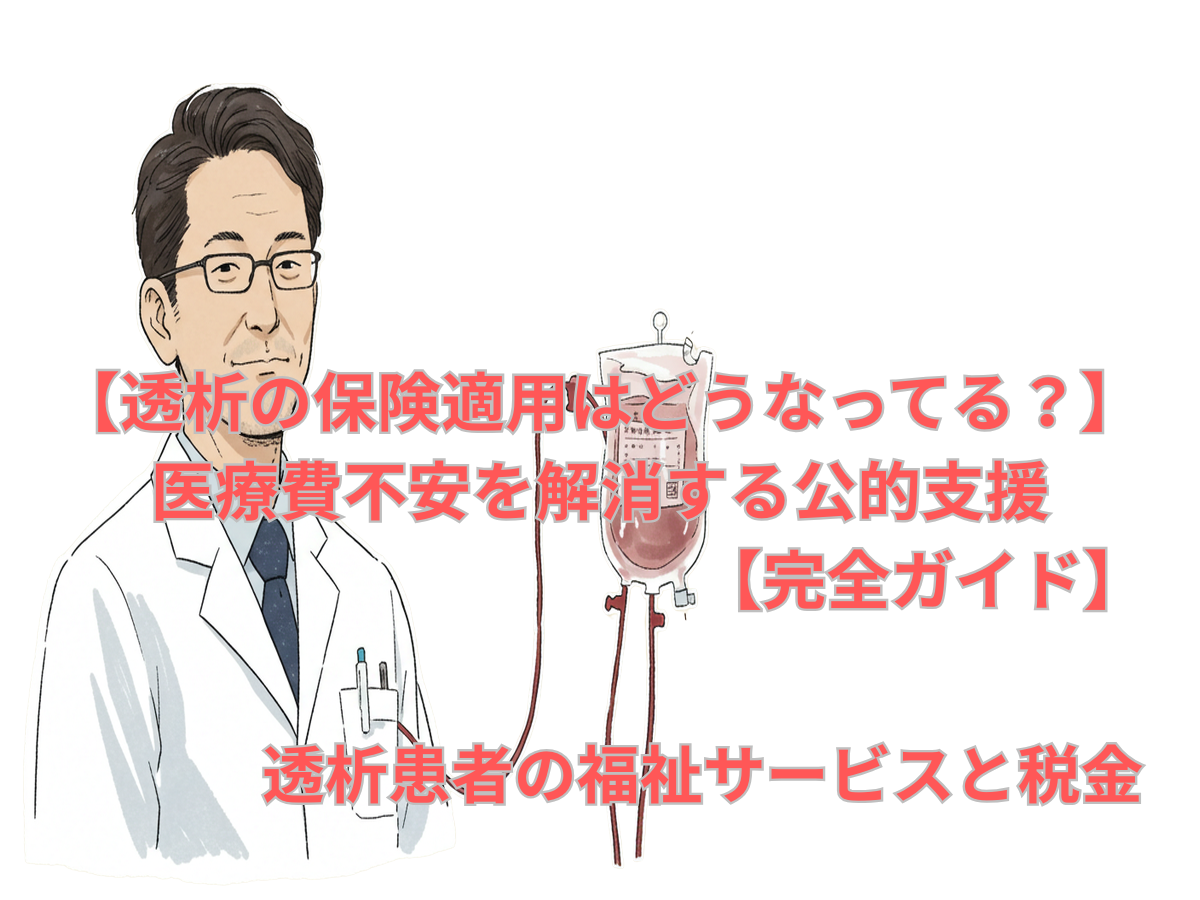
「透析になったら、治療費がとんでもなくかかるんじゃないか…」そんな不安、痛いほどよく分かります。私も透析を始めたばかりの頃は、透析の保険適用について右も左も分からず、お金の心配ばかりしていました。治療はもちろん大事だけど、生活だってありますもんね。
でも安心してください。日本の透析治療には、しっかりとした保険適用や公的な支援制度があるんです。この記事を読めば、透析の医療費に関する不安が軽くなり、「なんだ、意外となんとかなるじゃん!」って思えるはず。私自身の経験も交えながら、分かりやすく解説していきますね。
透析治療にかかる費用、ぶっちゃけどうなってるの?
透析治療って、聞くだけで「高そう…」ってイメージ、ありますよね。確かに、もし全額自己負担だったら、家計は火の車どころか、破産レベルかもしれません。だって、血液透析の場合、1回あたり数万円、それを週に3回、年間で考えると…うーん、考えたくないですね。
でも、そこは日本の医療制度、ちゃんとセーフティネットが用意されているんです。私ら透析患者にとって、これは本当にありがたいこと。具体的にどんな仕組みで医療費負担が軽くなるのか、見ていきましょう。
健康保険がしっかりカバー!自己負担は意外と少ない?
まず基本中の基本ですが、透析治療は保険適用です。皆さんが加入している国民健康保険や、会社員なら会社の健康保険組合(協会けんぽとかですね)が、医療費の大部分を負担してくれます。通常、医療費の自己負担は3割(年齢や所得によって1割や2割の場合もあります)ですが、透析治療の場合はさらに特別な扱いがあるんです。
それが次に説明する「高額療養費制度」と「特定疾病療養受療制度」。この2つの制度のおかげで、実際の自己負担額はもっともっと抑えられるんですよ。だから、「透析=自己破産」なんていう心配は、まずしなくて大丈夫です。
私が透析を始めた20年以上前、当時は書籍も少なく、ネットでの情報も少なくて、本当に「これからどうなっちゃうんだろう」って不安でいっぱいでした。でも、病院のソーシャルワーカーさんや、役所の人に相談する中で、こうした制度があることを知って、どれだけホッとしたか…。皆さんも、分からないことは一人で抱え込まず、どんどん周りに聞いてみてくださいね。
高額療養費制度っていう強い味方があるんです
「高額療養費制度」は透析患者に限らず、多くの人が利用できる制度ですが、特に透析患者にとっては重要な制度です。簡単に言うと、「1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が、一定の上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される」というもの。
この上限額は、年齢や所得によって細かく決められています。例えば、70歳未満で一般的な所得の方なら、月の上限額はだいたい8万円ちょっと(※正確な金額は所得区分によって異なります)。透析治療は毎月コンスタントに医療費がかかるので、この制度は本当に助かります。
ただ、この高額療養費制度、払い戻しを受けるには基本的に申請が必要です。しかも、払い戻されるまでに数ヶ月かかることもある。毎月の支払いが大変…という場合に備えて、「限度額適用認定証」というものを事前に申請しておくと、病院の窓口での支払いが最初から自己負担限度額までで済むようになります。これは絶対に申請しておくべき!私ももちろん、毎年更新しています。
あ、でもその前に説明しておきたいのは、次に紹介する「特定疾病療養受療証」があれば、透析患者の場合、この高額療養費制度の上限額がさらに低くなる、っていうことです。ちょっとややこしいですかね?大丈夫、順番に説明しますから。
透析患者が使える!知らなきゃ損する公的な支援制度
さて、ここからが透析患者にとって特に重要な支援制度の話です。これらの制度をしっかり活用することが、経済的な不安を減らす鍵になります。「こんな制度があったなんて知らなかった!」とならないように、ぜひ覚えていってください。
特定疾病療養受療証、これぞ透析患者の必須アイテム
透析患者にとって、まさに「お守り」とも言えるのが、この「特定疾病療養受療証」です。通称「マル長(まるちょう)」なんて呼ばれたりもしますね。
これは、厚生労働大臣が定める特定の疾病(人工透析が必要な慢性腎不全もこれに含まれます)の患者さんに対して、医療費の自己負担限度額を低く設定してくれる制度です。
具体的にいくらになるかというと、原則として月額1万円(※上位所得者は2万円)なんです!すごくないですか?
さっき説明した高額療養費制度の上限額よりも、さらにグッと負担が軽くなる。これが、透析治療が保険適用であることの、最大のメリットと言っても過言ではないかもしれません。
申請は、加入している健康保険(国民健康保険なら市区町村の窓口、会社の健康保険なら会社の担当部署や健康保険組合)で行います。医師の証明書などが必要になりますが、手続き自体はそれほど難しくありません。透析導入が決まったら、真っ先に手続きすべきものの一つです。
私もこの「マル長」には本当に助けられています。月々の医療費の見通しが立つだけで、精神的な安定感が全然違いますからね。これがない透析生活は、正直考えられません。
身体障害者手帳を持つメリット、実はたくさんあるんです
人工透析を受けていると、多くの場合「身体障害者手帳」の交付対象になります。等級は、透析導入後の経過や状態によって異なりますが、一般的には1級に該当することが多いようです。
「え、障害者手帳なんて、なんか抵抗があるな…」と感じる方もいるかもしれません。私も最初は少し戸惑いがありました。でも、この手帳を持つことには、医療費助成以外にも様々なメリットがあるんです。
例えば、
- 医療費助成: 自治体によっては、手帳を持っていることで、さらに医療費の助成(例えば、マル長の自己負担分を肩代わりしてくれるなど)を受けられる場合があります。これはお住まいの自治体によって制度が大きく異なるので、必ず確認してみてください。
- 税金の控除・減免: 所得税や住民税の障害者控除、自動車税の減免などが受けられます。年末調整や確定申告でしっかり申請しましょう。
- 公共料金の割引: JRや私鉄、バス、タクシーなどの運賃割引、携帯電話料金の割引、NHK受信料の減免など、生活に密着した割引サービスも多いです。
- 公共施設の利用料割引: 美術館や博物館、動物園などの入場料が割引または無料になることも。
結構たくさんあります。
手帳を持つかどうかは個人の自由ですが、受けられるメリットを考えると、申請を検討する価値は十分にあると思います。特に自治体の医療費助成は大きいです。私の住んでいる自治体では、「特定疾病療養受療証」の自己負担分が全額助成されるので、透析治療に関する窓口での支払いは実質ゼロになっています。これは本当にありがたい。
申請は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で行います。診断書などが必要になるので、まずは主治医の先生に相談してみると良いでしょう。
障害年金って、透析患者でももらえるの?
「障害年金」…これも透析患者さんにとって、生活を支える上で非常に重要な制度です。
「年金」というと、高齢になってからもらうもの、というイメージが強いかもしれませんが、障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。
人工透析を受けている場合、多くは障害等級2級に認定され、障害基礎年金(国民年金加入者)や障害厚生年金(厚生年金加入者)の受給対象となる可能性があります。
ただし、これにはいくつかの要件があります。
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中であること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間の保険料が納付されていること。
- 障害状態要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、または透析を開始してから3ヶ月を経過した日)に、法令で定められた障害の状態(透析患者の場合は多くが2級)にあること。
ちょっと要件が複雑ですよね…。特に「初診日」の特定や「保険料納付要件」の確認が、申請の際のハードルになることがあります。
私は会社員ではありますが、「初診日」が大学生のときにあたります。遡って障害基礎年金の対象になります。申請の時の相談先として、病院のソーシャルワーカーさんに聞きましたね。
時代は移り変わり、今は障害年金に詳しい社会保険労務士の方、社会労務士事務所に相談するおともできます。(思い返せば、書類の準備とか、年金事務所とのやり取りとか、自分だけだとかなり大変だったと思います。)やっぱり専門家は頼りになります!
障害年金は、受給できるようになると、経済的な基盤が多少なりとも安定します。治療に専念したり、無理のない範囲で仕事を続けたりする上での、大きな支えになります。もし「自分は対象になるかも?」と思ったら、諦めずに年金事務所や専門家に相談してみることを強くお勧めします。これも、知らなきゃ損、というか、知っておくべき大事な権利ですから。
年金は確かに複雑すぎます。「年金なんて自分には関係ない」って思う人のほうが多いのが現実。でも、これから透析を始める人や透析仲間の先輩、そして病院のソーシャルワーカーさんと「絶対申請した方がいいよ!」って強く勧められましたから!
半信半疑でいろいろと調べてみました。、「え、もらえる可能性があるんだ!」と。私の場合は学生時にきちんと保険料を払っていたかどうか、(また国民年金の学生納付の特例が出た頃でもあったため、多少なりとも納付要件が気がかりでした。)それで、一念発起して申請にこぎつけました。あの時周りからの一言がなかったら…と思うと、ちょっとゾッとしますね。
自治体独自の助成制度も要チェック!
これまで紹介してきたのは、国が主体となっている制度が中心でしたが、皆さんがお住まいの都道府県や市区町村が、独自に設けている助成制度も存在します。
例えば、
- 特定疾病療養受療証の自己負担分(1万円または2万円)の助成
- 身体障害者手帳を持っている人への医療費助成
- 透析のための通院交通費の助成
- 見舞金の支給
など、内容は自治体によって本当に様々です。
「うちの自治体はどうなんだろう?」と思ったら、まずは役所の福祉担当窓口や、健康保険担当窓口に問い合わせてみましょう。自治体のウェブサイトで情報公開されていることも多いです。引っ越しなどをすると制度が変わる可能性もあるので、定期的にチェックする習慣をつけておくと良いかもしれません。
私の住む街では、ありがたいことに通院交通費の一部助成があります。透析って週3回の通院が基本なので、地味に交通費もかさむんですよね。だから、この助成は本当に助かっています。こういう細かいサポートが、透析生活を続ける上でのモチベーションにも繋がったりするんですよ。
医療費控除、忘れずに申請してますか?
透析治療の自己負担額は、様々な制度のおかげでかなり抑えられますが、それでも年間で見るとある程度の出費にはなりますよね。そこで忘れてはいけないのが「医療費控除」です。
これは、1年間に支払った医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合に、確定申告を行うことで、所得税や住民税が還付・軽減される制度です。
通院交通費も対象になるって知ってた?
医療費控除の対象になるのは、病院での治療費や薬代だけではありません。なんと、透析のための通院にかかった交通費も対象になるんです!
ただし、対象になるのは公共交通機関(電車、バス)を利用した場合の運賃です。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、残念ながら対象外(私はふだん車通勤しつつ通院するので対象外です)。タクシー代は、病状などからみて緊急やむを得ない場合に限り対象となる可能性がありますが、基本的には公共交通機関と考えておきましょう。
毎回領収書をもらうのは大変なので、利用した日付、交通機関、区間、運賃を記録したメモなどがあればOKです。エクセルで簡単に記録するのも良いですね。これも積み重なると結構な金額になるので、忘れずに申請したいところです。
確定申告、面倒だけど節税効果は大きい!
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。会社員の方だと、「年末調整で全部済んでるから、確定申告なんてしたことないよ」という人も多いかもしれません。
確かに、確定申告って聞くと、書類をたくさん用意して、税務署に行って…となんだか面倒なイメージがありますよね「うわー、面倒くさいなぁ」って。
今はe-Tax(電子申告)を使えば、自宅のパソコンから比較的簡単に申請できますし、何より節税効果は馬鹿にできません。あとで還付金が振り込まれますから!
医療費の領収書や、さっき話した交通費の記録は、しっかり保管しておきましょう。申告の時期(通常、翌年の2月中旬から3月中旬)が近づいたら、税務署のウェブサイトを見たり、無料相談会などを利用したりして、チャレンジしてみてください。一度やってしまえば、翌年からはだいぶ楽になりますよ。
保険適用でもカバーしきれない費用、どうする?
ここまで、公的な保険や支援制度で透析治療の費用負担がかなり軽くなる、という話をしてきました。でも、「じゃあ、全くお金の心配はいらないの?」というと、実はそうとも言い切れない部分もあります。いくつか注意点を見ておきましょう。
差額ベッド代とか、個室料はちょっと注意が必要
入院が必要になった場合などに発生する可能性があるのが、「差額ベッド代」です。これは、希望して個室や少人数の部屋に入院した場合にかかる、健康保険適用外の費用です。
病院によっては、「大部屋が空いていない」などの理由で差額ベッド代のかかる部屋に入院せざるを得ない場合もありますが、原則として、患者側の希望によらない場合は請求されないことになっています。もし請求された場合は、理由をしっかり確認しましょう。
この差額ベッド代は、高額療養費制度や特定疾病療養受療証の対象にはなりません。全額自己負担になるので、個室などを希望する場合は、費用について事前に確認しておくことが大切です。
先進医療とか、保険適用外の治療を受ける場合
透析治療そのものは保険適用ですが、もし将来的に、保険適用外の新しい治療法(いわゆる「先進医療」など)を受けることを選択した場合、その費用は原則として全額自己負担になります。
もちろん、誰もが先進医療を受けるわけではありませんし、現時点での標準的な透析治療は、保険適用内で十分に行えます。ただ、こういうケースもある、ということは頭の片隅に置いておいても良いかもしれません。
民間の医療保険、入っておくべき?(これは個人の判断だけど…)
「公的な保障だけじゃ不安だから、民間の医療保険にも入っておいた方がいいのかな?」と考える方もいるかもしれません。
これについては、正直、一概には言えません。個人の経済状況や、どこまでリスクに備えたいか、という価値観によって判断は変わってくると思います。
透析患者の場合、残念ながら新規で加入できる医療保険はかなり限られますし、加入できたとしても保険料が割高になったり、特定の条件が付いたりすることが多いです。すでに加入している保険があれば、保障内容を確認してみましょう。
私個人の考えとしては、まずは公的な制度を最大限に活用することを第一に考えるのが良いと思っています。その上で、もし余裕があり、どうしても差額ベッド代や保険適用外の治療費、あるいは収入減への備えが心配、ということであれば、選択肢の一つとして検討する、というスタンスが良いのではないでしょうか。
ただ、保険の営業マンの言うことを鵜呑みにするのではなく、複数の商品を比較検討したり、中立的なファイナンシャルプランナーに相談したりすることをお勧めします。私も一時期、色々検討したんですが、結局「まずは公的制度のフル活用だな」という結論に至りました。これはあくまで私の場合、ですけどね。
【体験談】20年透析してる私が、お金の不安とどう向き合ってきたか
さて、ここまで制度の話を中心に解説してきましたが、最後に、私自身の経験について少しお話しさせてください。透析歴20年超、現役で会社員を続けながら、透析治療を受けている私が、お金の不安とどう向き合ってきたか、というリアルな話です。
最初はやっぱり不安だった…「治療費、払い続けられるかな?」って
40代後半の私ですが、透析導入が決まったのはもっと若い頃でした。仕事もこれから、っていう時期に、「一生、週3回の透析が必要で、それにはお金がかかる」という現実は、正直かなり重かったです。
「透析の保険適用って言っても、結局いくらかかるんだろう?」「仕事を続けられなくなったらどうしよう?」「家族に迷惑をかけたくない…」。そんな不安で、夜も眠れない日がありました。
最初に病院で医療費の説明を受けたときも、高額療養費制度とか、特定疾病療養受療証とか、なんだか難しい言葉ばかりで、正直チンプンカンプンでした。「とにかく手続きしなきゃ!」とは思うものの、体調も万全ではない中で、役所に行ったり書類を集めたりするのは、なかなかしんどかったです。
制度をフル活用!そして「お金の専門家」にも相談してみた
でも、分からないなりに、病院のソーシャルワーカーさんや、役所の窓口の人に何度も質問して、一つずつ制度を理解していきました。特定疾病療養受療証、身体障害者手帳、そして障害年金…。申請できるものは、とにかく全部申請しました。
手続きは、確かに面倒でした。特に障害年金の申請は、初診日の証明とか、病歴の申立とか、かなり骨が折れました。今は、障害年金に詳しい社会保険労務士さん、社会保険労務士事務所もあります。費用はかかりますが、結果的にスムーズに受給が決まるはずです。
確定申告での医療費控除も、最初は面倒でしたが、数年続けるうちに慣れました。今はe-Taxでサクッとやっています。こういう「やれることは全部やる」っていう姿勢が、経済的な不安を少しずつ軽くしてくれたんだと思います。
あと、これは私の個人的な経験ですが、一度ファイナンシャルプランナー(FP)さんに相談したこともあります。透析治療を続けながら、将来のライフプランをどう考えていけばいいか、客観的なアドバイスをもらえたのは大きかったです。お金のプロに相談するっていうのも、一つの手ですよ。
透析とお金、うまく付き合っていくコツみたいなもの
20年以上透析を続けてきて思うのは、お金の不安と向き合う上で大事なのは、
- 使える制度を正確に知ること
- 面倒くさがらずに手続きすること
- 一人で抱え込まず、周りに相談すること
この3つかな、ということです。
特に「知る」ことは本当に大事です。知らないと、使えるはずの制度も使えませんからね。この記事が、皆さんが制度を知るきっかけになれば嬉しいです。
そして、手続きは面倒でも、一度やってしまえば、あとは更新だけ、というものも多いです。最初の一歩を踏み出す勇気が大切だと思います。
最後に、困ったときは遠慮なく周りを頼りましょう。主治医の先生、看護師さん、ソーシャルワーカーさん、役所の担当者、家族、友人、そして私のような透析仲間の経験談…。誰かに話すだけでも、気持ちが楽になることがあります。
透析治療は長丁場です。お金の心配ばかりしていると、精神的にも参ってしまいます。利用できる制度をしっかり活用して、少しでも心穏やかに、前向きに治療と向き合っていけるように、一緒に頑張りましょう!
まとめ:透析の保険適用と支援制度を賢く活用して、前向きな透析ライフを!
今回は、透析の保険適用と、それに伴う医療費負担、そして利用できる様々な公的支援制度について、私自身の経験も交えながらお話ししてきました。
ポイントをまとめると、
- 透析治療は保険適用であり、高額療養費制度や特定疾病療養受療証によって、自己負担額は大幅に軽減される(原則月1万円 or 2万円)。
- 身体障害者手帳を取得すると、自治体独自の医療費助成や税金の控除、公共料金の割引など、多くのメリットがある。
- 要件を満たせば、障害年金を受給できる可能性があり、生活の大きな支えになる。
- お住まいの自治体独自の助成(通院交通費助成など)も要チェック。
- 医療費控除(通院交通費も対象!)を確定申告で行うことで、税金が還付される。
これらの制度をしっかり理解し、活用することで、透析治療にかかる経済的な不安は、かなり軽減できるはずです。
確かに、透析導入は人生の大きな変化ですし、不安を感じるのは当然です。でも、お金の面では、日本には手厚いサポート体制が整っています。どうか、必要以上に心配しすぎず、まずは利用できる制度について情報を集め、手続きを進めてみてください。
私も透析と共に20年超、会社員として働き、家族との時間も大切にしながら、なんとかやってこられました。お金の心配がゼロになったわけではありませんが、制度のおかげで「なんとかなる」と思えています。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、前向きな透析ライフを送るための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。