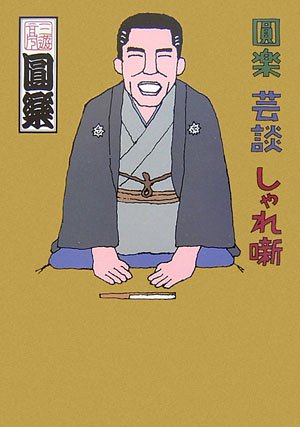80年代のテレビっ子世代として、日曜夕方の『笑点』を見ながら家族で食卓を囲んだ記憶は、今でも鮮明に残っています。その中心にいたのが、5代目三遊亭圓楽師匠。穏やかでユーモアに満ちた語り口は、病気を持つ今の自分にとっても、どこか「寄り添ってくれる」ような安心感を与えてくれます。
この記事では、透析患者である私自身の視点から、同じく人工透析を受けながら生涯を噺家として生き抜いた圓楽師匠の生き様をたどっていきます。
ただの追憶ではなく、「透析生活の中でも自分らしく生きる」ことのヒントを、圓楽師匠の姿を通じて見つけたいと思っています。あの時代を共に生きた感覚と、病と向き合うリアルな生活が交差することで、この記事が誰かの背中を少しでも押せるよう願っています。
圓楽師匠が人工透析に至った道のりと、私の思い出
幼少期からの慢性腎炎との闘い
5代目三遊亭圓楽師匠が人工透析を導入したのは1998年、66歳のとき。彼は幼少期から慢性腎炎を抱えており、長い年月をかけて徐々に腎機能が低下していったとされています。私が透析生活に入るようになってから初めて知ったのですが、こうした長期にわたる「静かな進行」は、腎疾患では決して珍しくありません。
実際、私が腎臓に異常があると診断されたのは、大学生のときの健康診断でした。それまで自覚症状はほとんどなく、病気という意識も持っていませんでした。でも、まさか自分が「将来透析をすることになる」なんて、その時は想像すらしていませんでした。私が透析を始めたのは28歳のとき。そこに至るまで、実に6年近く、食事療法や薬での管理、通院を続けてきました。
不思議な縁のようにも思えるのですが、小学校の高学年のとき、同じクラスに転校してきたY君という少年がいました。彼はネフローゼ症候群を患っており、私とはよく一緒に帰ったり、入院中にはお見舞いに行ったりした記憶があります。当時は「病気で休むことが多い子」くらいの認識でしたが、今になってみると、彼の抱えていた不安や痛みが痛いほどわかります。
圓楽師匠も、きっとそうやって長い時間をかけて、病気と「共に生きる」道を選んできたのだと思います。突然病気になる人もいれば、ゆっくりと近づいてくる病に気づかずに過ごす人もいる。そのどちらにしても、心の準備ができている人なんていないのです。私もそうでした。
66歳で透析導入…師匠の選択
66歳という年齢で人工透析を導入するというのは、当時としてはかなりの決断だったと思います。透析を始めるには、シャントを作る手術が必要で、それ以外にも生活の大きな見直しを迫られます。圓楽師匠ほどの多忙な人が、透析を受けながら活動を続けるというのは、並大抵のことではありません。
私も透析導入前、いろいろな不安を抱えました。「これから先、普通の生活ができるのか?」「仕事はどうなる?」「外出や旅行は?」そんな疑問や不安が頭の中を渦巻いていました。でも、師匠は違いました。透析を受けながらも高座に立ち、弟子を育て、芸を守り続けたのです。
この事実に初めて触れたとき、「透析=終わり」ではないんだという強いメッセージを受け取った気がしました。私が透析を受けながらも仕事や趣味、社会との関わりを続けていこうと思えたのは、間違いなく圓楽師匠の影響があります。
66歳での決断は、きっと彼にとっても不安だったと思います。でも、「噺家として生きる」ことを何よりも大事にしていたからこそ、病気との共存を選んだのではないでしょうか。
小学生の友人Y君とネフローゼ症候群
小学生のときに一緒のクラスだったY君は、今思えば、私の「腎臓の記憶」の原点かもしれません。当時は「ネフローゼって何?」という状態でしたが、彼がたびたび学校を休んだり、顔がむくんでいたことを思い出します。
子どもながらに「大変そうだな」と感じていたけど、まさか数十年後、自分も腎臓病と向き合うことになるとは思いませんでした。病気の種類は違えど、「腎臓に持病を持つ」という点で、あの時のY君の気持ちが今ならよくわかります。
私はその後、大学生の頃に腎機能低下を指摘され、生活が一変しました。制限の多い食事、毎日の薬、定期的な通院…最初は「自分だけが不幸なんじゃないか」と思ったこともあります。でも、あの時のY君を思い出すと、少し気が楽になることもありました。子ども時代に出会った彼は、私にとって、病気と向き合う覚悟の原点のような存在です。
意識が遠のく体験と緊急オペの記憶
透析をしていると、どうしても避けられないのが「低血圧」です。圓楽師匠も、透析時の血圧が上は80mmHgと非常に低かったという記録があります。これ、透析患者にとっては本当に怖い数値です。私も経験がありますが、透析中はもちろん、透析後にふとしたことで意識が遠のくこともあります。
実際、私は自宅で血圧が急激に下がり、その影響でシャントが閉塞してしまったことがあります。慌てて病院に駆け込み、緊急手術。シャントがなければ透析そのものができないので、命に関わる事態です。あのときの冷や汗と手の震えは今でも忘れられません。
でも、そういう経験を重ねていくうちに、少しずつ「自分なりのコントロール方法」も身につけていけるようになります。水分制限や体重管理、透析前後の過ごし方…。自分の体と対話することが、生活の一部になってくるのです。圓楽師匠もまた、そうやって自分の身体と折り合いをつけながら、芸を続けていったのだと思います。
病を抱えながらも高座に立ち続けた理由
圓楽師匠は、病を抱えながらも芸を捨てることはありませんでした。それどころか、透析を受けながらも弟子を育て、自らも高座に立ち続けました。この姿勢には、本当に頭が下がります。
私も「自分に何ができるか」を、ベッドの上で何度も考えました。ノートPCを持ち込んでブログを書いたり、タブレットで映画を観たり。最初は暇つぶしのつもりでしたが、だんだん「この時間をどう使うか」が、透析生活を前向きにするヒントになっていきました。
圓楽師匠のように、大きな舞台で活躍することはできませんが、自分なりの「表現」はできる。透析という制限があるからこそ、見えてくる世界がある。そう思えるようになったのは、師匠の生き様に背中を押してもらったからです。
芸と病の両立──ベッドの上でも「生きる」を続ける
週3回の透析と師匠の芸の継承
透析患者にとって週3回、1回あたり4〜5時間もの時間を病院で過ごすというのは、体力的にも精神的にも非常に大きな負担です。実際、私も月曜・水曜・金曜は夜間透析。仕事を早退してきて、夕方には必ず透析に時間を取られており、そこを起点に日常のスケジュールを組んでいます。外出や会食の予定も、まず透析ありきで考える必要があります。
そんな中で圓楽師匠は、透析を受けながらも、弟子である三遊亭王楽に対して10席もの演目を指導し、録音テープまで残しています。この話を初めて聞いたとき、私は大きな衝撃を受けました。透析中は体もつらく、何かに集中するのも大変なこと。ましてや、人に教えるほどの精神的エネルギーがどれだけ必要か…私には想像を絶するものがありました。
私の場合、透析中に資格勉強などもしましたが、仕事を終えてかつ車で通院してですから、意識を集中させるのも一苦労です。でも、いまでも思いますが「何か目的を持って時間を過ごす」ことが、メンタルの支えなんだと。
師匠が録音を残したように、私もブログやSNSを通じて、自分の考えや体験を発信しています。それは「誰かの役に立ちたい」だとか「元気!現状報告」という気持ちもありますが、なにより「自分自身が前を向く」ための行動でもあるのです。
芸の継承という形は違えど、私もまた、透析という時間の中で、自分らしく生きる術(すべ)を探し続けています。
録音テープに刻んだ「教え」
三遊亭王楽師匠が持つ10席分の録音テープは、圓楽師匠が病と闘いながら残した「生きた教科書」だと言われています。録音には演目の細かな間や口調、感情の込め方までもが刻まれており、まさに「芸のDNA」と言えるものです。
私はそのエピソードに、すごく心を動かされました。患者さんならわかるでしょうが、透析中って、ほんとうに気力が削られるものなんです。針を刺され、血が循環する音に包まれながら、身体はどんどん水分と老廃物を失っていく・・・。気分も体力も底辺に近づいていくなかで、「誰かのために何かを残す」という選択をした師匠の姿には、ただただ尊敬の念を抱きます。
私自身、透析中はノートPCやタブレットを活用して、アイデアを書き溜めたりをしつつ、ブログを作成したりなどを続けていますよ!師匠ほどの技術はなくても、「何かを残す」という思いには、共感します。
録音という形は時代を越えて価値を持つものです。師匠が遺したテープが、今も弟子たちの学びとなり、落語の世界を支えている。「透析中でも自分が社会の一部である」ことを再確認させてくれる、希望の光のように思います。
ノートPCと映画で過ごす私の透析時間
私は透析中、ノートPCを持ち込んでブログを書いたり、タブレットで映画を観たりしています!
昭和の名画『男はつらいよ』シリーズなんかは、懐かしさもあって気持ちが落ち着きます( ´艸`)。昭和80年代を小学生を生きた自分には、あの人情味と寅さんの軽快な言葉が、まるで心をマッサージしてくれるような感覚になるんですよね。
まあ、透析のベッドの上では自由がききません。姿勢も制限され、片腕は動かせない。でも、「動けないからこそ、できることがある」と気づいたのは、透析導入して透析生活に慣れてきてからでした。確かにTVを見たり、携帯ラジオを聴くのもよいけれど。目先にあるのはとにかく、転職活動!仕事に就く、そのためには資格取得しておかないと。(当時は中古ノートPCや携帯DVDプレイヤー、MP3プレイヤーを持参!!)
年齢を重ね、年月が経った今となっては、ブログ執筆、資料の読み込み、音楽を聞く、YouTubeで落語を見てます。やろうと思えばいくらでも「今できること」があるんです。
圓楽師匠も、透析中でも芸を育み、人を育てていました。それに比べたら、私が映画観るくらいで「頑張ってる」とは言えませんが(笑)、それでも「日常の質」を保つという意味では、立派な過ごし方だと思っています。
透析は時間の拘束ではありますが、見方を変えれば「集中できる自分だけの時間」でもあるんです。
脳梗塞からの高座復帰に心打たれて
圓楽師匠は2005年、透析中に脳梗塞を発症しました。しかしその後、懸命なリハビリを経て、高座に復帰します。このエピソードを知ったとき、私は心の底から震えました。
私は幸い、脳梗塞などの大きな合併症は経験していませんが(年齢も重ねていますから、この先は注意で!)、それでも透析後の倦怠感や頭痛に悩まされることは多々あります。そんな体調の中でも、「再び高座に立つ」と決めた師匠の意志は、まさに信念の塊です。
私も日々、体調の波に振り回されながら仕事を続けています。特に冬場は体温調節が難しく、通勤だけでも一仕事。そうした中で、生活を「止めない」ことの大切さを強く感じます。
病気があるから何もできないのではなく、病気があっても「できることを続ける」。師匠の高座復帰は、私にとって「もう一歩、頑張ってみよう」と思える背中の押しでした。人の姿勢が、こんなにも力になるのかと感じさせてくれました。
「死ぬまで噺家」の姿勢に私が学んだこと
圓楽師匠は晩年、「死ぬまで噺家でいたい」と語っていたそうです。この言葉には、本当に深い意味が込められていると私は思います。「噺家」という職業は、ただ芸を披露するだけではなく、「生き方そのもの」なんだと。
私にとって透析生活は、「終わり」ではなく「新しいステージ」です。透析生活での”制限”は増えました。でも、だからこそ工夫するようになり、物事の本質を考えるようになりました。「自分は何がしたいのか」「どう生きていきたいのか」を考えるようになったのです。
圓楽師匠が透析を受けながらも、噺家としての自分を貫いたように、私も「透析患者である前に、自分でありたい」と思っています。透析をしているという事実は消えないけど、それに人生を支配される必要はありません。
「どうせ透析だし」とあきらめていたら、きっと今の私はいなかったでしょう。師匠の姿勢から学んだのは、「生きるとは、選び続けること」。それが私の中で、今も強く息づいています。
腎移植を選ばず「透析で生きる」と決めた理由
師匠が腎移植をしなかった事実
5代目三遊亭圓楽師匠は一度も腎移植を受けることなく、血液透析を続けていたとされています。私は「あえて移植を選ばなかっただろうなあ」と感じました。もちろん、高齢であることや低血圧、脳梗塞の発症・治療といった背景・諸事情はありました。
腎移植は、腎不全に対する一つの治療選択肢であることは間違いありませんが、決して万人向けではないのです。私も、28歳で透析導入する前に「移植を考えたことはありますか?」と医師から尋ねられた経験があります。
でも、「一応、あります」とは答えたのですが・・・。
私自身と両親とのドナーの話
移植を考える上で避けられないのが「ドナー」の問題です。私にも、両親が「もし自分たちの腎臓で助けられるなら…」と申し出てくれたことがありました。その気持ちは本当にありがたかったでも。でも、私は断りました。
「親の腎臓をもらってまで自分が生き延びたいか?」──そう問われたとき、どうしても「はい」と言えなかったんですね。自分のために親の身体を削ることへの申し訳なさ、リスクに対する不安、そして「その先が本当に幸せになるのか」という答えの出ない問い…。
だから私は、「透析で生きる」という道を選びました。圓楽師匠も、きっとそういう思いを抱えていたのではないでしょうか。移植の技術が確立されているとはいえ、年齢や合併症の有無、生活への影響を考えると、透析という確実な方法を選ぶ理由は十分あるのです。
日本社会の腎移植の現実
日本では欧米に比べて腎移植の実施件数が少なく、生体腎移植に依存している現状があります。ドナー探しのハードルは高く、臓器移植法の問題や倫理的な課題も多く、透析患者にとって「現実的な選択肢ではない」と感じることも多いのです。
さらに、移植後も免疫抑制剤を一生飲み続ける必要があり、その副作用や感染リスクも軽視できません。透析よりも自由が効くと言われても、それは「何もかもが元通りになる」というわけではないのです。
私自身、「自由な生活が取り戻せるなら…」という気持ちはありましたが、情報を集めれば集めるほど、リスクや不安も増えていきました。私にとっては、定期的に透析を受けながら生活を安定させる方が、今の暮らしには合っていたのです。
治療スケジュールと芸の両立という現実的選択
圓楽師匠が透析を選び続けた背景には、「予定を立てやすい治療法」という面があったのではないかと思うのです。透析は決まった時間に通院し、一定のルーティンの中で体調を管理できます。逆に、移植後は体調が安定するまで不確定な要素が多く、師匠のような多忙な芸能生活との両立は難しかったかもしれません。
私も、夜間透析という決まったスケジュールがあるからこそ、その合間に自分の仕事や趣味、交友関係をコントロールできています。透析前後は体力の波があるものの、「自分の中でのリズム」ができることは、むしろ生活の柱になります。
「病気に振り回される」のではなく、「病気と並走する」。圓楽師匠が選んだのも、きっとそういう生き方だったのだと思います。
「病に主導権を渡さない」人生の哲学
透析生活に慣れてくると、「この治療に自分の人生が支配されているのでは?」という思いがよぎる瞬間があります。私も初めの頃は、透析の日を軸にすべてを決めることに、無力感や怒りを覚えた時期がありました。
でも、そんな時に圓楽師匠の生き方を知り、「病気に主導権を渡さない」ことの大切さに気づいたのです。自分の体を理解し、自分で時間をデザインする。その一つひとつが、自分らしい人生を守る手段になるのだと。
師匠は芸を続け、弟子を育て、自分のスケジュールで生きていました。決して病に引きずられることなく、あくまで「自分がどう生きたいか」を第一にしていた。これは、透析患者としてだけでなく、一人の人間としても大切な教訓だと思っています。
圓楽師匠の偉業と落語家としての深み
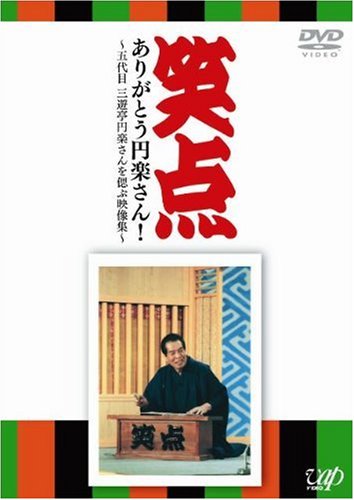
笑点 ありがとう円楽さん! ~五代目 三遊亭円楽さんを偲ぶ映像集~ [DVD]
笑点での笑顔と国民的存在感
5代目三遊亭圓楽師匠と聞いて、真っ先に思い浮かぶのが『笑点』です。あの紺の着物姿、穏やかな微笑み、軽妙な進行。1966年から約40年にわたって番組を支え続けたその姿は、まさに昭和から平成を駆け抜けたテレビの象徴でした。
私自身、日曜の夕方に家族で『笑点』を見るのが習慣でした。中学生のころ、部活帰りに帰宅してテレビをつけると、ちょうど圓楽師匠の声が流れてくる。あの雰囲気には、どこか“家族の安心感”のようなものがありました。
「人を笑わせる」ことの裏にあるのは、深い観察力と、優しさと、リズム感。圓楽師匠の司会は、ただ出演者を回すだけでなく、一人ひとりの個性を最大限に引き出すような懐の深さがありました。これって、実はとても高度な技術なんですよね。
透析生活に入った今、改めて『笑点』を見返すと、当時は気づかなかった師匠の絶妙な“間”や“空気の読み方”に気づくことが多くなりました。あれだけ自然体で笑いを届け続けた人が、実は裏で病気と闘いながら毎週テレビに出ていたなんて…。その事実を知った今では、彼の笑顔がより深く、尊く感じられます。
真打昇進から文化庁芸術祭賞まで
5代目三遊亭圓楽師匠が真打に昇進したのは、1955年に入門してからわずか7年後の1962年。これは当時としては異例のスピード出世でした。そこには、彼の非凡な語りの技術と、芸に対する真摯な姿勢があったのでしょう。
特に私が注目したいのは、1988年に師匠が受賞した「文化庁芸術祭賞」です。この賞は、年間を通じて最も優れた舞台芸術に贈られるもので、落語界では非常に名誉あるものです。つまり、彼はテレビの顔である一方で、伝統芸能の担い手としても本物だったということ。
病と共に歩むようになっても、圓楽師匠の芸が評価され続けた背景には、“本物”の落語家としての信念があったと思います。実力のある人はたくさんいますが、信念を持ち続ける人はそう多くありません。
私も透析を受けながら働く一人として、どんな状態でも「誇りをもって取り組む」ことの大切さを痛感します。評価されることよりも、自分の中で納得できるかどうか。圓楽師匠の受賞歴は、そんな生き方のひとつの答えだと感じています。
印象深い名演目とその背景
圓楽師匠には数々の名演目がありますが、個人的に思い入れがあるのは『芝浜』『中村仲蔵』『文七元結』『浜野矩随』といった、どれも人情味あふれる古典落語です。
特に『芝浜』は、彼が病を抱えながらも再び高座に立った2007年の「国立名人会」で披露されたもので、その演技に多くの人が涙したといいます。生活に疲れた魚屋が、妻の愛によって人間として立ち直っていく物語。これ、病気で一度自信を失いかけた私にとっても、本当に響く話でした。
『浜野矩随』は職人の誇りを描いた作品。これも、透析という制限の中でも自分の仕事に誇りを持ちたいと思っている私にとっては、まさに「今の自分に必要な物語」でした。
落語というのは、ただ笑わせるだけではなく、こうやって心に寄り添ってくれる芸なんですよね。圓楽師匠の演目は、どれも“聴いたあとに残る余韻”がある。その余韻が、私にとっては希望だったり、反省だったり、また歩き出す勇気だったりするのです。
「寄り添う芸」がもたらす癒やし
私は透析中に落語を聴くことがあるのですよ。どうしても音楽番組やニュース寄りになってしまうのですが、落語のリズムって心地よくて、疲れているときでもすっと頭に入ってくるんです。圓楽師匠の語りには“寄り添ってくれる”ような優しさがありますね。
『文七元結』。これは、お金に困って娘を吉原に売ろうとする父親が、ある出会いによって救われるという話。社会の底辺であえぐ人間に向けたまなざしが、圓楽師匠の語りからは強く感じられます。病気で弱っているとき、こういう話が心にしみるんですよね。「頑張れよ、まだ終わってないぞ」って、言われている気がして。
落語って本当に不思議で、登場人物の人生に重ねながら、自分自身を見つめ直せる時間になります。透析で横になっているとき、耳だけが自由な感覚ってあるんです。そんなときに聴く圓楽師匠の声は、まるで友だちみたいにそっと寄り添ってくれます。
芸が癒しになるって、こういうことなんだなと実感しています。
病を越えて伝わる優しさと品格
圓楽師匠には、語りの中に“品格”がありました。それは言葉づかいだったり、ちょっとした間の取り方だったり、見た目にも表れる立ち振る舞いだったり。病気を抱えていることを感じさせない、むしろ“生き様の中で培われた深み”があったのです。
透析生活に入ってから、私は「どうしても生活が荒れがちだな」と思う瞬間が増えました。体がだるい、食べたいものが食べられない、予定通りに動けない…。でも、圓楽師匠の落語を聴くと、ふと我に返るんです。
「ちゃんとした言葉で、ちゃんと人と向き合おう」とか、「日々の所作を丁寧にしよう」とか、小さなことだけど、心を整えるスイッチになる。師匠の落語には、そんな“自分を見つめ直す鏡”のような効果がありました。
病があるからといって、人としての優しさや品格まで失ってはいけない。それを思い出させてくれたのが、圓楽師匠の語り口でした。
芸と生き様に触れるおすすめ作品と体験
師匠の芸談が詰まった書籍
落語は「耳で聴くもの」という印象が強いかもしれませんが、書籍を通して触れることで、より深く噺家の人生や芸に迫ることができます。圓楽師匠の魅力が詰まった一冊としておすすめしたいのが、『圓楽芸談 しゃれ噺』(百夜書房)です。
私はこの本を透析室に持ち込んで、何度も繰り返し読みました。透析中って、思考がぼんやりしたり、逆に時間が止まったように感じたりする瞬間があります。そんなときに、言葉のリズムが心地よい文章に触れると、時間が“流れている”と実感できるんです。
この書籍では、師匠の修行時代の話、芸に対するこだわり、弟子に伝えた言葉の数々などが綴られており、読むたびに新たな発見があります。「落語は人間の業を笑いに変える芸」だという師匠の信念には、私も多くを学びました。
「芸談」としても優れていますが、人生をどう生きるかという問いに対して、ヒントが詰まっている本でもあります。病と付き合いながらも「どう在りたいか」と悩んでいる方に、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
映像作品で追う圓楽の魅力
圓楽師匠の芸も含め視覚的に味わいたいなら、『笑点 宴 -放送50周年完全保存版- DVD-BOX』(日本テレビ)や、当時の舞台公演を収録したDVDがおすすめです。
映像で見る師匠の魅力は、「語りの巧さ」だけではありません。所作、表情、間の取り方――どれも一流の芸を感じさせるものばかり。とくに、観客との“空気のキャッチボール”のようなやりとりには、落語の枠を超えたエンターテイナーとしての力を感じられると思います。
透析を受けていると、身体は疲れていても頭は冴えていることが多く、「見ること」「聞くこと」によって気分転換が図れることが多々あります。テレビや映画も悪くありませんが、落語のように“人間の機微”が感じられるコンテンツに触れることで、心が安らぐことってあります。
映像作品では、師匠の温かな笑顔や観客を包み込むような語りをそのまま体感できますよ!
追悼特番で知る素顔
2009年に師匠が亡くなったあと、いくつかのテレビ局で追悼特番が放送されました。その中には、圓楽師匠の素顔や裏側、弟子たちとのやり取り、テレビでは見られない表情が詰まっていて、非常に印象的でした。
私は録画しておきましたが、透析の無い日に見ましたよ。何度見ても飽きないのは、そこに映っているのが“病を抱えながらも人生をまっとうしようとするひとりの男”だからです(「自分もそのような一人の人間なのだ!」)
人前では常に笑顔で、飄々とした語り口。でも、舞台裏では努力と工夫の連続。そのギャップに触れるたび、私自身も「よし、もう少し頑張ろうか」と思えるのです。透析を続けるというのは、地味で孤独な道です。だからこそ、こうした映像で“生き様”に触れることが、何よりの励ましになるのです。
映像の中の圓楽師匠は、いつも私の少し前を歩いているように感じます。道に迷いそうなとき、その背中を見て「こう生きるんだよ」と言われているような気がします。
弟子に残した「10席」の録音テープの意義
師匠が晩年、三遊亭王楽師匠に向けて遺した「10席の録音テープ」は、単なる記録ではなく、“未来への贈り物”です。病と闘いながらも芸を後世に残そうとする姿勢は、まさにプロの矜持そのもの。
私がこのエピソードを知ったとき、思わずノートを取り出して自分の想いを書きました。「自分も、何かを残せる存在でありたい」と。その内容はブログにまとめ、同じ透析患者や読者の方々から多くの反響をいただきました。
透析中に何ができるか。それは人それぞれですが、「今の自分にできること」を見つけることが何よりも大切だと思います。師匠は録音という形で「自分の声」を残しました。私は文章で「今の気持ち」を残しています。
録音テープに込められた10の演目は、ただの芸ではなく、命の一部です。あの記録がなければ、伝えられなかった技、伝えられなかった情が、きっとあるはずです。芸を遺すという行為は、記憶を遺すこと。透析中の私にも、それができるのだと勇気をもらえました。
透析中の耳からの癒やし──落語がくれる希望
透析は基本的に長時間にわたってベッドで過ごすため、どうしても退屈さとの戦いになります。最初のころは、病院の天井を見つめながら「早く終われ」と願うだけの時間でした。でも、あるときから“耳”を使って何かできないかと思い、落語を聴くようになりました。
最初に聴いたのは『芝浜』。圓楽師匠の語り口は、実に滑らかで、自然に情景が頭に浮かびました。おかげで、ただの治療時間だった透析が「自分だけの物語時間」に変わったのです。
今では『文七元結』『浜野矩随』など、師匠の演目をローテーションしながら、落語の世界を”旅”しています。透析中の不安や孤独も、落語の語りが“間”で包んでくれるような、そんな安心感があります。
落語には、ただ笑わせるだけではない、人の生き様や弱さを肯定してくれる力があります。それが、透析中の私の心にそっと寄り添ってくれる。耳から入る芸の力は、想像以上に深く、あたたかいのです。
まとめ:病と共に、自分らしく生きるということ
5代目三遊亭圓楽師匠の人生は、病気によって狭められたものではありませんでした。むしろ、透析という制約の中でも自分らしさを貫き、芸を磨き続けたその姿勢に、私は何度も勇気をもらいました。
透析生活に入ってからは、不安や孤独と戦う日々でもありましたが、圓楽師匠の生き様に触れることで、「自分の人生にも意味がある」と信じられるようになったのです。
私たちは、病気である前に、一人の人間です。5代目三遊亭圓楽のように、「何をやるか」より「どう生きるか」を大切にしたい。制限の中でも工夫し、時間を大事に使い、人と繋がり、自分の思いや考えを発信していくこと。それが、透析生活を豊かにする鍵だと、私は思います。
病を悲観せず、人生を諦めず、自分らしく前に進む。圓楽師匠の落語と生き方は、まさにそんな私たちにとっての“道しるべ”なのです。