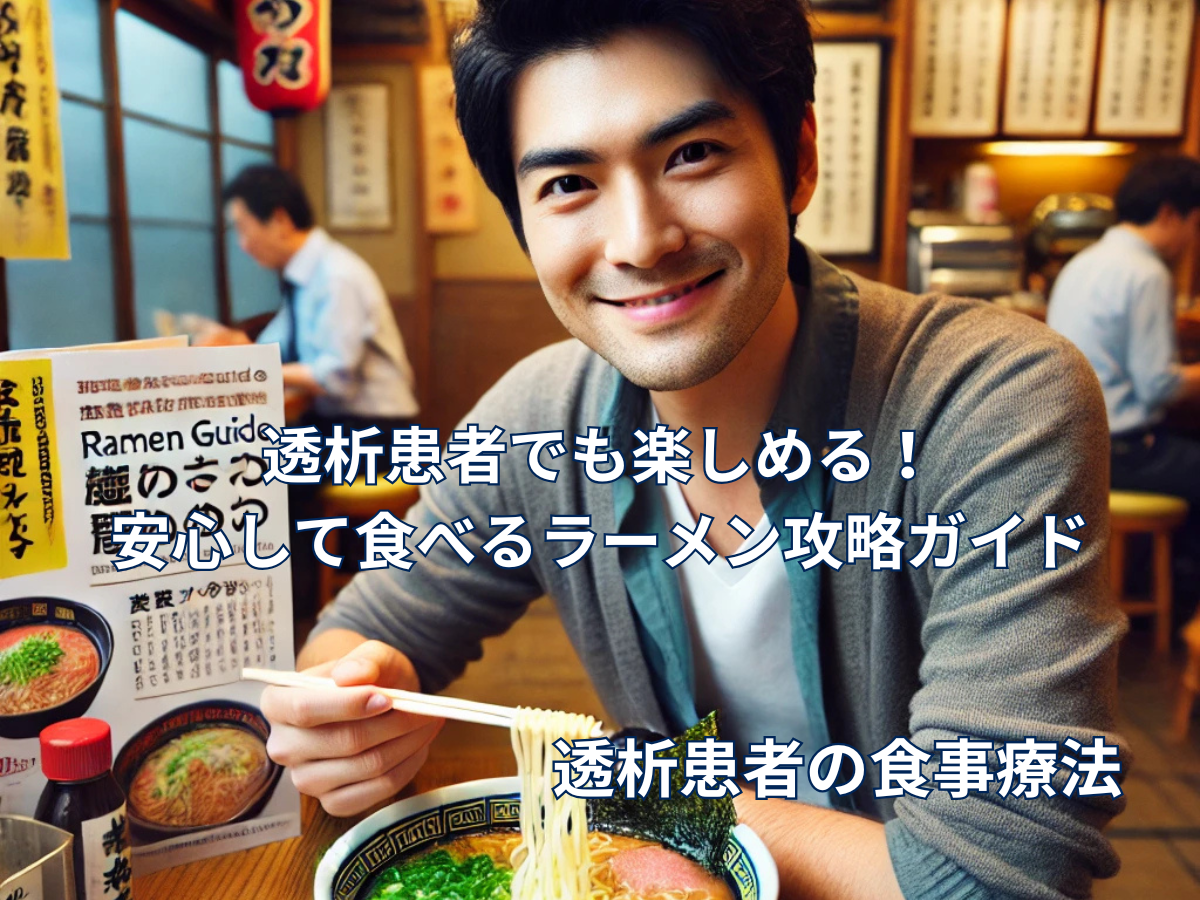
「透析患者はラーメンなんて絶対ダメ」と思い込んでいませんか?
たしかに、塩分やリン、カリウムのリスクはあります。でも、実は少しの工夫とルールさえ守れば、透析患者でもラーメンを安全に楽しむことができるんです!
この記事では、透析歴20年以上の筆者が、実際にラーメンを楽しんでいる経験をもとに「安心・安全にラーメンを食べる方法」を具体的に解説します。「たまのご褒美ラーメン」で、透析ライフに楽しみを取り戻しませんか?
透析患者がラーメンを楽しむための基本ルール
透析患者にとってラーメンは本当にダメなのか?
「透析患者はラーメン禁止」とよく言われます。でも実際は「絶対ダメ」というわけではありません。ポイントは「量」と「頻度」、そして「選び方」です。透析患者は腎臓が機能していないため、塩分や水分、カリウム、リンの管理がとても重要になります。ラーメンはスープに塩分が多く含まれ、麺や具材にもカリウムやリンが含まれがちですが、適切な対策をすれば、たまに楽しむことは可能です。
私自身、週に1回の「ご褒美ラーメン」を楽しみに生活しています。ただし「食べ方」と「その後のケア」がカギです。ラーメンを「一切禁止」としてしまうと、食事が味気なくなり、ストレスが溜まってしまいます。医師とも相談しつつ、自分に合った「ルール作り」をすることで、ラーメンも安心して食べられるようになります。
なぜラーメンは制限されるのか?塩分・カリウム・リンの影響
ラーメンを控えるべき理由は、大きく分けて「塩分」「カリウム」「リン」の3つです。
ラーメンの種類別 栄養成分の目安(1食あたり)
| ラーメンの種類 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) |
|---|---|---|---|
| 醤油ラーメン | 4.5〜8.5 | 300〜600 | 250〜400 |
| 味噌ラーメン | 5.0〜9.0 | 400〜700 | 300〜500 |
| とんこつラーメン | 5.0〜8.5 | 350〜650 | 350〜550 |
| 味噌とんこつ | 5.5〜9.5 | 450〜800 | 350〜600 |
| 塩ラーメン | 5.5〜7.5 | 300〜550 | 250〜400 |
| つけ麺 | 7.0〜10.0 | 400〜700 | 300〜500 |
-
塩分
ラーメン1杯にはスープに約6〜8gもの塩分が含まれています。透析患者の1日の塩分摂取目安は6g以下と言われていますので、1杯でオーバーしてしまいます。塩分が多いと、のどが渇いて水分をとりすぎる→体重が増えすぎて透析が大変→高血圧や心臓への負担も増えます。 -
カリウム
麺や具材、特に野菜や海藻系トッピングにカリウムが多く含まれています。カリウムが血中に多くなると、不整脈や心停止のリスクが高まります。怖いのは「症状がないまま急に」という点です。 -
リン
スープの出汁やチャーシュー、卵などにはリンがたっぷり。リンが増えすぎると、血管が固くなったり、骨がもろくなったりといった合併症を招きやすくなります。
これらを意識して、「何を」「どれだけ」「どう食べるか」を工夫するのが、透析患者のラーメン攻略の第一歩です。
「外食禁止」と言われるけど本当に全部ダメ?
病院の栄養指導では「外食は控えて」とよく言われます。でも、患者目線から言わせてもらうと「無理!」って思いますよね。大事なのは「外食の頻度と選び方」です。たとえば、外食は月1回、体調が良い時に限定する。外食をする日は前後の食事を調整する(リンやカリウムを抑えた食事を意識する)など、バランスをとればOKです。
私の場合、外食をしたい日は、朝と昼をあっさり目にして、野菜を減らし、リンの少ないメニューを選びます。透析仲間の中には、食べた分だけ翌日しっかり体重をコントロールし、透析中の除水で調整している人もいます。ただし、無理は禁物。医師や看護師にも相談して、自分に合った「外食ルール」を見つけましょう。
食べてもOKなラーメンの条件と選び方
透析患者が食べても安心なラーメンを選ぶ時のポイントは3つあります。
-
スープはなるべくあっさり系(塩分少なめ)
とんこつや味噌は塩分が高めなので、塩ラーメンや醤油ラーメンがおすすめ。ただし、魚介系はリンが多いので注意が必要です。 -
麺は量を少なめ、できれば低リン・低カリウム麺を
最近はこんにゃく麺や低リン麺を扱うお店もありますし、自宅で作るならそういった麺にするのが理想です。 -
トッピングは慎重に選ぶ
チャーシューは脂肪もリンも多いので控えめに。卵はリンが多いので、控えた方が無難です。代わりに、メンマやネギなど少量で楽しむトッピングを選ぶといいでしょう。
食べた後どうする?透析患者のリスク回避術
ラーメンを食べた後のケアはとても大事です。
-
水分をすぐに取らない
スープの塩分で喉が渇きますが、そこはぐっと我慢。少量の氷を口に含むだけにして、余計な水分摂取は控えます。 -
体重管理を意識する
ラーメンを食べた日は、体重がいつもより増えやすいので、翌日は水分や食事の摂取量をさらに意識して調整します。 -
次回の透析で医師や看護師に相談
「ラーメン食べちゃいました」と報告すると、除水量を少し考えてくれたり、血圧の変化を気にしてくれたりします。無理に隠さず、オープンに伝えることが大切です。
透析患者でも安心!ラーメン選びの実践テクニック
ラーメンの種類別リスクとおすすめ度【醤油・味噌・とんこつ・塩・しょうゆとんこつ・魚介・つけそば】
ラーメンにはいろいろな種類がありますよね。スープの味も違えば、使われる素材も違います。透析患者にとっては、どのラーメンを選ぶかがとても重要。ここでは、それぞれのラーメンの「塩分」「カリウム」「リン」のリスクと、おすすめ度を分かりやすくまとめてみました。
| ラーメンの種類 | 塩分量 | カリウム量 | リン量 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| 醤油 | 中 | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
| 味噌 | 高 | 中 | 高 | ★★☆☆☆ |
| とんこつ | 高 | 低 | 高 | ★★☆☆☆ |
| 塩 | 中 | 中 | 中 | ★★★☆☆ |
| しょうゆとんこつ | 高 | 中 | 高 | ★★☆☆☆ |
| 魚介 | 中 | 高 | 高 | ★☆☆☆☆ |
| つけそば | 高 | 中 | 高 | ★☆☆☆☆ |
-
醤油ラーメン
比較的あっさり系で、塩分も控えめな場合が多いです。店によりますが、スープを残すなどの工夫でリスクを減らせます。 -
味噌ラーメン
味噌ダレに塩分が多く含まれている上に、スープもこってり系が多く、リンも高め。味は濃いので満足感はありますが、回数は控えめに。 -
とんこつラーメン
濃厚なスープに塩分とリンがたっぷり。カリウムは比較的低いですが、透析患者には負担が大きいので注意。 -
塩ラーメン
塩分はそれなりにありますが、スープが透き通っていて具材もシンプルなことが多いので、比較的選びやすいメニューです。 -
しょうゆとんこつラーメン
醤油の塩分+とんこつのリンが合わさり、ダブルパンチ。濃厚好きな人は手が出やすいですが、控えめに。 -
魚介系ラーメン
魚の出汁にはリンが多く含まれています。健康な人にはヘルシーなイメージですが、透析患者にはちょっと危険です。 -
つけそば(つけ麺)
スープが濃い目で塩分が高く、麺も太くて量が多いことがほとんど。さらに、つけ汁に全部浸けて食べることで、さらに塩分を取りがち。私は月1回以下の頻度にしています。
この表を参考に、自分に合ったラーメンを選んでみましょう。基本は「塩分少なめ・スープ控えめ・量を調整」です。
スープは残すべき?透析患者の「汁事情」

透析患者がラーメンを食べる場合、一番重要なのは「スープを飲まない」こと。
スープにはラーメンの塩分とリンの大部分が溶け込んでいます。私の経験だと、スープを一口飲むだけでも翌日の体重が500g増えたことがあります…。
スープの塩分量は、1杯で約6〜8g。スープを残せば、実際に摂取する塩分は約1/3〜1/2程度に抑えられます。
スープを飲まないコツは「最初からレンゲを使わない」「麺をすすったあと、スープは切るようにして食べる」など。
それでも味気ないなら、スープを「一口だけ」と決める。無理せず楽しむのも大切ですが、自己管理を意識しましょう。
麺は何がベスト?中華麺、こんにゃく麺、低リン麺の比較
ラーメンの麺にも注意が必要です。
一般的な中華麺にはリンや塩分が含まれていることが多いです。特に「かんすい」が使われているため、カリウムが気になります。
おすすめは「こんにゃく麺」や「低リン麺」。
こんにゃく麺はカロリーも低く、リンやカリウムも抑えられています。ラーメン屋ではなかなかありませんが、自宅ラーメンで使えば安心して食べられます。最近では「低リン」「低カリウム」表示のある中華麺もスーパーで買えます。
| 麺の種類 | カリウム量 | リン量 | 塩分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中華麺(一般) | 中 | 高 | 中 | かんすい使用。市販品は要注意 |
| 低リン麺 | 低 | 低 | 低 | 透析患者向けの商品もあり |
| こんにゃく麺 | 低 | 低 | 低 | カロリーカットも期待 |
トッピングの選び方とNG例(チャーシュー、卵、海苔…)
トッピングは「美味しさの要」ですが、透析患者にとってはリスクも潜んでいます。
-
チャーシュー
リンが多く、脂質も高い。薄め1枚に抑えるのがおすすめ。 -
味玉(煮卵)
リンとカリウムが非常に高い。丸ごとはNG。半分だけにするか、避けましょう。 -
海苔
意外にカリウムが高い。1枚ならOKですが、トッピング盛りは避けたいところ。 -
メンマ
塩分が高いので、少量だけにしましょう。減塩メンマがあればベター。 -
ネギ
比較的安心。ただし、大量摂取はカリウムが増えます。
工夫次第で、安心してトッピングを楽しむことも可能です。お店によってはトッピングの量を減らしてもらえますので、注文時にお願いするのも良いですよ!
「減塩」「低カリウム」のラーメン店を探す方法
最近では健康志向のラーメン店も増えています。
「減塩ラーメン」や「低カロリー」「ビーガン対応」など、透析患者でも比較的安心して楽しめるお店があります。
探し方は、以下の方法が有効です。
- Googleマップで「減塩 ラーメン」と検索
- 食べログやレビューサイトで「健康志向」「あっさり系」でフィルター
- SNS(特にInstagram)で「#減塩ラーメン」「#健康ラーメン」タグ検索
透析患者のコミュニティや、患者会でも情報が共有されていることがあるので、積極的に情報交換してみましょう。
袋ラーメン・インスタントは透析患者でもOK?
市販の袋ラーメンはNG?選ぶ時の3つのポイント

市販の袋ラーメンは手軽で安価。つい食べたくなりますよね。でも、透析患者にとっては注意点がたくさんあります。ただし「NG」と決めつける必要はなく、ポイントを押さえれば食べられます。
1つ目は「塩分」。袋ラーメンのスープには多くの塩分が含まれています。パッケージ裏の「ナトリウム量(mg)」をチェックして、できれば1食あたり2g以下のものを選ぶと安心。
2つ目は「リン」。加工食品には「リン酸塩」という食品添加物が使われがちです。「リン酸塩」「調味料(アミノ酸等)」の表示が多いものは避けたほうが無難です。
3つ目は「カリウム」。乾燥野菜が添付されている商品は、戻すとカリウムが増えます。シンプルなものを選び、自分でトッピングを調整するのがベスト。
私は「無化調」や「減塩」と書かれたものを選びつつ、スープを薄めて使う工夫もしています。
減塩ラーメンは本当に安心?成分表示の見方
「減塩」と書かれているラーメンなら大丈夫!…と言いたいところですが、油断は禁物。「減塩」はあくまで「従来品と比べて」なので、まだまだ塩分が高いことが多いです。
成分表示を見るときは、以下の3つをチェックしましょう。
- 食塩相当量(スープ込み)
目安は1食あたり4g以下。理想は2g以下です。 - ナトリウム量ではなく、食塩相当量で確認
ナトリウム(mg)だとわかりにくいので、「食塩相当量」を基準にします。 - リン酸塩、アミノ酸等の表記
リンの多い添加物があるかをチェック。なければ安心材料です。
最近では「管理栄養士監修」のインスタント麺もありますよ。こうした商品を選べば、ある程度安心感があります。
自宅でできる!リンやカリウムを減らす調理法
インスタント麺を自宅で調理する時、一工夫するだけでリンやカリウムを減らせます。
-
麺は一度茹でこぼす
一度お湯で茹でてから、茹で汁を捨てることでカリウムとリンを減らせます。特に乾麺は有効。 -
スープは薄めに作る
粉末スープを全部入れず、半分〜1/3にするのがおすすめ。代わりに「だし」を加えると旨味が出ます。 -
具材は低カリウム・低リンを選ぶ
もやしを軽く茹でたものや、白菜などをトッピング。肉はゆで鶏にすると安心です。 -
調味料を工夫する
塩分の代わりに「柚子胡椒」や「すだち」を使うと、風味が増して満足度アップ。
リンやカリウムのコントロールは「下処理」がポイント。丁寧にやると安心感も違います!
インスタントでも工夫次第!トッピングで栄養バランスを取る
透析患者にとって、インスタントラーメンは栄養バランスが心配。でも、トッピングを工夫すれば、安心して楽しめます。
おすすめのトッピングは…
- ゆで鶏(リン少なめ、たんぱく質補給)
- もやし(茹でてカリウムを減らす)
- ネギ(少量ならOK、風味アップ)
- すだち・レモン(塩分控えめでも味を引き締める)
- 卵白だけの卵焼き(リンを抑えつつたんぱく質補給)
逆に避けたいのは、
- チャーシュー(特に脂身が多いもの)
- 味玉(リン・カリウムともに高い)
- 練り物(リンが多い食品添加物入りが多い)
トッピングの工夫で、インスタントラーメンも「安全なお楽しみ」になります。
ラーメンを食べた後に気をつけたい透析患者のケア方法
食後の水分管理と体重コントロールのポイント
ラーメンは塩分が多いので、どうしても喉が渇きます。でもすぐに水分を取るのは危険です。私がやっているのは基本的に「氷を舐める」「口をゆすぐ」「ガムを噛む」といった方法。水分は、次の透析までの増えすぎが心配なので、なるべく控えめに!
体重は、食後から翌日の透析までの間にこまめにチェックが必要ですね。例えば「体重が1kg以上増えた場合は要注意」というマイルールを自分に課すのもあり。急激な体重の増加は、心身に負担をかけます。透析時
前日に水分管理をしっかりすれば、透析中の除水もスムーズになりますよ。
血圧が上がった時の対処法と日常のチェック
ラーメンを食べると、塩分過多で血圧が上がりやすくなります。食後の血圧測定を習慣にしましょう。上が140mmHgを超えたら要注意です。
もし高血圧が続く場合は、
- 塩分摂取量の見直し
- 水分摂取の調整
- 医師に相談
を早めに行いましょう。
次回の透析で注意するべきポイントとは?
ラーメンを食べた後の透析は、
- 体重増加(除水量増加)
- 高血圧
- リン値・カリウム値の急上昇
に注意です。
事前に透析スタッフに「ラーメン食べちゃいました!」と報告すると、
- 血圧測定をこまめにしてくれたり
- 除水ペースを考慮してくれたり
と対応してもらえます。遠慮せずにオープンに伝えましょう。
医師・看護師に話すべきか?報告のタイミング
基本は「ラーメン食べた日」を申告するのがベターです。
私は透析開始時に、看護師さんへ一言伝えています。
報告することで、安全に透析を受けられ、何かあった時にも迅速に対応してもらえます。
「たまのご褒美」にする!頻度とルールの決め方
ラーメンはあくまで「ご褒美」
- 月1〜2回
- 体調が良い日限定
- 前後の食事と水分管理を徹底
が私のルール。
これで20年以上透析を続けても、大きなトラブルはありません。ストレスを溜めず、楽しみを上手に取り入れるのが、長く透析生活を続けるコツだと思います。
まとめ
透析患者でも、工夫とルールを守ればラーメンを楽しむことは可能です。
「絶対にダメ」と思い込まず、体調と相談しながら「たまのご褒美」を味わうことが、長く透析生活を続けるためのモチベーションにもなります。
ポイントは、
- ラーメンの種類や具材をしっかり選ぶ
- スープは飲まない、スープの濃さを調整する
- 食後の水分管理と体重コントロールを徹底
- 医師や看護師にしっかり報告する
この4つです。
透析をしていても「食の楽しみ」は大事です。私自身、ラーメンを楽しむ日は、なんだか気分が晴れて、その後の自己管理も頑張れたりします。この記事が、同じ透析仲間の皆さんの「楽しく、美味しく、生きるヒント」になれば嬉しいです。