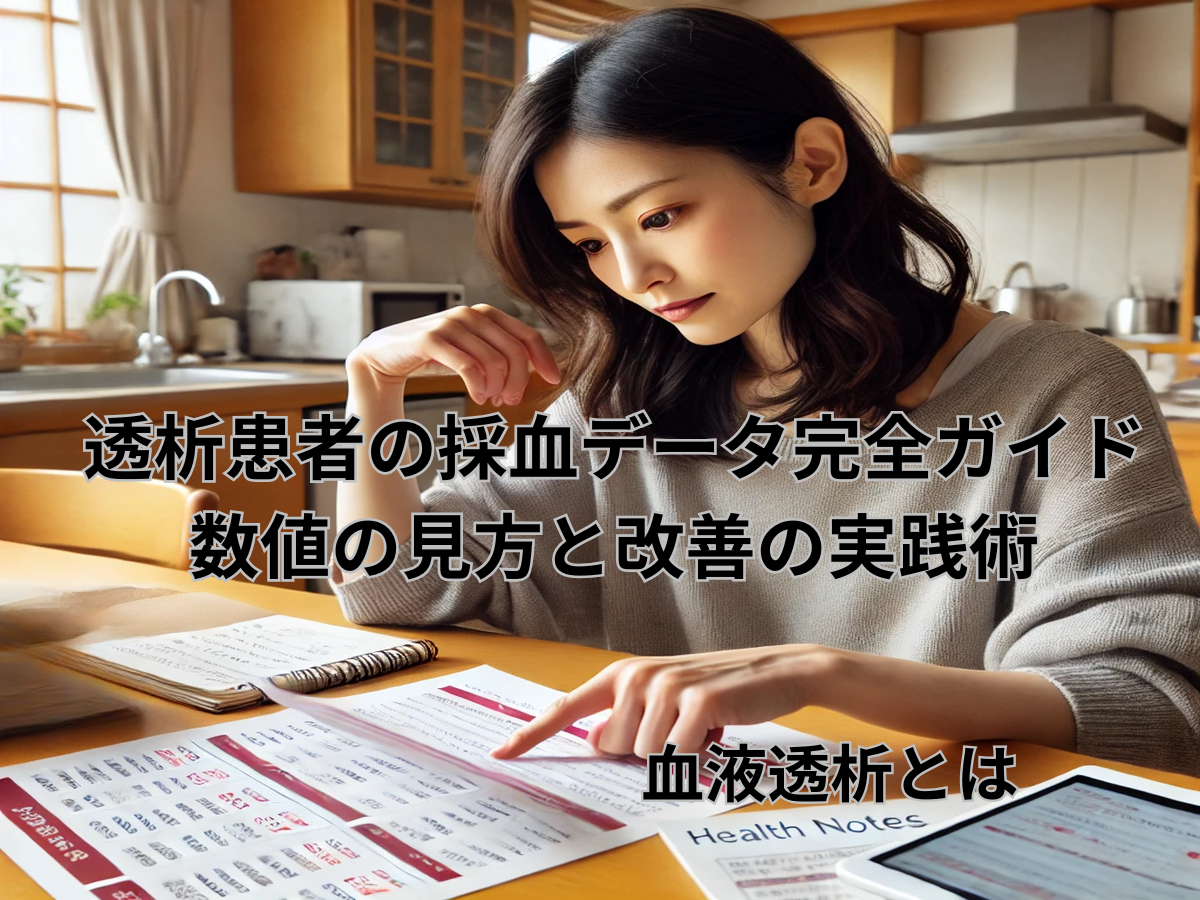
透析治療を始めたばかりの方や、長年続けている方にとって、定期的な採血検査は欠かせないものです。私も透析歴20年を超えていますが、最初のころは検査結果の紙をもらっても、数値の意味がさっぱり分からず不安でいっぱいでした。「この数値が高いのは危険なの?」「どうすれば良くなるの?」と悩んだ日々を今でも覚えています。
この記事では、透析患者さんが知っておくべき採血データの見方と、数値を改善するための実践的なアドバイスをお伝えします。私自身の経験も交えながら、あなたの透析生活の質を高めるお手伝いができれば嬉しいです。
透析患者にとって採血データが重要な理由
透析患者にとって採血データは、単なる数字の羅列ではなく、体の状態を映し出す大切な「健康の地図」なんです。私が透析を始めた頃、医師から「あなたの体は数値で語るようになりますよ」と言われたことがあります。当時はピンときませんでしたが、今ではその言葉の重みを実感しています。
腎臓の機能が低下した私たち透析患者は、体内の老廃物や水分、電解質のバランスを自分でコントロールすることができません。そのため、透析治療によってこれらを調整する必要があるのです。採血データは、その調整がうまくいっているかを確認する重要な指標となります。
ある時、私は「どうせ医師が見るんだから、自分で理解する必要はないだろう」と思っていました。でも、自分の数値を把握し始めてから、食事や生活習慣の改善点が明確になり、体調管理が格段に楽になったんです。例えば、リン値が高いときは前日に何を食べたかを振り返ることで、次回からの食事選びに活かせるようになりました。
また、透析間の体重増加と血圧の関係を理解することで、水分管理の重要性も実感できました。数値を知ることは、自分の体と向き合うための第一歩なのです。
透析患者が注目すべき主な採血データ
透析患者さんが特に注目すべき採血データをご紹介します。これらの数値を理解することで、自分の体調管理に役立てることができますよ。
クレアチニンと尿素窒素(BUN)
クレアチニンと尿素窒素(BUN)は、腎機能の指標として最も基本的な数値です。健康な人なら腎臓でろ過されて尿として排出されるものですが、私たち透析患者は体内に蓄積されてしまいます。
私の場合、透析前のクレアチニン値は通常10〜12mg/dLほどで、透析後は4〜5mg/dLまで下がります。健康な人の基準値(0.6〜1.1mg/dL程度)と比べるとかなり高いですが、これは透析患者としては一般的な範囲です。
ある時期、私のクレアチニン値が急に上昇したことがありました。焦って医師に相談したところ、「筋肉量が増えたのかもしれないね」と言われました。実は、クレアチニンは筋肉の代謝産物でもあるため、筋トレを始めた時期と重なっていたのです。このように、数値の変化には様々な要因があることを知っておくと安心できます。
尿素窒素(BUN)も同様に、透析前後で大きく変動します。私の場合、透析前は60〜70mg/dL、透析後は20mg/dL前後になります。この数値の変化率(尿素除去率)は、透析の効率を示す指標にもなるんですよ。
カリウム
カリウムは、私たち透析患者にとって最も注意すべき電解質の一つです。高カリウム血症は心臓のリズムを狂わせ、最悪の場合、命に関わることもあります。
健康な人の基準値は3.5〜5.0mEq/Lですが、透析患者は食事制限をしていても上昇しやすいです。私の場合、透析前は4.5〜5.5mEq/L程度を維持するよう心がけています。
以前、バナナやトマトなどカリウムの多い果物や野菜を好んで食べていた時期があり、数値が6.0mEq/Lを超えてしまったことがあります。その時は手足のしびれや動悸を感じ、医師から厳重注意を受けました。それ以来、食品のカリウム含有量表を壁に貼り、意識するようにしています。
特に夏場は汗でカリウムが失われるため油断しがちですが、スポーツドリンクには意外とカリウムが含まれていることも覚えておきましょう。水やお茶で水分補給するようにしています。
リン
リンの管理も透析患者には重要です。高リン血症が続くと、骨からカルシウムが溶け出し(骨軟化症)、血管や関節に石灰化を引き起こす原因になります。
健康な人の基準値は2.5〜4.5mg/dLですが、透析患者は6.0mg/dL以下を目標にすることが多いです。私の場合、リン吸着薬を服用しながら、食事にも気をつけて5.0mg/dL前後をキープしています。
リンは加工食品や清涼飲料水、インスタント食品に多く含まれています。「えっ!」と思いますが、特にコーラなどの炭酸飲料には驚くほど多くのリンが含まれています。ですので、飲みたいときもありますが、飲む量を減らしました。また、リン吸着薬は食事の最初に飲むことで効果が高まることも、経験から学びました。
ある時、リン値が急に上昇したことがあり、原因を探ったところ、新しく始めたプロテインサプリメントにリンが多く含まれていたことが判明しました。このように、新しい食品やサプリメントを取り入れる際は、リン含有量にも注意が必要です。サプリメントについては、別記事で取り上げていきます。
カルシウム
カルシウムはリンと密接に関連しており、バランスが重要です。透析患者はビタミンDの活性化が不十分なため、カルシウムの吸収が悪くなりがちです。
健康な人の基準値は8.5〜10.5mg/dLで、透析患者もこの範囲内を目指します。私の場合、透析液のカルシウム濃度調整と、ビタミンD製剤の服用によって9.0mg/dL前後を維持しています。
あまり意識はいなかったのですが、年齢を重ねるにつれ、骨粗しょう症が気になりますね。いずれ、医師と相談して、カルシウムとビタミンDのバランスを見直しについて相談する時期が来るでしょう。骨の健康は目に見えないだけに、数値で確認することが大切ですね。
ヘモグロビン(Hb)
ヘモグロビンは赤血球中の酸素運搬タンパク質で、腎性貧血の指標となります。腎臓からのエリスロポエチン分泌が減少するため、透析患者は貧血になりやすいのです。
健康な男性の基準値は13.0〜17.0g/dL、女性は12.0〜16.0g/dLですが、透析患者は10.0〜12.0g/dLを目標にすることが多いです。私の場合、エリスロポエチン製剤の注射と鉄剤の投与によって11.0g/dL前後を維持しています。
貧血が進むと、疲れやすさや息切れ、動悸などの症状が現れます。私も一時期、仕事中の集中力低下や帰宅後の極度の疲労感に悩まされていました。ヘモグロビン値が9.0g/dL台まで下がっていたのが原因でした。治療によって数値が改善すると、驚くほど体が軽くなり、日常生活の質が向上したのを覚えています。
アルブミン
アルブミンは肝臓で作られるタンパク質で、栄養状態を示す重要な指標です。透析患者は食事制限やタンパク質の喪失により、低アルブミン血症になりやすいです。
健康な人の基準値は3.8〜5.3g/dLで、透析患者も3.5g/dL以上を維持することが望ましいとされています。私の場合、良質なタンパク質摂取を心がけ、4.0g/dL前後をキープしています。
アルブミン値が低下すると、むくみやすくなったり、傷の治りが悪くなったりします。私も一時期、風邪をひいた後に食欲不振が続き、アルブミン値が3.2g/dLまで下がったことがあります。その時は足のむくみが目立ち、透析中の血圧低下も頻繁に起こるようになりました。栄養士さんと相談して食事内容を見直し、少しずつ改善していきました。
C反応性タンパク(CRP)
CRPは炎症の指標となるタンパク質です。感染症や炎症性疾患があると上昇します。透析患者は感染リスクが高いため、定期的にチェックされます。
健康な人の基準値は0.3mg/dL以下で、透析患者も同様です。私の場合、通常は0.1mg/dL以下ですが、風邪やシャント部の炎症時には上昇することがあります。
ある冬、なんとなく体がだるく、透析中も寒気がするような日が続きました。採血結果でCRPが1.2mg/dLと高値を示し、精密検査の結果、軽度の肺炎が見つかったことがあります。早期発見・早期治療ができたのは、定期的な採血のおかげでした。CRPの上昇は体からのSOSサインと捉え、軽視しないことが大切です。
採血データの見方と理解するコツ
採血データを見るときのコツをいくつかご紹介します。私も最初は戸惑いましたが、これらのポイントを押さえると理解しやすくなりますよ。
| 項目 | 役割・意味 | 透析患者の目標値 (参考) |
|---|---|---|
| クレアチニン | 腎機能の指標。腎臓が老廃物を排泄できているかを示す。 | 8~12 mg/dL(透析前) |
| BUN | 尿素窒素。タンパク質代謝の老廃物で腎機能の評価に使われる。 | 60~100 mg/dL |
| カリウム | 体内の電解質バランス、心臓・筋肉機能に重要。 | 3.5~5.5 mEq/L |
| リン | 骨の代謝に関与し、腎不全で高くなりやすい。 | 3.5~6.0 mg/dL |
| カルシウム | 骨の健康維持に必要。リンとのバランスが重要。 | 8.4~10.2 mg/dL |
| ヘモグロビン | 酸素を運ぶ赤血球の構成成分。貧血の指標。 | 10~12 g/dL |
| アルブミン | 栄養状態を反映する血清タンパク質。低値は栄養不良を示す。 | 3.5 g/dL 以上 |
| CRP | 炎症や感染の指標。上昇は体内で炎症があるサイン。 | 0.3 mg/dL 以下 |
透析前後の数値の違いを理解する
透析患者の採血データを見る際に最も重要なのは、透析前と透析後の数値の違いを理解することです。特にクレアチニン、尿素窒素(BUN)、カリウムなどは透析によって大きく変動します。
私の場合、透析前後でBUNは65mg/dLから20mg/dLへ、クレアチニンは12mg/dLから5mg/dLへと変化します。この変化率(除去率)が高いほど、透析の効率が良いと言えます。
ある時、風邪で食欲がなく、透析前のBUNが普段より低かったことがありました。医師に相談したところ、「タンパク質摂取量が減っているのかもしれない」と指摘されました。このように、数値の変化には生活状況が反映されることを知っておくと、自己管理の参考になります。
また、透析間の体重増加と採血データの関係も重要です。水分摂取量が多く、体重増加が大きいと、透析前の数値が希釈されて実際より低く出ることがあります。逆に、体重増加が少ないと濃縮されて高く出ることも。私は透析間の体重増加率を3~5%以内に抑えるよう心がけています。
経時的な変化をチェックする
一回の採血結果だけでなく、経時的な変化を追うことが大切です。私は毎月の採血データをノートに記録し、グラフ化しています。これにより、徐々に進行する変化や季節変動なども把握できるようになりました。
例えば、私の場合、夏場はカリウム値が下がりやすく、冬場はリン値が上がりやすい傾向があることがわかりました。夏は汗でカリウムが失われるため、冬は活動量が減って代謝が落ちるためかもしれません。こうした自分の体の傾向を知ることで、先手を打った対策ができるようになります。
また、数年単位での変化も重要です。私の場合、透析歴10年を過ぎたあたりから、アルブミン値が徐々に低下する傾向が見られました。栄養士さんと相談して食事内容を見直し、筋トレも取り入れることで改善できました。長期的な視点で自分の体と向き合うことの大切さを実感しています。
基準値と目標値の違いを知る
健康な人の「基準値」と、透析患者の「目標値」は異なることが多いです。これを理解せずに一般的な基準値と比較すると、不必要な不安を抱くことになります。
例えば、クレアチニンは健康な人なら1.0mg/dL前後ですが、透析患者は透析前で10mg/dL以上あっても珍しくありません。これは腎機能がないため当然のことで、心配する必要はないのです。
私も最初のころは、基準値を大きく外れる数値に不安を感じていました。ある時、同じ透析施設の先輩患者さんに「透析患者の数値は健康な人とは違って当たり前だよ」と教えてもらい、肩の荷が下りた思い出があります。
大切なのは、医師と相談して自分の目標値を設定し、それに向けて管理していくことです。私の場合、カリウムは5.5mEq/L以下、リンは5.5mg/dL以下、ヘモグロビンは11.0g/dL以上を目標にしています。この目標値は体調や年齢によって変わることもあるので、定期的に医師と相談することをおすすめします。
採血データを改善するための実践的アドバイス
採血データを改善するためには、日常生活での工夫が欠かせません。私自身の経験から得た実践的なアドバイスをご紹介します。
食事管理のコツ
透析患者にとって食事管理は治療の一環です。特にカリウム、リン、塩分、水分の管理が重要になります。
カリウム対策としては、野菜や果物を生で食べるのではなく、茹でこぼしや水にさらすことで含有量を減らす工夫が効果的です。私は週末にまとめて野菜を茹でこぼし、小分けにして冷凍保存しています。忙しい平日でも手軽に低カリウム食が実践できるようになりました。
また、リン対策としては、加工食品やインスタント食品を避け、なるべく手作りの食事を心がけています。特にハムやソーセージ、練り製品などには食品添加物としてリンが多く含まれているので注意が必要です。
塩分制限は血圧管理や水分制限にも関わる重要なポイントです。調味料を計量スプーンで測る習慣をつけ、徐々に薄味に慣れていく。また、香辛料やハーブ、レモン汁などを活用することで、塩分控えめでも美味しく食べられるようになりました。
食事記録をつけることも効果的です。私はスマホのアプリで食事内容と採血データを記録し、関連性を分析しています。例えば、外食が続いた週はリン値が上昇しやすいことがわかり、外食時の食べ物選びに活かしています。
薬の正しい飲み方
透析患者は複数の薬を服用することが多いですが、その飲み方も重要です。特にリン吸着薬は食事中または食直前に飲むことで効果を発揮します。
私は以前、リン吸着薬を食後に飲んでいたのですが、リン値がなかなか下がりませんでした。医師に相談したところ、「食事と一緒に飲まないと効果が半減する」と教えられ、飲み方を変えたところ、次の検査ではリン値が改善していました。
また、薬の飲み忘れ防止も大切です。私は大丈夫ですが、患者さんよって薬の数量も違いますから、朝・昼・晩の薬をピルケースに一週間分セットしておくとか、スマホのアラームで服薬時間を管理するといったように工夫することが必要です。旅行も含めてですが、外出時には携帯用のピルケースを持ち歩き、どんな状況でも服薬できるようにしています。
薬の副作用にも注意が必要です。例えば、鉄剤は便秘を引き起こすことがあります。私の場合、便秘になると透析効率も落ちるため、食物繊維を意識的に摂るようにしています。何か気になる症状があれば、自己判断せずに医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
適切な運動習慣
適度な運動は、透析患者の体調管理に大きく貢献します。特にアルブミン値の維持や筋力低下防止に効果的です。
私は透析のない日に30分程度のウォーキングを習慣にしています。最初は5分程度から始めて、徐々に時間を延ばしていきました。また、自宅でできる簡単な筋トレも取り入れています。特に下半身の筋力維持は、透析中の血圧低下防止にも役立っています。
ただし、シャント側の腕に負担をかけ過ぎないよう注意が必要です。私は理学療法士に相談して、シャントを保護しながらできるエクササイズを教えてもらいました。また、運動前後の水分補給も忘れずに行っています。
運動を続けるコツは無理をしないことです。「今日はちょっとだけ」と思って始めると続きやすいですよ。私も体調に合わせて強度を調整しながら、長く続けることを心がけています。
ストレス管理と質の良い睡眠
ストレスや睡眠不足は、様々な数値に悪影響を及ぼします。特にCRPの上昇や免疫力低下につながることがあります。
私はストレス解消法として、趣味の読書や音楽鑑賞の時間を大切にしています。また、深呼吸や簡単な瞑想も取り入れています。透析中の時間を有効活用し、映画を観たり、好きな本を読んだり、音楽を聴いたりすることで、治療のストレスも軽減できています。
質の良い睡眠も重要です。実のところ私は寝つきが悪いです。就寝前、スマホを見るなどブルーライトを避け、寝室の温度と湿度を快適に保つような心がけは必要です。平日・土日祝日とを問わず、就寝時間と起床時間を一定にすることで、体内時計を整えるようにするのがよいですね。
私事ながら、かれこれ20年超の透析歴とデスクワークはある種、連動しているのですが、若いころにいた現場とは違い、仕事のストレスで不眠が続き、採血データが悪化し続けた時期ががありました。仕事上のミスや悩み事を病院、いやベットの中にまで持ち込んでしまう性格もあったからでしょう。その経験から、心と体の健康は密接に関連していることを痛感しましたね。
今では「良い数値のためには良い心の状態も必要」と考え、ストレス管理も治療の一部として捉えています。
採血データが気になるときの対処法
採血データが気になるときは、冷静に対処することが大切です。私自身の経験から学んだ対処法をご紹介します。
医療スタッフとの効果的なコミュニケーション
採血データで気になる点があれば、遠慮なく医療スタッフに質問しましょう。私は検査結果をもらったら、まず自分で前回との比較をし、疑問点をメモしておきます。そして診察時に「○○の数値が前回より上がっていますが、何か考えられる原因はありますか?」と具体的に質問するようにしています。
例えば、リン値が急に上昇したときは、「最近の食生活で変わったことはありますか?」と医師に聞かれ、新しく始めたプロテインドリンクを飲んだことが原因だと伝えたことで「それが原因かも」と言われていた患者さんもいました。このように、自分の生活の変化を伝えることで、より的確なアドバイスがもらえるんですね。
また、看護師や栄養士、臨床工学技士など、様々な専門スタッフの知識を活用することも大切です。栄養士さんには1週間の食事記録を見てもらい、カリウムやリンの摂り過ぎを指摘してもらっうといった感じです。
質問するときのコツは、「なぜその数値が問題なのか」「どうすれば改善できるのか」という具体的な情報を求めることです。ただ「この数値は大丈夫ですか?」と聞くよりも、「この数値を改善するために、日常生活で気をつけることはありますか?」と聞いた方が実践的なアドバイスがもらえます。
急な数値変化があったときの対応
採血データに急な変化があったときは、パニックにならず、まず考えられる原因を探りましょう。
私の場合、ある時カリウム値が6.8mEq/Lと危険な高値を示したことがあります。思い返してみると、前日に干し柿を大量に食べていたことに気づきました。干し柿は乾燥させることでカリウムが濃縮されるのです。このように、食事内容を振り返ることで原因が見つかることも多いです。
また、季節の変化や体調不良、運動量の変化なども数値に影響します。私は夏場に熱中症で脱水になった際、クレアチニンやBUNが普段より高く出たことがあります。体内の水分が減ると、血液が濃縮されて数値が上がるのです。
急な変化があった場合は、次回の検査までに生活習慣を見直し、改善に努めましょう。それでも改善しない場合は、医師に相談することが大切です。私は一度、CRP値が3ヶ月連続で上昇したため医師に相談したところ、精密検査を受けることになり、早期に歯周病を発見・治療できました。
不安を軽減するための情報収集
採血データに関する不安を軽減するには、正確な情報収集が欠かせません。インターネット上には様々な情報がありますが、信頼性の高いソースから情報を得ることが大切です。
私がおすすめするのは、日本透析医学会や日本腎臓学会などの公式サイト、大学病院や専門病院等が発行している患者向け資料です。また、透析患者会の情報誌も実体験に基づいた貴重な情報源になります。
書籍では、医師や看護師が監修した透析患者向けの解説本が参考になります。私は「透析患者のための食事療法ガイド」や「透析生活を快適に過ごすコツ」など、実践的なアドバイスが載った本を何冊か持っています。
また、同じ透析施設の患者さんとの情報交換も有益です。採血データの改善に成功した方の体験談もありますが、人差があることを念頭に置き、自分に合った方法を見つけることが大切です。
情報収集の際は、「なぜそうなるのか」という仕組みを理解することを心がけています。単に「これを食べてはいけない」ではなく、「なぜ食べてはいけないのか」を知ることで、応用が利くようになるからです。
採血データと上手に付き合うための心構え
最後に、採血データと上手に付き合うための心構えについてお話しします。
完璧を求めすぎない
採血データの管理で大切なのは、完璧を求めすぎないことです。すべての数値を理想的な範囲内に保つことは、現実的には難しいことがあります。
私も透析歴20年超の中で、理想的な数値を維持できない時期がありました。特に仕事が忙しい時期は、食事管理が難しく、数値が乱れがちでした。そんな時、担当医から「人生の中で透析はあくまで一部。無理なく続けられる範囲で管理していきましょう」と言われ、肩の荷が下りた思い出があります。
大切なのは、長期的な視点で徐々に改善していくことです。例えば、いきなり完璧な食事制限を始めるのではなく、まずはカリウムの多い食品を減らすことから始め、慣れてきたらリンの管理も加えるといった段階的なアプローチが効果的です。
また、特別な日や行事の際は、多少の逸脱も自分へのご褒美と考え、その後の調整で対応することも大切です。私は誕生日や記念日には好きなものを少し楽しみ、翌日から数日間は特に厳しく管理するようにしています。このメリハリが、長期的な自己管理のモチベーション維持につながっています。
自分の体調との関連を意識する
採血データは単なる数字ではなく、自分の体調と密接に関連しています。数値の変化と体調の変化を結びつけて考えることで、自己管理の意識が高まります。
私の場合、カリウム値が高い時は手足のしびれや脱力感を感じることがあります(ちょっとコーヒー飲みすぎなのかも)。また、ヘモグロビン値が低下すると、階段の上り下りで息切れがしやすくなります。このように、数値と体調の関連を意識することで、「数値を良くするのは自分の体調を良くするため」という実感が湧き、モチベーションにつながります。
ある時には、(もともと血圧は低いほうでしたが)透析中の血圧低下に悩まされていました。採血データを見直すと、アルブミン値が低下していることに気づきました。栄養状態を改善するため、良質なタンパク質を意識的に摂るようにしたところ、アルブミン値の上昇とともに透析中の血圧も安定するようになりました。このように、データと体調の関連を知ることで、効果的な対策が取れるようになります。
体調の変化を日記やアプリに記録しておくと、後々採血データとの関連が分かりやすくなりますね。患者さんそれぞれではありますが、「やりやすい方法で」、簡単にメモするとか、日記に残すとかで、採血結果と照らし合わせて自分の体の傾向を把握できれば、と思います。
長期的な視点で改善を目指す
透析治療は長期戦です。一時的な数値の変動に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で改善を目指すことが大切です。
私は透析を始めた頃、毎回の採血結果に一喜一憂していました。数値が悪いと落ち込み、良いと油断するという繰り返しでした。しかし、長年の経験から、季節変動や体調による一時的な変化は避けられないことを学びました。大切なのは、3ヶ月、半年、1年単位での改善傾向です。
直近でいうと、20年超の透析歴のなかで季節変動や体調は「この時期は!」というのが分かっていたのですが、年齢のこともあるでしょう。どうもコロナ禍、異常気象だと言われ続けてきたこの2,3年あたりから、”ズレ”てきていることを感じています。ふだん気にかけている血圧がそうです。
私はコンビニ食などはめったりしないものの、若いころはよくリン値でひっかかることがありました。「何で!」と思っていたのですが、腎性副甲状腺機能亢進症(※)となり、手術することになってしまいました。それ以降もリン吸着薬で調整しています。月によって上下しますが、年間平均で見ると徐々に改善しています。
(※)腎性副甲状腺機能亢進症…透析患者にとって、腎臓の機能低下は骨を丈夫にするホルモン調節も狂わせます。副甲状腺ホルモン(PTH)が過剰になる腎性副甲状腺機能亢進症は、血液中のカルシウム不足が原因。骨からカルシウムが溶け出し、骨がもろくなったり、血管にカルシウムが溜まったりするリスクがあります。対策として、リンの摂取制限、活性型ビタミンDやPTHを下げる薬の服用、そして適切な透析治療が重要です。自身の状況を理解し、医師と相談しながら、骨の健康維持にも気を配ることが大切です。
また、定期的に自分の採血データを振り返る時間を設けることも効果的です。過去のデータを見直し、改善点や悪化している点をチェックしてもらい、医師や看護師、栄養士さんと相談しながら、次の目標を設定するようにしていくのです。
腎移植でもしない限り、透析治療は一生続く可能性がありますが、だからこそ無理なく続けられる自己管理法を見つけることが大切です。私自身、20年超の透析生活で試行錯誤を重ねてきましたが、今では自分なりのバランスを見つけ、比較的安定した数値を維持できるようになりました。皆さんも焦らず、長い目で見て改善を目指していただければと思います。
まとめ:採血データを味方につけて透析生活の質を高めよう
透析患者にとって採血データは、健康管理の重要な指標です。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ理解を深めていくことで、自分の体調管理に役立てることができます。
この記事でご紹介したポイントをおさらいしましょう。まず、クレアチニン、BUN、カリウム、リン、カルシウム、ヘモグロビン、アルブミン、CRPなどの主要な数値の意味を理解することが大切です。そして、透析前後の数値の違いや経時的な変化に注目し、健康な人の基準値と透析患者の目標値の違いを知っておきましょう。
| 項目 | 役割・意味 | 透析患者の目標値(参考) |
|---|---|---|
| クレアチニン | 腎機能の指標。腎臓が老廃物を排泄できているかを示す。 | 8~12 mg/dL(透析前) |
| BUN | 尿素窒素。タンパク質代謝の老廃物で腎機能の評価に使われる。 | 60~100 mg/dL |
| カリウム | 体内の電解質バランス、心臓・筋肉機能に重要。 | 3.5~5.5 mEq/L |
| リン | 骨の代謝に関与し、腎不全で高くなりやすい。 | 3.5~6.0 mg/dL |
| カルシウム | 骨の健康維持に必要。リンとのバランスが重要。 | 8.4~10.2 mg/dL |
| ヘモグロビン | 酸素を運ぶ赤血球の構成成分。貧血の指標。 | 10~12 g/dL |
| アルブミン | 栄養状態を反映する血清タンパク質。低値は栄養不良を示す。 | 3.5 g/dL 以上 |
| CRP | 炎症や感染の指標。上昇は体内で炎症があるサイン。 | 0.3 mg/dL 以下 |
数値を改善するためには、食事管理、薬の正しい飲み方、適切な運動習慣、ストレス管理と質の良い睡眠が重要です。気になる数値があれば、医療スタッフと効果的にコミュニケーションを取り、正確な情報収集を心がけましょう。
そして何より、完璧を求めすぎず、自分の体調との関連を意識しながら、長期的な視点で改善を目指すことが大切です。
私自身、20年の透析生活で多くの試行錯誤を重ねてきました。今でも完璧ではありませんが、採血データを「敵」ではなく「味方」と考え、自分の健康管理に役立てています。皆さんも採血データを上手に活用して、より良い透析生活を送ってください。
最後に、透析治療は医療スタッフとの二人三脚です。分からないことがあれば、遠慮なく質問してください。皆さんの透析生活が少しでも快適になることを願っています。