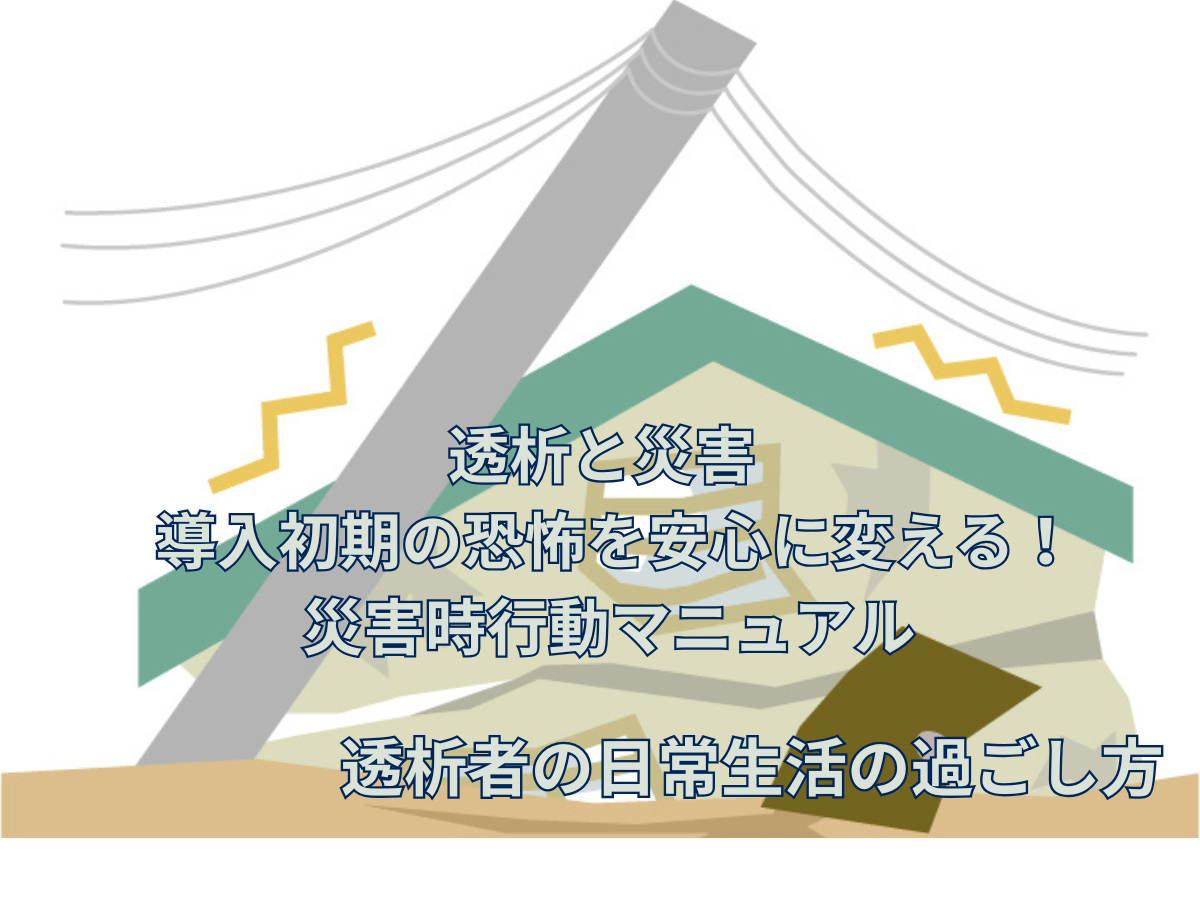
透析導入直後、ただでさえ不安なのに「もし災害が起きたら…?」と考え出すと、もう夜も眠れないですよね。透析治療が受けられなくなったらどうしよう、水や食料は?薬は?そんな心配が頭をぐるぐる…分かります、めちゃくちゃ分かります。
私も透析を始めたばかりの頃、ニュースで地震速報が流れるたびに心臓がバクバクしたものです。
この記事では、そんなあなたの「透析と災害」という重くのしかかる不安に対して、今すぐできる具体的な備えと、いざという時のリアルな行動を、ちょっとお節介かもしれませんが、徹底的に解説します。
これを読めば、漠然とした恐怖が「なんだ、こうすればいいのか!」「これなら自分でもできそう!」という確かな安心感に変わるはず。さあ、一緒に未来への備え、始めませんか?
もしも…透析中に大災害が起きたら?まず考えるべきこと
想像してみてください。いつものように透析を受けている、その瞬間に、経験したことのないような大きな揺れが襲ってきたら…。まず、パニックにならないでください、とは言いません。だって、怖いですよね、普通に。でも、その恐怖の中で、ほんの少しだけ冷静さを保つことが、あなたの命を救う鍵になります。
突然の災害、透析はどうなるの?
透析が受けられなくなる主なリスクと、それに対する認識の重要性を以下で整理します。
| 透析が中断される主なリスク | 対策の必要性 |
|---|---|
| 停電 | 透析機械が停止、情報収集手段(スマホ充電)喪失。 |
| 断水 | 透析に必要な水が確保できない。 |
| 道路寸断 | 透析施設に行けない、スタッフが施設に来れない。 |
| 施設被災 | 施設自体が透析治療を提供できない。 |
| 情報錯綜 | 施設の安否、再開情報、受け入れ先が分からない。 |
| 🚨 認識 | 日本の透析医療体制も万全ではないことを認識し、個人で「知っておく」「備えておく」ことが、ネットワーク活用と命を守るために不可欠。 |
一番心配なのは、やはり「透析が続けられるのか?」ということでしょう。大規模な災害が発生した場合、残念ながら、いつも通りの透析が受けられなくなる可能性は否定できません。停電で透析機械が動かなくなる、断水で透析に必要な水が確保できない、道路が寸断されて透析施設に行けない、あるいは施設自体が被災してしまう…。考え始めるとキリがないですが、様々な理由で透析が中断されるリスクがある、ということはまず認識しておく必要があります。
でも、ここで絶望しないでくださいね。日本の透析医療体制は、災害時にもなんとか機能するように、様々なネットワークや備えを持っています。すぐに全ての機能が停止するわけではありません。だからこそ、私たちが「知っておく」こと、「備えておく」ことが、そのネットワークを最大限に活用し、自分の身を守るために、めちゃくちゃ重要になってくるんです。
正直、私も最初は「災害なんて、自分には関係ない」ってどこかで思ってたんですよね。甘かった、本当に。でも、ある日、透析仲間の先輩が、昔、被災した時の壮絶な体験談を聞かせてくれたんです。「透析が受けられないかもしれない」っていう恐怖、水や食料の制限、情報の錯綜…それを聞いて、もう他人事じゃない、本気で備えなきゃダメだって、背筋が凍る思いで実感しました。実際に年月が経って、東日本大震災を経験しました。「もし、あの時の自分だったら…って。」が現実化となってしまったのです。
情報収集が命綱!どうやって情報を得る?
災害時に最も重要なことの一つ、それは「正確な情報」です。テレビやラジオはもちろんですが、停電時には使えない可能性も。だから、スマートフォンや携帯ラジオは必須アイテム。モバイルバッテリーも忘れずに準備しておきましょう。電池式のラジオも、一つあると安心感が違いますよ。
そして、透析患者にとって特に重要なのが、「透析施設に関する情報」です。自分の通っている施設は無事か?透析は再開されるのか?もしダメなら、どこか受け入れてくれる施設はあるのか?
多くの透析施設では、災害時の連絡方法や安否確認の方法を事前に決めているはずです。施設のウェブサイトや掲示、配布される資料などを必ず確認し、連絡手段(電話番号、SNS、伝言ダイヤルなど)を控えておきましょう。施設のスタッフの方に、直接聞いてみるのが一番確実かもしれませんね。「災害の時って、どうやって連絡取ればいいんですか?」って。
あ、でもその前に説明しておきたいのは、災害直後は電話回線がパンクしやすいってこと。だから、電話以外の連絡手段、例えば災害用伝言ダイヤル(171)の使い方や、SNSでの情報発信なども確認しておくと、いざという時に役立ちます。自治体が発信する防災情報(防災無線、ウェブサイト、SNS、防災アプリなど)も、めちゃくちゃ重要なので、普段からチェックする癖をつけておくと良いです。
避難は必要?どこへ行くべき?
自宅が安全で、ライフライン(電気、水)も確保されているなら、むやみに避難する必要はありません。特に透析患者は、環境の変化が体調に影響しやすいですからね。しかし、家屋の倒壊や浸水の危険がある場合、または自治体から避難指示が出た場合は、速やかに安全な場所へ避難しなければなりません。
問題は、「どこへ避難するか?」です。一般的な指定避難所(学校の体育館など)は、残念ながら透析患者にとって最適な環境とは言えないことが多いです。食事や水分の管理、衛生面、プライバシーの確保など、様々な課題があります。
理想的なのは、透析治療が受けられる、あるいは受け入れ態勢のある「福祉避難所」や、災害拠点病院などですが、全ての地域に十分な数が整備されているわけではありません。まずは、お住まいの自治体のハザードマップや防災計画を確認し、透析患者を受け入れ可能な避難所があるか、事前に調べておくことが重要です。これも、かかりつけの透析施設や、地域の患者会などに相談してみると、情報が得られるかもしれません。
もし、事前に安全な親戚や友人の家を避難先として決めておけるなら、それも一つの有効な手段です。その場合は、避難先でも自分の病状や必要な配慮を伝えられるように準備しておきましょう。(東日本大震災では親類の家に移動しましたし、水道や電気が来ないために、隣県に移動しての透析を経験しています。)
災害への「備え」、これだけは絶対やって!透析患者のための防災リスト
さて、ここからが本番です。「もしも」の時に備えて、私たちが「いつも」からできること。透析患者ならではの、絶対に押さえておきたい防災リストを具体的に見ていきましょう。これはもう、理屈抜きで、やるしかない!ってやつです。
「最重要!「お薬手帳」と「透析条件」の携帯」の項に基づき、肌身離さず携帯すべき最重要アイテムをリスト化します。
| 携帯品 | 必須度 | 目的・注意点 |
|---|---|---|
| 透析条件カード / 災害時連絡カード | 🔥最重要 | ドライウェイト、ダイアライザー、透析時間、薬剤など。避難先の施設で安全な透析を受けるための生命線。常に財布やパスケースに携帯。 |
| お薬手帳 | 🔥最重要 | 常用薬の種類・量を他施設に伝え、適切な処方を受けるために必須。 |
| 常用薬の予備 | 高 | 最低3日分、できれば1週間分を防災リュックに。主治医・薬剤師に相談。 |
| モバイルバッテリー | 高 | 情報収集(スマホ)、連絡手段の確保に。予備電池式ラジオも推奨。 |
| スリッパ/靴 | 中 | 避難時のガラス破片などから足元を守るため。枕元に準備。 |
最重要!「お薬手帳」と「透析条件」の携帯
これ、本当に、本当に、絶対に忘れないでください。災害時、もし自分の通っている施設以外で透析を受けることになった場合、あなたの「透析条件」が分からなければ、安全な透析を行うことができません。
透析条件とは、ドライウェイト(目標体重)、使用しているダイアライザーの種類、透析時間、除水量、血液流量、処方されている薬剤など、あなたの透析治療に関する詳細な情報のことです。これは、あなただけの「カルテ」のようなもの。
多くの透析施設では、「透析カード」や「災害時連絡カード」のような形で、これらの情報をまとめたものを発行してくれています。もし、まだ持っていない場合は、すぐに施設に相談して作成してもらいましょう。そして、それを「お薬手帳」と一緒に、常に携帯する!財布やパスケースなど、肌身離さず持ち歩くものに入れておくのがベストです。
お薬手帳も同様に重要です。あなたが普段服用している薬の種類や量が分からなければ、適切な処方を受けることができません。災害時には、薬の供給が不安定になることも考えられます。最低でも3日分、できれば1週間分程度の予備の薬を、防災リュックなどに入れておくことも検討しましょう。これも、かかりつけ医や薬剤師さんに相談してみてくださいね。
「まあ、大丈夫だろう」なんて思わないでください。災害は、本当に突然やってきます。その時、「あのカード、家に置いてきちゃった…」では、取り返しがつかないことになりかねません。これは脅しじゃなくて、切実なお願いです。
非常食と飲料水 – 透析患者ならではの注意点
災害時の備蓄として、非常食や飲料水は基本中の基本ですが、透析患者は、その内容に特に注意が必要です。一般的な非常食は、保存性を高めるために塩分が多かったり、カリウムやリンが多く含まれていたりすることがあります。
非常食と飲料水に関する透析患者ならではの注意点を以下で整理してみます。
| 項目 | 一般的な注意点 | 透析患者が追加で注意すべき点 |
|---|---|---|
| 非常食 | エネルギー源(炭水化物)の確保。 | 低カリウム・低リンを意識した食品を選ぶ(栄養成分表示を確認)。野菜ジュースや果物缶は避ける。白米(アルファ米)や、低タンパク・低リンのおかずレトルトなどを推奨。 |
| 飲料水 | 1人1日2Lを目安に3日~1週間分備蓄。 | 水分制限を考慮し、備蓄量を調整。透析スタッフに「透析が数日中断した場合の水分制限量」を事前に確認し、脱水と体液過多のバランスを自己管理する。 |
カリウム・リン制限を意識した備蓄食
透析患者にとって、カリウムとリンの管理は生命線です。災害時、透析の間隔が空いてしまう可能性を考えると、普段以上に食事管理が重要になります。
備蓄食を選ぶ際は、栄養成分表示をしっかり確認しましょう。最近では、災害食でも「低カリウム」「低リン」を謳った商品や、腎臓病患者さん向けに開発されたレトルト食品、栄養補助食品なども増えています。例えば、白米やうどん、そうめんなどの炭水化物を中心に、缶詰なら魚介類よりも肉類の缶詰(水煮など、味付けの濃くないものを選ぶ)の方が比較的リンが少ない傾向にあります。野菜ジュースや果物の缶詰はカリウムが多いので避けた方が無難です。
でも、完璧を目指さなくても大丈夫。「何も食べない」よりは、多少制限から外れても、エネルギーを摂取することの方が優先される場合もあります。大切なのは、「意識して選ぶ」こと。普段から、管理栄養士さんに相談して、自分の食べられる非常食リストを作っておくと安心ですね。なんか、こういう地道な準備が、結局一番効くんですよね。
ちなみに、私のおすすめは、アルファ米(白米)と、低タンパク質・低カリウム・低リンのおかずレトルトをいくつかストックしておくこと。あと、エネルギー補給用に、ようかんとか、飴とかも少しあると、精神的にも助かります。
水分制限と備蓄水のバランス
透析患者は、水分制限も重要ですよね。だからといって、災害時に水を全く飲まないわけにはいきません。脱水は命に関わります。
備蓄する飲料水は、1人1日あたり2リットル程度を目安に、最低3日分、できれば1週間分を用意しておきたいところです。これは一般的な目安なので、ご自身の水分制限量を考慮して調整してください。
問題は、災害時にどれくらいの水分を摂るべきか、という判断です。透析が受けられる見込みが立たない状況では、普段よりも厳しく水分を管理する必要があるかもしれません。一方で、暑い時期や、避難所での生活で汗をかくような状況では、脱水を防ぐためにある程度の水分補給が必要です。このバランス、めちゃくちゃ難しいですよね。
これも、普段から主治医や透析スタッフと、「もし災害で透析が数日受けられなかったら、水分は1日どれくらいまでなら大丈夫ですか?」と具体的に相談しておくことが大切です。自分の体調を観察しながら、少しずつ水分を摂る、尿量を記録しておく(もし可能なら)といったセルフケアも重要になります。
電気がない!自家発電やバッテリーの準備は?
これは主に、在宅透析(特に腹膜透析)を行っている方に、より切実な問題かもしれませんが、血液透析の方にとっても無関係ではありません。停電は、情報収集手段を奪い、夜間の安全を脅かし、スマートフォンの充電もできなくさせます。
在宅で腹膜透析(APD)を行っている方は、停電時に機械が使えなくなるため、手動でのバッグ交換(CAPD)に切り替える準備が必要です。そのための知識と技術、そして必要な物品(CAPD用の透析液など)を常に備えておく必要があります。これは、導入時にしっかり指導があるはずですが、いざという時に慌てないよう、定期的に手順を確認しておきましょう。
血液透析の方も、スマートフォンやラジオの充電、最低限の明かりの確保のために、モバイルバッテリーや乾電池、電池式ランタンなどを準備しておくことを強くお勧めします。最近は、ソーラー充電機能付きのモバイルバッテリーや、手回し充電式のラジオライトなど、便利なグッズもたくさんあります。ちょっと投資してでも、備えておく価値は絶対にありますよ。
もっと本格的な備えとして、ポータブル電源や小型の発電機を検討する方もいるかもしれません。これは、費用もかかりますし、保管場所や燃料の管理も必要になるので、誰にでもお勧めできるものではありませんが、選択肢の一つとして知っておくのは良いことだと思います。
透析施設との連携 – 事前に確認しておくべきこと
繰り返しになりますが、かかりつけの透析施設との連携は、災害時の生命線です。
- 災害時の連絡方法(電話、SNS、ウェブサイトなど)
- 安否確認の方法
- 透析が中断した場合の対応方針
- 近隣の連携施設(もし自分の施設が被災した場合、どこで透析を受けられる可能性があるか)
これらの情報を、事前に、具体的に確認しておきましょう。施設のスタッフは、日頃から災害対策について考え、訓練を行っているはずです。遠慮せずに、どんどん質問してみてください。「もしもの時」のために、お互いに顔の見える関係を築いておくことが、何よりの安心材料になります。
そういえば、以前、私が通っているクリニックで防災訓練があったんです。最初は「面倒だなあ」なんて思ってたんですけど(正直者)、実際にスタッフの方々が、災害時の患者さんの誘導や情報伝達の手順を確認しているのを見て、「ああ、ちゃんと考えてくれてるんだな」って、すごく安心したんですよね。参加して良かった、って心から思いました。
災害発生!その時、透析患者が取るべき行動
どれだけ備えていても、いざ災害が発生したら、冷静でいるのは難しいかもしれません。でも、事前に「何をすべきか」を知っておくだけで、パニックの度合いは大きく変わります。
「災害発生!その時、透析患者が取るべき行動」に基づき、時系列の行動を以下に整理します。
| フェーズ | 行動の優先順位 | 詳細な行動 / 留意点 |
|---|---|---|
| ❶ 災害発生直後 | 身の安全確保(揺れが収まるまで) | 透析中はスタッフの指示に従う。慌てて針を抜かない。火の始末。靴/スリッパで足元保護。 |
| ❷ 状況安定後 | 情報収集と連絡 | 携帯品(透析カード/お薬手帳)を確認。透析施設への連絡(事前に確認した複数手段を試す)。回線混雑を考慮し、災害用伝言ダイヤル(171)やSNSも活用。 |
| ❸ 避難が必要な場合 | 適切な避難先の選定 | 自宅の安全を確認。福祉避難所や受け入れ可能な施設を事前に確認しておくのが理想。一般避難所では食事・水分の管理、衛生面、プライバシー確保に課題があることを認識。 |
| ❹ 避難所生活 | 自己管理と情報伝達 | 自分が透析患者であることを運営スタッフに明言し、食事・水分制限の配慮を依頼。持参の備蓄食を活用。手洗いやマスクで感染症対策を徹底。 |
まずは落ち着いて身の安全確保
地震であれば、まず揺れが収まるまで、丈夫なテーブルの下に隠れるなど、身を守る行動を最優先してください。透析中であれば、スタッフの指示に従いましょう。慌てて針を抜いたり、動き回ったりするのは危険です。
揺れが収まったら、周囲の状況を確認し、火の始末(もし使っていれば)をします。ガラスの破片などで怪我をしないように、足元にも注意してください。可能であれば、枕元や防災リュックに、スリッパや靴を入れておくと良いでしょう。
透析施設への連絡 – いつ、どうやって?
身の安全が確保できたら、次は透析施設への連絡を試みましょう。ただし、災害直後は回線が非常に混雑します。すぐには繋がらない可能性が高いです。
事前に確認しておいた連絡方法(電話、SNS、災害用伝言ダイヤルなど)を試してみてください。繋がらない場合は、少し時間をおいてから再度試みるか、別の手段を探しましょう。
重要なのは、「自分の安否」と「透析の必要性」を伝えることです。もし、施設に連絡がつかない場合でも、自治体や地域の災害対策本部、あるいは近隣の病院などに相談することで、情報が得られたり、支援に繋がったりする可能性があります。諦めずに、情報を求めて動き続けることが大切です。
避難所での生活 – 透析患者が気をつけること
もし避難所での生活を余儀なくされた場合、透析患者にとっては、普段以上に厳しい環境になることを覚悟しなければなりません。しかし、ここでも事前の知識と準備が役立ちます。
食事と水分 – 周囲への伝え方
避難所で配給される食事は、多くの場合、透析患者の食事制限に配慮されていません。おにぎりやパン、カップ麺など、塩分やカリウムが多いものが中心になりがちです。
まず、自分が透析患者であり、食事制限(特にカリウム、リン、塩分、水分)が必要であることを、避難所の運営スタッフや、食事を提供してくれるボランティアの方に、はっきりと伝えましょう。可能であれば、持参した「透析カード」や「お薬手帳」を見せると、より理解してもらいやすくなります。
とはいえ、特別な食事を用意してもらうのが難しい場合も多いでしょう。その場合は、配給された食事の中から、比較的制限に引っかかりにくいものを選んで食べる、持参した非常食を活用する、などの工夫が必要です。例えば、おにぎりなら中の具材(昆布や梅干しは塩分・カリウムが多い)を避ける、パンなら菓子パンより食パンを選ぶ、汁物は飲まない、など、できる範囲での自己管理が求められます。
水分についても同様です。「水は自由に飲んでください」と言われても、自分の制限量を守る必要があります。これも、周囲に「自分は水分制限がある」と伝えておくことが大切です。誤解を避けるためにも、コミュニケーションは積極的に取りましょう。
衛生管理と感染症対策
避難所は、多くの人が密集して生活するため、衛生環境が悪化しやすく、感染症のリスクも高まります。
透析患者は、免疫力が低下している場合もあり、感染症にかかると重症化しやすいため、特に注意が必要です。
- 手洗いや手指消毒をこまめに行う(ウェットティッシュや消毒ジェルを備蓄しておくと便利)
- マスクを着用する
- シャント肢(透析のための血管)を清潔に保ち、傷つけないように注意する
- できるだけ換気の良い場所にいるように心がける
- 体調の変化(発熱、咳、下痢など)があれば、すぐにスタッフに申し出る
これらの基本的な対策を徹底することが、自分自身を守ることに繋がります。周りに気を遣いすぎる必要はありません。自分の健康が第一です。
「いつも」の備えが「もしも」を救う – 日常からできること
災害への備えは、特別なことではありません。日々の生活の中で、少しだけ意識を変えるだけで、できることはたくさんあります。
「透析施設との連携」と「日常からできること」をまとめます。
| 連携対象 | 事前に確認・共有すべき事項 |
|---|---|
| 透析施設 | 災害時の連絡方法(電話、SNS、ウェブサイト等)。安否確認の方法。透析中断時の近隣連携施設情報。透析条件カードの発行。 |
| 主治医/管理栄養士 | 薬の予備日数(1週間分など)の相談。災害時の水分制限量の目安。低カリウム・低リンの非常食リスト作成。 |
| 家族/周囲 | あなたが透析患者であることと特別な配慮(制限)が必要な点の共有。緊急時の連絡先や薬の場所、透析施設情報を共有。 |
| 自治体/地域 | ハザードマップの確認。透析患者を受け入れ可能な福祉避難所の有無。地域の防災訓練への参加。 |
家族や周囲との情報共有
あなたが透析患者であること、災害時に特別な配慮が必要なことを、家族や親しい友人、職場の同僚など、身近な人に伝えておきましょう。緊急連絡先や、かかりつけの透析施設の場所、普段服用している薬の情報などを共有しておくことも大切です。
いざという時、あなた自身が動けなくても、周りの人が状況を理解し、適切なサポートをしてくれる可能性が高まります。「迷惑をかけるかも」なんて思わずに、オープンに話しておくことが、結果的にあなたと周りの人、双方の助けになります。
かかりつけ医・透析施設とのコミュニケーション
これはもう、耳にタコができるほど言っていますが(笑)、本当に重要なので、もう一度。普段の通院時から、主治医や看護師、臨床工学技士、管理栄養士といった専門スタッフと、良好なコミュニケーションを築いておくことが、何よりの防災対策になります。
体調の変化や不安なこと、災害時のことなど、何でも気軽に相談できる関係性を作っておきましょう。専門家からの的確なアドバイスは、あなたの不安を和らげ、具体的な備えを進める上で、大きな力になります。
地域の防災訓練への参加のススメ
お住まいの地域で行われる防災訓練には、ぜひ積極的に参加してみてください。避難所の場所や避難経路を確認したり、地域住民との顔つなぎができたりするだけでなく、災害時のリアルな雰囲気を体験することができます。
訓練に参加することで、「自分には何が足りないか」「もっとこうしておけば良かった」といった、具体的な課題が見えてくることもあります。透析患者であることを伝え、配慮が必要な点を相談してみるのも良い経験になるでしょう。あの、ちょっとした「やってみた」経験が、本番での冷静な行動に繋がるんです、絶対。
不安を乗り越えて – 先輩透析患者の体験談
ここまで、たくさんの備えや行動についてお話ししてきましたが、それでもやっぱり不安は残るかもしれません。最後に、災害を乗り越えた先輩透析患者の声をお届けしたいと思います。
「あの時、これがあって助かった!」リアルな声
「透析導入してまだ半年くらいの時に、大きな地震に遭いました。家の中はぐちゃぐちゃ、電気も水道も止まってしまって…。頭が真っ白になりましたが、クリニックでもらっていた『災害時連絡カード』と『お薬手帳』だけは、いつも財布に入れていたんです。それが本当に命綱になりました。避難所で、他の病院で臨時透析を受けることになったんですが、そのカードがあったおかげで、スムーズに治療してもらえたんです。あの時、ちゃんと携帯しておいて良かった、って心底思いましたね。」(Aさん・男性)
「うちは、夫が透析してるんですけど、災害用の備蓄食は、普段から二人で選んでました。管理栄養士さんに相談して、低カリウム・低リンのレトルト食品とか、栄養補助食品とかをいくつかストックして。被災して、避難所ではなかなか思うような食事が摂れなかった時、その備蓄食が本当に役に立ちました。『食べられるものがある』っていう安心感は、精神的にも大きかったです。あと、モバイルバッテリー!スマホで情報を集めたり、クリニックと連絡取ったりするのに、絶対必要でした。」(Bさん・女性・家族)
備えがあったからこそ乗り越えられた
「正直、災害前は『透析患者が災害に遭ったら、もう終わりだ』くらいに思ってました。でも、実際に被災してみて、もちろん大変だったけど、『備えがあれば、なんとかなる』って実感できたんです。薬の予備、最低限の食料と水、そして何より『情報』。事前に調べて、準備していたことが、パニックにならずに行動できた理由だと思います。透析仲間の存在も大きかったですね。お互いに声を掛け合って、情報を共有して…一人じゃないって思えたことが、心の支えになりました。」(Cさん・男性)
いかがでしたか?
透析と災害。この二つが重なることは、想像するだけで大きな不安を感じるかもしれません。でも、正しい知識を持ち、具体的な備えをしておくことで、その不安は確実に減らすことができます。「自分にはできない」なんて思わないでください。今日、この記事を読んだことが、あなたの「備え」の第一歩です。
小さなことからで構いません。まずはお薬手帳と透析条件の確認から。そして、家族や施設とのコミュニケーション。一つ一つ、できることから始めてみませんか?あなたのその一歩が、「もしも」の時に、あなた自身と、あなたの大切な人を守る力になるはずです。
応援しています。一緒に、乗り越えていきましょう。