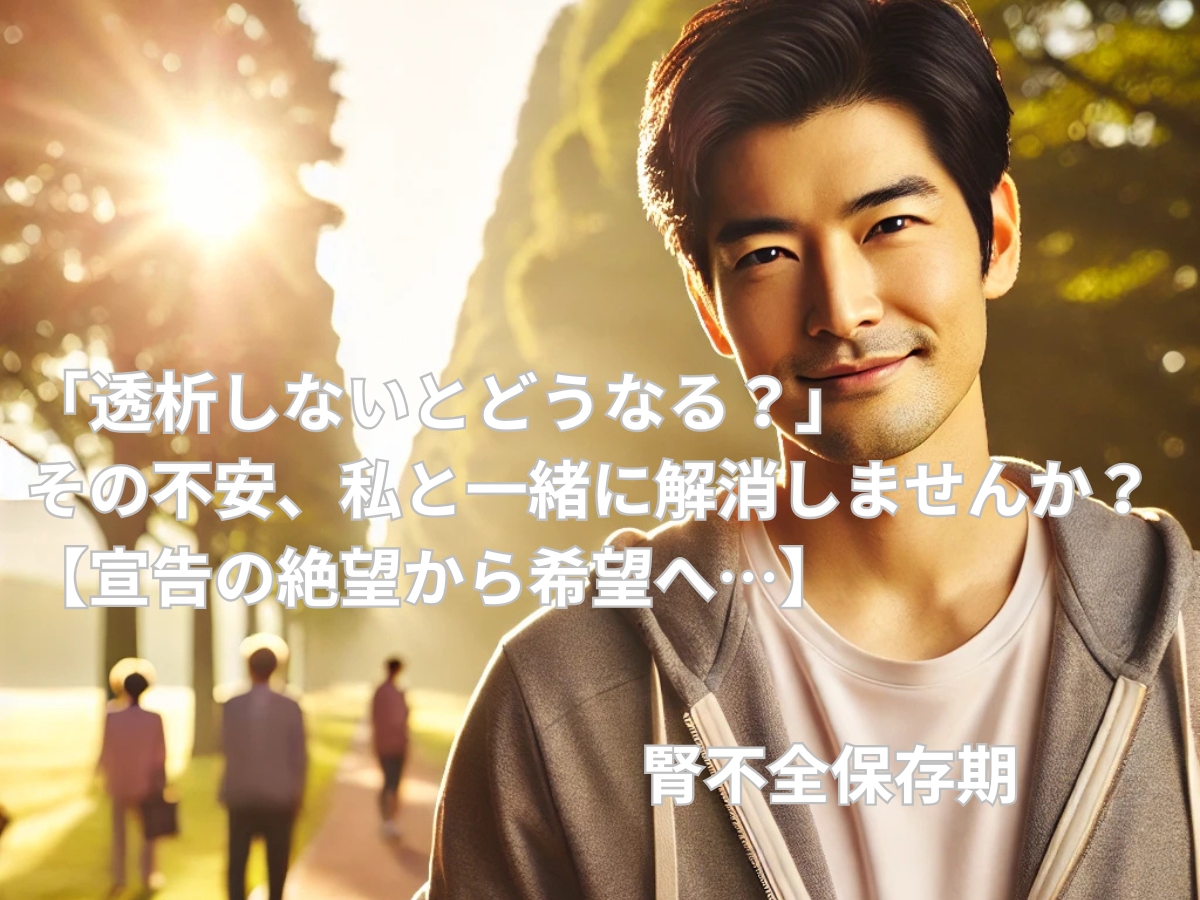
「透析が必要です」――。突然の宣告に、頭が真っ白になっていませんか? 「透析しないとどうなるんだろう」「これから私の人生はどうなるの?」そんな不安で、夜も眠れないかもしれませんね。何を隠そう、20年以上透析を続けている私も、最初は同じでした。目の前が真っ暗になったような、あの感覚…痛いほど分かります。
でも、安心してください。この先には、あなたが想像するよりもずっと普通の、そして充実した生活が待っています。この記事では、透析歴20年超の私が、あなたの抱える「透析」への疑問や不安に、患者目線でとことん向き合います。一緒に、希望の光を見つけましょう。
「透析」って、そもそも何のためにするの? 腎臓の働きと腎不全
まず、ちょっとだけ体の仕組みの話をさせてください。難しい話は抜きにして、できるだけ分かりやすくお伝えしますね。私たちの体には「腎臓」という、そら豆みたいな形をした臓器が2つあります。これがもう、本当に働き者なんですよ。
主な仕事は、血液をろ過して、体の中の老廃物や余分な水分を尿として体の外に出すこと。まるで、高性能なフィルターみたいなものですね。血液をキレイにしてくれるおかげで、私たちは元気に活動できるわけです。他にも、血圧を調整したり、血液を作るホルモンを出したり、骨を丈夫にするビタミンDを活性化したり…本当に色々な仕事をしてくれています。地味だけど、めちゃくちゃ重要な役割を担っている、縁の下の力持ちなんです。
ところが、何らかの原因でこの腎臓の働きが弱ってしまうことがあります。徐々に機能が低下していって、健康な時の30%以下になると「腎不全」と呼ばれる状態になります。フィルターが目詰まりを起こして、うまく血液をろ過できなくなっちゃうイメージですね。そうなると、体の中に老廃物や余分な水分がどんどん溜まって、様々な不調が現れてきます。
そして、腎臓の機能が10%以下くらいまで低下してしまうと、自分の腎臓だけでは生命を維持することが難しくなってくる。この段階を「末期腎不ح全」と呼びます。こうなると、腎臓の代わりに血液をキレイにする治療が必要になるんです。それが「透析療法」なんですね。
…なんて、今でこそこうやって説明できますけど、私も最初に先生から説明を受けたときは、正直ちんぷんかんぷんでした。「ジンフゼン?トウセキ?」って感じで。ショックの方が大きくて、内容なんてほとんど頭に入ってこなかったのを覚えています。だから、今あなたが不安に思う気持ち、すごくよく分かりますよ。
もし透析をしなかったら… 体はどうなるの?
「透析しないと、どうなっちゃうんだろう…」これは、誰もが最初に抱く、一番大きな不安だと思います。私もそうでした。「なんとかならないかな」「透析以外の方法はないのかな」って、必死で考えました。でも、末期腎不全の状態で透析を受けずにいると、残念ながら体はどんどん深刻な状態になっていきます。
具体的にどんなことが起こるかというと…
老廃物が体に溜まる(尿毒症)
腎臓が機能しないと、血液中の老廃物(尿素窒素やクレアチニンなど)が排出されずに、体の中にどんどん蓄積していきます。これが「尿毒症」と呼ばれる状態です。なんだか怖い名前ですよね…。症状としては、吐き気や食欲不振、頭痛、倦怠感、かゆみなどが現れます。ひどくなると、意識障害やけいれんを起こすこともあって、命に関わる危険な状態になります。体が内側から悲鳴を上げているような感じ、と言えば伝わるでしょうか。
余分な水分が溜まる(むくみ、心不全、肺水腫)
おしっこの量が減って、飲んだ水分がうまく排出されなくなると、体の中に水分が溜まってしまいます。最初は足や顔のむくみ(浮腫)として現れることが多いですね。私も導入前は、靴下の跡がくっきり残ってなかなか消えなかったり、まぶたが腫れぼったくなったりしていました。「ちょっと太ったかな?」くらいに思っていたんですが、あれがサインだったんですね…。
さらに水分が溜まると、心臓に負担がかかって「心不全」を起こしたり、肺に水が溜まって呼吸が苦しくなる「肺水腫」になったりする危険があります。肺水腫は、息ができなくなるような、非常につらい状態です。溺れているような感覚、と表現する人もいます。
電解質のバランスが崩れる(高カリウム血症など)
腎臓は、ナトリウムやカリウム、カルシウム、リンといった「電解質」のバランスを調整する役割も担っています。腎機能が低下すると、このバランスが崩れてしまうんです。
特に危険なのが「高カリウム血症」。血液中のカリウム濃度が高くなりすぎると、不整脈や心停止を引き起こす可能性があります。カリウムは、果物や野菜、イモ類などに多く含まれているので、腎臓が悪くなると食事制限が必要になるのは、これが大きな理由の一つです。私もカリウム制限には長年苦労しています。大好きな果物も、量を気にしないといけないのは、正直ちょっと寂しいですけどね。でも、自分の体を守るためですから。
貧血が進む
腎臓は「エリスロポエチン」という、赤血球を作るように指令を出すホルモンを作っています。腎機能が低下すると、このホルモンの分泌が減ってしまい、赤血球が十分に作られなくなって貧血になります。透析患者さんに貧血が多いのはこのためです。貧血になると、だるさや息切れ、めまいなどの症状が出やすくなります。私も透析導入当初は、階段を上るだけで息が上がって大変でした。
…と、少し怖い話になってしまいましたが、これが透析をしない場合に起こりうることです。透析は、これらの危険な状態を防ぎ、失われた腎臓の働きを補うために必要不可欠な治療なんです。決して「罰」なんかじゃなくて、生きていくための、そして、あなたらしい生活を取り戻すための「手段」なんですよ。
なぜ私が? 透析が必要になる主な原因
「どうして自分が透析にならなきゃいけないんだ…」そう思う方も多いでしょう。透析に至る原因は人それぞれですが、主なものとしては、以下の3つの病気が挙げられます。
糖尿病性腎症
これは、糖尿病の合併症として腎臓が悪くなるケースです。血糖値が高い状態が長く続くと、腎臓の細い血管(糸球体)がダメージを受けて、ろ過機能が低下していきます。実は、現在、日本で透析を始める原因として最も多いのが、この糖尿病性腎症なんです。生活習慣病と言われる糖尿病が、腎臓にも大きな影響を与えるんですね。私も会社の健康診断で血糖値が高めだと言われ続けていた時期があって…もっと早くから気をつけていれば、と後悔したこともありました。
慢性糸球体腎炎
腎臓の糸球体という部分に、慢性的な炎症が起こる病気です。免疫の異常などが原因と考えられていますが、はっきりとした原因が分からないことも多いようです。学校の検尿でタンパク尿や血尿を指摘されて、この病気が見つかるケースもあります。昔はこちらが透析導入原因のトップだったんですが、最近は糖尿病性腎症に次いで2番目になっています。
腎硬化症
これは、高血圧が長く続くことによって、腎臓の血管が動脈硬化を起こし、腎機能が低下する病気です。高血圧も自覚症状が出にくいので、気づかないうちに腎臓に負担をかけていることがあります。血圧の管理って、本当に大事なんですよね…。
他にも、多発性のう胞腎という遺伝性の病気や、膠原病、薬剤の影響など、様々な原因で腎機能は低下します。
あ、でも、ここで一つ強調しておきたいのは、透析になったからといって、「自分が何か悪いことをしたせいだ」とか「自己管理ができなかったからだ」なんて、自分を責めないでほしいということです。もちろん、生活習慣が関わっている場合もありますが、病気の進行は体質や他の要因も複雑に絡み合っています。誰のせいでもない、という場合だってたくさんあるんです。
私の場合は、若い頃の不摂生も多少は影響したかもしれませんが(笑)、主な原因は慢性糸球体腎炎でした。発見されたときは、もうかなり進行していて…。だから、原因が何であれ、今は前を向いて、治療とどう向き合っていくかを考えることが大切だと、私は思っています。
透析って、具体的にどんな治療をするの?
透析療法には、大きく分けて「血液透析」と「腹膜透析」の2種類があります。どちらを選ぶかは、体の状態や生活スタイル、価値観などによって、医師と相談しながら決めていくことになります。簡単にですが、それぞれの特徴を見てみましょう。
血液透析(HD:Hemodialysis)
これは、体から血液を取り出して、「ダイアライザー」と呼ばれる人工の腎臓(フィルター)に通して、老廃物や余分な水分を取り除き、キレイになった血液を再び体に戻す治療法です。多くの場合、週に3回、1回あたり4~5時間ほど、病院やクリニックなどの透析施設に通って行います。
治療を受けるためには、腕の血管を手術して、たくさんの血液を効率よく取り出せるように「シャント」というものを作る必要があります。このシャント、透析患者にとってはまさに「命綱」なんですよね。私もこの左腕のシャントと共に、もう20年以上過ごしています。
血液透析のメリットとしては、医療スタッフが治療を行ってくれるので安心感があること、施設で行うため自宅に特別なスペースや設備が不要なことなどが挙げられます。デメリットとしては、週3回の通院が必要で時間的な制約があること、毎回針を刺す痛みがあること、食事や水分の制限が比較的厳しいことなどがあります。
私も血液透析を選択しています。会社勤めをしているので、週3回の通院は正直、大変な時もあります。でも、治療中は読書をしたり、仕事をしたり、最近はタブレットで映画を見たりして、自分なりに時間を有効活用するようにしています。まあ、ぶっちゃけ、寝てることも多いですけどね(笑)。
腹膜透析(PD:Peritoneal Dialysis)
こちらは、自分のお腹の中にある「腹膜」をフィルターとして利用する治療法です。お腹にカテーテルという細い管を埋め込む手術をして、そのカテーテルから透析液をお腹の中に入れます。一定時間お腹の中に溜めておくことで、腹膜を通して血液中の老廃物や余分な水分が透析液に移動します。その後、老廃物などが溶け込んだ透析液を体の外に出して、新しい透析液と交換します。
この透析液の交換(バッグ交換)は、基本的には自宅や職場で自分自身または家族が行います。1日に数回(通常3~5回)、1回の交換に30分程度かかるのが一般的です。夜寝ている間に機械が自動で交換してくれる「APD(自動腹膜透析)」という方法もあります。
腹膜透析のメリットは、通院が月1~2回程度で済むこと、時間や場所に縛られにくく、比較的自由な生活を送りやすいこと、血液透析に比べて食事や水分の制限が緩やかな傾向があることなどです。デメリットとしては、自己管理が重要であること、カテーテル出口部の感染や腹膜炎のリスクがあること、長期間続けると腹膜の機能が低下して、いずれ血液透析への移行が必要になる場合が多いことなどが挙げられます。
どっちが良いか、というのは本当に人それぞれ。生活スタイル、性格、体の状態…色々なことを考慮して、先生や家族とじっくり話し合って決めるのが一番です。途中で変更することも可能ですしね。私も導入時には、腹膜透析も選択肢として説明を受けました。在宅でできるのは魅力的でしたが、当時の私は自己管理にあまり自信がなくて(苦笑)、結局、血液透析を選びました。
押し寄せる不安の波… どう乗り越えたか(私の体験談)
さて、ここまで透析の基本的な情報をお伝えしてきましたが、一番知りたいのは、きっと「この不安とどう向き合えばいいのか」ということかもしれませんね。
私が透析導入を告げられたのは、20代後半の頃でした。仕事もプライベートもこれから、という時期。まさに青天の霹靂でした。当時は介護職をしていましたが、介護することが天職とも思っていました。「これからも続けたい」という気持ちもあったにも関わらず「透析=人生どうなっちゃうの?」ってみたいに感じてしまって、絶望感でいっぱいになりました。(介護職してますから、介護される方々の立場、気持ちというのも分かっていたのですが・・・)何だか夜も眠れず、食事も喉を通らず…。「なんで俺が…」「これからどうなるんだ…」ってばかり考えていましたね。
当時、両親や兄弟姉妹には心配をかけまいと気丈に振る舞ってはいましたが、内心はホントに不安で押しつぶされそうでした。
何が一番不安だったかというと、「制限だらけの生活になるんじゃないか」「好きなことができなくなるんじゃないか」「周りに迷惑をかけるんじゃないか」…そういう漠然とした、でも強烈な不安でした。
でも、実際に透析を始めてみると、もちろん時間とか食事といった”制限”をはじめとして大変なことはたくさんありましたけど、「あれ?意外と普通に生活できるじゃん」と思う場面も多かったんです。
透析導入直後は、体調の変化についていくのが大変でした。透析後のだるさとか、血圧の変動とか…。食事制限も、最初は本当に戸惑いました。カリウム、リン、塩分、水分…何をどれだけ食べていいのか、さっぱり分からなくて。
管理栄養士さんに相談したり、透析仲間におすすめのレシピを教えてもらったりしながら、少しずつ慣れていきました。(大前提として、慢性腎臓病のステージ3までは食事療養を徹底してきて、何とか腎機能低下を阻止するようには務めてきましたし、慢性腎臓病と透析とでは違ってきます。)
今では、外食だって工夫すれば楽しめますし、低カリウムの果物を選んだり、調理法を工夫したりして、食生活もそれなりに楽しんでいますよ。まあ、たまに無性にラーメンとか食べたくなりますけどね!そういう時は、リン吸着薬をちゃんと飲んで、ちょっとだけ…とか(笑)。自己判断は禁物ですけど、たまの息抜きも大事かな、なんて。
仕事の方はというとは、「就職氷河期+障害者」とが重なり転職活動が長引いてしまいました。そもそも、透析導入を機に”働き方”を見直す必要はありました。自宅から車で通える病院と会社選びを重視しました。ネットで探せるような時代でもなかったですから、真っ先にハローワークに通い詰めていましたね。
こうして何とか会社の理解もあって転職することができました(ただ、最初の会社については通院時間のためのオーバー、治療時間が短くなり入室することが遅くなっていくなどもあり、働きながら再転職を目指すことになりました)。今では15年超働き続けることができています。もちろん、透析日以外は残業すすることもありますし、朝の車通勤は精神的・体力的にキツい時もあります。でも、周りのサポートに助けられながら、なんとかやっています!
一番大きかったのは、「一人じゃない」と思えたことかもしれません。病院のスタッフの方々、特に看護師さんや臨床工学技士さんは、いつも親身になって話を聞いてくれましたし、同じように透析を受けている仲間との出会いも大きかったです。休憩室で交わす何気ない会話の中で、「あ、悩んでるの、自分だけじゃないんだな」って思えただけで、すごく心が軽くなったのを覚えています。
不安が完全になくなることはないかもしれません。でも、透析を受けながらでも、できることはたくさんあるし、新しい楽しみだって見つけられる。そう思えるようになったのは、透析を始めてしばらく経ってからでした。焦らなくていいんです。少しずつ、自分のペースで、新しい生活に慣れていけばいいんですよ。
絶望の淵から見えた希望の光 ~透析と生きるということ~
透析導入は、確かに人生の大きな転機です。ショックや不安を感じるのは、当然のことだと思います。でも、決して「終わり」ではありません。むしろ、新しい人生の「始まり」と捉えることだってできるかもしれない。
「透析患者は、あれもこれもできない」そんなイメージを持っている人もいるかもしれません。でも、それはちょっと違う。もちろん、健康な時と同じように、とはいきません。食事や水分に気を配る必要があるし、定期的な通院や治療は欠かせません。体調管理にも、より一層の注意が必要です。
でもね、工夫次第で、できることは本当にたくさんあるんです。
- 仕事: 体調に合わせて働き方を調整したり、職場の理解を得たりする必要はありますが、仕事を続けている人はたくさんいます。私もその一人です。
- 旅行: 事前に計画して、旅先で透析を受けられる施設(臨時透析、旅行透析)を予約すれば、国内旅行も海外旅行も可能です。私も何度か、家族と旅行に行きましたよ。透析があるからって、諦める必要はないんです。
- 趣味やスポーツ: 体調に合わせて、軽い運動や趣味を楽しむことも十分可能です。ウォーキングやストレッチ、筋トレ(無理のない範囲で!)などを続けている仲間もいます。大切なのは、主治医と相談しながら、自分に合ったペースを見つけることですね。
透析生活は、確かに「制限」もあります。でも、その中でどうやって「自分らしく」生きていくか、どうやって「QOL(生活・人生の質)」を高めていくか。それを考えることが、すごく大事なんだと、私は20年以上の透析生活を通して感じています。
それに、今は様々なサポート体制も整っています。医療費の助成制度(特定疾病療養受療証や更生医療、重度心身障害者医療費助成など)や、障害年金、身体障害者手帳の取得による各種サービスなど、経済的な負担を軽減するための制度があります。手続きがちょっと複雑だったりするので、病院のソーシャルワーカーさんや、役所の担当窓口に遠慮なく相談してみてください。こういう制度をしっかり活用することも、安心して治療を続けるためにはとても重要です。
あ、そうだ、食事に関しても、最近は透析患者さん向けの美味しい宅配弁当サービスなんかも増えてきていますよね。栄養計算されていて、塩分やカリウム、リンが調整されているので、毎日の食事作りの負担を減らしたい、という方にはすごく助かるんじゃないでしょうか。私も時々利用しています。これがまた、結構美味しいんですよ!
最後に伝えたいこと ~あなたは一人じゃない~
透析宣告を受けて、今、不安や絶望の中にいるかもしれません。未来が見えないように感じているかもしれません。
でも、どうか思い出してください。あなたは決して一人ではありません。
家族、友人、そして医師や看護師、臨床工学技士、管理栄養士、ソーシャルワーカーといった医療チームが、あなたのそばにいます。そして、私のように、同じ透析という治療を受けながら、日々を生きている仲間がたくさんいます。
透析は、あなたの腎臓の代わりをしてくれる、大切なパートナーです。上手に付き合っていけば、きっと、あなたらしい人生を続けることができます。
焦らず、比べず、諦めず。一歩ずつ、あなたのペースで進んでいきましょう。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、前を向くための小さなきっかけになれたら、こんなに嬉しいことはありません。応援しています。